米国では、ケーブルモデム、xDSL、衛星などのワイヤレスアクセス、さらに電力線を利用した1.5Mbps以上のブロードバンドアクセスサービスが多様化し、本格的な競争が展開しつつある。プロバイダーは、異なる技術のポジショニング、統合化、運用管理面の高度化、カスタマーへのサービス提供方法などを検討していく必要が出てきている。1998年はブロードバンドアクセスサービスが大きく進展していく年となるであろう。
MCI社のManager, Claire A. Lewisは、プロバイダーからみたブロードバンドアクセス技術を以下の点から重要であると考えている。
- カスタマーベースの維持と新規ユーザーの開拓
- 規制緩和と技術の融合
- トータルコストオブオーナーシップの削減
- サービスパッケージ/バンドリング
また、カスタマーからみたブロードバンドアクセスサービスの選択要因に以下のような項目を指摘している。
- ビジネスセクター
- 帯域幅のパフォーマンス
- フルタイムでの利用可能性
- サービスレベルアグリーメント
- 信頼性
- 料金
- 既存網との統合
- サービス品質
- 個人セクター
- 使いやすさ
- 技術的透過性
- 応答時間(帯域幅/接続速度)
- 利用可能性
- 情報/娯楽の価値
ブロードバンドアクセスの、主なアプリケーションはインターネットアクセスと企業LANへのリモートアクセスであり、既存のカスタマーベースの維持と新規市場の開拓をめぐって激しい競争が展開されていく。プロバイダーは、サービスのバンドル化による提供可能なサービスのコスト削減と追加収入増によるトータルでの競争を展開していく、すなわち、レイヤーから見れば、ダークファイバーから、通信回線、通信サービス、IPベースのサービスまでマルチレイヤーで、卸・小売などのビジネスを展開していく。通信サービスだけ見ても、Chip Setによるアナログ56kbpsモデム接続からADSL1.5Mbps接続までの一体的なフレキシブルな提供が必須となっている。これに対応するため、米国のインターネットサービスプロバイダーは、xDSLを利用していくため電話会社に通信設備をコロケーションする必要があり、CLEC(Competitive Local Exchange Carrier):通信キャリアーとして、その業態を変化させつつある。同時に長距離通信事業者による合併・提携が行われている。
ブロードバンドアクセス技術の中で、FTTC(ファイバーツーザカーブ)は、まだ投資コストが高く、サービス提供可能距離も3,000フィート以内と都市部の一部のビジネス向けに限定されている。ワイヤレスでは周波数を再利用してもブロードバンド向けではスペクトラムに限界がある。衛星はブロードキャストサービス、短期的なサービス提供、人口密度が低い地域と固定網のバックアップとしては最適であるが、双方向性アプリケーションを固定網と競争していくにはまだ不効率である。したがって、当面は、主な競争の局面は、通信インフラである56kbpsまでのアナログモデムから、ISDN、xDSL、専用線などの通信インフラ内でのサービス間競争と、xDSL対ケーブルモデムに絞られる。
■通信インフラ内でのサービス間競争:400kbpsの標準サービスの進展
カスタマーの帯域幅への要望を、各アプリケーションの送受信時間(秒)と判断すると、Eメールではアナログモデムでも問題ないが、デジタル画像やWordファイルの転送には不十分であることがわかる。遠隔医療やリモートLANアクセスには6Mbps以上の速度が必要である。
|
ファイル
サイズ
kバイト |
28.8kbps
モデム |
128kbps
ISDN |
384
kbps |
768
kbps |
1544
kbps |
6144
kbps |
| Eメール |
30 |
8.3(秒) |
1.9(秒) |
0.63(秒) |
0.31(秒) |
0.16(秒) |
0.04(秒) |
|
| デジタル画像 |
125 |
34.7 |
7.8 |
2.6 |
1.3 |
0.6 |
0.2 |
| Wordファイル |
250 |
69.4 |
15.6 |
5.2 |
2.6 |
1.3 |
0.3 |
遠隔医療
X線 |
5,000 |
23.1分 |
5.2分 |
1.7分 |
52.1 |
25.9 |
6.5 |
リモートLAN
バルクファイル |
20,000 |
1.5時間 |
20.8分 |
6.9分 |
3.5分 |
1.7分 |
26.0 |
今日のインターネットではスループットに限界がある。すなわち、TCP/IPであること、ルーター遅延、パケット・フラグメンテーション、サーバーのパフォーマンス、PCなどの限界により、400-600kbps程度のスループットしか実現できない。すなち、アクセス速度が300-500kbpsを超えた時点でパフォーマンスの向上に大きな変化はないとみられている(Orkit Communication社Nigel Cole氏)。したがって、現時点では、いくらアクセス速度を高速にしてもインターネットアクセスでの利用は価値がない。
ISDN128kbsでは、リアルタイムビデオ会議、Webホスティング、ビデオストリーミング、ビデオオンデマンドなどの利用は在宅勤務者には困難である。しかし、ADSLを導入すれば、企業ネットワークを在宅勤務者、ブランチオフィス、ビジネスパートナーと1.5MbpsのT1速度でアクセスを可能とする。ADSLはポイントツーポイントで"always on"(常時接続)で専用線のように利用できる。また、回線交換ではないのでプロバイダーのPOPでトラヒック混雑によるパフォーマンスへの悪影響を受けることはない。この点が、ローカルループに流れているダイヤルアップインターネットトラヒック量に影響を受けるISDNとは異なる。企業PBX回線とホームオフィスを直接接続するデジタル電話サービスを追加したり、データ通信では、アプリケーションに必要な帯域幅に応じてスケールアップをフレキシブルに提供することが可能となるため、プロバイダーはADSLを特定のアプリケーションを実現する必要十分な帯域幅に応じた料金設定をしていくことが可能となる。例えば、利用ユーザー数、データサービスや付加価値サービスの種類に応じた料金設定などである。
したがって、インターネットアクセスでの利用では384kbpsのxDSLサービス、企業LANアクセスでは1.5MbpsのHDSL(High-bit-rate DSL)サービスが中心となっていくことが予想される。
■xDSL対ケーブルモデム
米国の調査会社では、XDSL、ケーブルモデムともに2001-2002年には、それぞれ300万程度の普及を予測している。なお、ADSL/RADSL回線は89万、G.Lite/Universal回線は220万と予測している。
XDSLとケーブルモデムの比較
| XDSL | ケーブルモデム |
| インフラコスト | 導入に支障ない | 導入に支障ない |
| サービス料金 | やや高い(384kbpsで月80ドル) | 安い(月30-60ドル) |
| 世帯普及率 | 95%以上 | 65%以上 |
| 非対称速度 | あり | あり |
| 対称速度 | あり | なし |
| セキュリティー | スウィッチド回線で優れている | 帯域幅の共有でやや難ある |
| 距離 | 18kft以内と限界あり | - |
| 速度(保証なし) | フル:6Mbps/640kbps
Lite/Universal:1.5Mbps/384kbps | 30Mbpsまで可能、
1.5Mbps/300kbps |
| トポロジー | 専用、増設容易 | 共有(300-1000世帯) |
| ISP | 選択可能 | ケーブルTV |
| 家庭での導入 (Liteの場合) | 簡単、既存のインサイドワイヤーを利用、エンドユーザー自身の設置 | 複雑、新規"Home Run"ケーブル、PCのシステム設定が必要。使用機器が少ないので維持管理が簡単 |
| モビリティー | 可能 | 難あり |
| 複数送信先の利用 | 可能 | 難あり |
Telechoice社の調査結果によれば、ADSL普及の問題点として”相互運用性がない”という理由が最も大きく、次いで”利用距離の限界”、スケーラビリティーとスペクトラムのコンパチビリティーなどを指摘している。相互運用性という点に関して、ADSL.Lite/Universal ADSL Working Group(UAWG)などの結成によるエンドエンドでの接続性の確保、CPEの設置など運用上の課題を克服しつつある。Lucent Technologies社はPCで従来のアナログでもDSLサービスでもインターネットにアクセスできるDSL Chip setを発表した。Lucent 1690DSP、ADSL codec、アナログモデムcodecで構成されるThree-chip WildWire chip setはLucent社のWildWire DSL"Lite"技術によるスプリッターレスで1.5Mbpsまでを可能とするADSLとV.90をサポートしている。CO(電話局)がDSL接続で利用可能な最高速度でデータ伝送できるかどうか調べる自動探索機能を備えており、PCを56kモデムとDSLの間で再設定し直して利用する必要がない。
また、プロバイダー側からみれば、クラス5スウィッチとの統合によるFTTCへの移行が容易である。ATU-C(ADSL Transmission Unit Central)とCO(電話局)スウィッチの統合化が進展しCOをベースとしたADSLソリューションは運用面、管理面、維持管理などでの提供コストが節約可能となっていく。
したがって、インターネットユーザーからの追加収入を期待しているケーブルモデムは個人ベースの企業か、娯楽番組中心の一般家庭ユーザーを中心に進展し、一般企業向けへの普及には、バックアップなど特殊な利用形態を除いて、その普及には疑問が残る。現時点では、やや普及が遅れているxDSLはChip Setを組み込み2002年以降急速に浸透していくと思われる。ただ、地域コミュニティーの情報や一般家庭での(教育・文化等の)情報や娯楽をベースとする利用ではケーブルモデムが主体となる可能性がある。
■xDSLを利用した新規キャリアーの挑戦:XCOM+Level3
ADSL技術のアプリケーションとして、通信キャリアーがISP向けにADSL回線の卸売りがある。その例として、IPネイティブバックボーンプロバイダーであるLevel3 Communications社が買収したマサチュセッツ州ベースのCLECであるXCOM Communications社ではISP向けにカスタマーからISPのホストまでの通信回線を卸売りしている。市内電話で56kbpsまでのアナログダイヤルアップ、ISDNアクセスサービス、企業網へのリモートアクセス、VPNサービスをISPに提供している。現在、PSINet社、Prodigy社などにを提供している。1998年には、ISP向けに768kbps DSLサービス、インターネット電話などをリセールしていく。
Ascend Communication社との共同で開発したXCOM社固有のゲートウェイ(Ascend社のMax-TNT)で、出来るだけカスタマーに近い地点で通話をIPパケットに変換し、最もトラヒックが混雑しているPSTNのタンデム交換機をバイパスしている。COスウィッチからパケットベースIP機器にデータトラヒックを切り離し、"Data Center" (EDS4/5とノーザンテレコム社のDMS500スウィッチ)に伝送していく。スウィッチングはCOベースのスウィッチではなく"Data center"で全部行い、ISPあるいはIXCにトラヒックを伝送していく。地域電話会社(LEC)とのインターフェイスはタンデムスウィッチをバイパスしてエンドオフィスで行う。この結果、価格競争力を高めるだけでなく、信頼性を向上することを実現している。
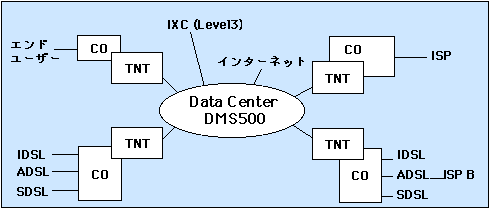
| 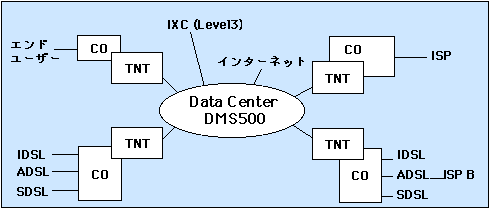
 トップページ
トップページ