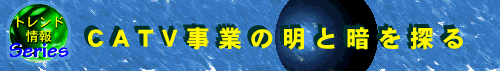| トレンド情報-シリーズ[1997年] |
|
(1997.11) CATV局の多くは、当初MSOなど大規模事業者への合併などにより業界再編成の大きな波に巻き込まれると見られていた。一部の経営の破綻した局では、経営権の譲渡や投資を受けて系列化されたが、大幅な業界再編はおきなかった。多くのCATV局が第三セクターであったことと大資本が大都市やその周辺地域のCATV空白地域でのCATV局の新設に力を注いだことが大きな要因である。しかし、CATV網の広域化や通信利用を考えると業界再編は、避けてとおることのできない課題といっても良い。
|
| 1)CATV業界の課題 CATV業界の課題としては、
|
| 2)CATV局のパターンと業界再編のターゲット 現状のCATV局の動向を大別すると、次の4つのパターンに分類できる。
|
| 3)系列化の動き CATV法の改正や大資本や異業種の参入、系列化などの動きやデジタル化、多チャンネル化さらには情報通信への新たな事業への展開など大きな転換期になっている。 系列化の動きとしては、次の4つの動きが活発である。
|
| 4)CATV局の広域化とCATV局相互の連携 大資本や通信事業者を背景とした系列化のほか、CATV事業者による広域化や連携が進んでいる。 1都市1事業者の規制緩和により、既存CATV事業者の隣接市町村へのエリア拡大が容易に可能となってきた。このことにより、CATV局の大規模エリア化に拍車がかかり、従来経営的に困難と思われてきた隣接市町村地域へもCATV事業が広がってきている。 通信事業への展開を模索する局の中には、CATV局同士が連携をとりCATV網の広域化を目指している局が出てきた。従来、CATV広告など連携を図った業務を行っていたが、CATV網の広域ネットワーク化やMSOの系列化の不安などからCATV局が協力して各種事業を進めるといったいわば日本的な取り組みが行われ始めている。更に、複数事業者のセンター共同利用などが規制緩和すれば更に広域化や連携の動きが活発化するものと考えられる。 |
| 5)インターネットや電話事業など新たな事業展開が、より通信業界に密着 経営状況の良いCATV会社やエリア内の普及率が高い局にとっては、エリア拡大のほか、通信事業などへの事業展開が大きな経営戦略となっている。 双方向サービスの事業化を展望すると、広域エリアと多くの普及数が必要となると同時に、通信技術やコンピュータ技術のノウハウが必要となってくる。 このため最新の技術や機器の導入さらには通信ネットワークとの接続など、機器メーカーや通信事業者との連携がより密接になってきた。 アメリカでは、全米1位と2位CATV会社TCIとTWの業務連携やインターラクティブ放送ためのマイクロソフト社の資金支援、地域統合サービスとして電力会社の通信から放送まで一体的に行うエリア網の事業化、さらには無線CATVによる双方向多チャンネルCATV(MMDS)への本格的サービスへの参入など大きな変化が起きようとしている。 更に、日本においては通信事業への外国資本の規制緩和が行われたため、地域通信事業にも積極的に海外キャリアが参入することが予想できる。また、日本の通信事業者も、加入者抱え込みやトラヒックの抱え込みのためCATV網と接続し、エンドツーエンドの通信のトータルサービスを目指している。 |
| 6)通信業界の再編成が、鍵 従来の業界再編は、CATV事業経営の効率化や大規模化がキーワードと考えられてきた。特に、米国に象徴されるM&A(企業買収)が思い起こされる。しかし、第三セクターが多くかつM&Aに対し嫌悪感のある日本ではうまく機能しなかった。 しかし、CATV電話サービスやインターネット接続サービスなどCATV網を通信サービス利用ないしはアクセス網として活用する動きが出てきた。CATV事業は、通信と放送の融合の最前線にいる業界と見て良い。 一方、通信業界は、大きな業界再編成の中に突入したところである。このため、CATV業界の再編成は、従来型の大規模化による系列化でなく、通信事業の再編成の動きに連動したものになると見て良い。 現在でも、日本テレコム、電力系NCC、KDDなどがCATV事業への積極的に参加している。さらに、NTTの分離分割後の長距離会社のCATV事業への参入が可能となっている。 CATV網は、NTT網以外では最大の市内アクセス網のため、通信事業者の戦略によっては、業界再編が加速することも考えられる。CATVの通信サービスの事業化やエリア拡大が進むほど、通信業界の再編の大波が、CATV事業にも大きな影響を与えることは間違いない。すでに、インターネット接続サービスにも通信事業者の影がちらついている。 通信と放送の融合は、単にサービスの融合のみならず、通信業界とCATV業界の統合や系列化など業界再編成の大きな鍵を握っている。 |
|
(システム応用研究部 遠山 廣) e-mail:tohyama@icr.co.jp (入稿:1997.10) |
| このページの最初へ |
 トップページ トップページ(http://www.icr.co.jp/newsletter/) |