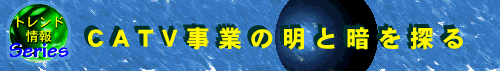8月11日、東京通信ネットワークが、自社のネットワークとNTTの市内交換機接続により中継電話サービスの認可申請をした。従来、専用線サービスと直接加入者線を敷設して電話サービスを提供していた。この電話サービスの主なユーザーとしては、電力会社関係の企業が主なユーザであったため、サービスも限定されていた。今回は、市内交換機より上位の中継区間でのいわば中・長距離通信事業といえる。営業エリアは、関東一円、山梨県、静岡県の一部であるが、いずれの事業者よりも割安の料金設定であり、事業の採算性を無視した料金との声が聞こえるほどである。
他の長距離事業者にとっても、衝撃的な価格であり、LCR付電話の対応に苦慮することとなる。
このため、東京電話のサービス開始までに、各通信事業者の追随値下げがおきることは、必死である。
東京電話との競争を考えると、CATV電話は、非常に狭い加入エリアでありかつ現状の料金設定では、十分対抗できるとは思われない。CATV電話サービスは、事業化したとたんに通信事業の本格競争の大波をかぶることとなった。
今までの電話サービスは、管理された競争であったが、今回の東京電話のサービスは、新の自由競争を呼び起こすこととなった。まさに、CATV電話サービスの出鼻をくじく一撃になることが想定される。CATV電話と比較して市内アクセス網構築が必要ないため、非常に低コストの電話サービスとなっている。
今後、東京電話に対してCATV電話が取りうる戦略として、
- CATV電話事業からの撤退
- 料金の追随値下げ
- TTNetと同様の形態で電話サービス事業に参入
- 他の通信事業者と連携して対抗
- TTNetのアクセス網としてCATV電話サービスを行う。
などが考えられる。,p>
当然、2.を行うこととなるが、この場合、通信事業者の価格競争に巻き込まれることとなり、事業拡大の展望が描けなくなる恐れがある。 したがって、CATV事業の特徴を生かし、有線TV放送、インターネット接続、電話サービス、情報提供といったトータル情報通信サービスで対抗していくことがもっとも有効な手段である。
放送視聴はいくら、電話はいくらと言った個別サービスでの競争でなく、統合サービスとして事業採算性を考えていくこととなる。いってみれば、放送と通信のCATV版ワンストップショッピングが必要である。
1.のケースは、最悪のシナリオであり、実質的もこのケースは避けなければ、CATVの将来とってに大きな汚点を残すこととなる。つまり、CATV網の放送以外の事業は、競争に勝てないことを示すこととなり、元の有線TV放送に戻ってしまうことになりかねない。
3.、4.、5.のケースの場合は、通信事業に本格的に参入することとが前提であり、CATV電話は、通信サービスのメニューの一つでしかなくなる。この場合には、連携する通信事業者によって自ずとパターンは決まってくる。
したがって、タイタスやジュピターのここ1年間のCATV電話への取り組みに注目したい。
 トップページ
トップページ