| トレンド情報-シリーズ[1999年] |
|
| (1999.10) |
|
いよいよ経営とITのシリーズも第4回となりました。 今回の本題に入る前に、「ビジネス・モデル特許研究会」の問い合わせ、反響にお礼を申し上げます。特に、海外での「ビジネス・モデル特許」の現地情報をいただいたり、多数の国内情報を提供していただいた方々にあらためて厚くお礼を申し上げます。 「ビジネス・モデル特許研究会」の参加問い合わせはこの2週間ほどで60件を超え、大手企業の参加問い合わせの多いことにとても驚きました。ビジネス・モデル特許についてはこれまでの装置特許、製法特許、媒体特許と異なり、情報の検索や収集を専門にする必要があります。膨大な特許情報の中から関連するビジネス・モデル特許と思われるものを検索、収集して、データベース化することも容易ではありません。
また、ビジネス・モデルとは何か、モデリング手法とはどんなものか。ビジネス・モデル特許の成立要件など基本的な整理・研究もしなければなりません。今回のビジネス・モデル特許研究会では、基本的な情報の収集からビジネス・モデルに関係する多くの事柄についても調査し、ご報告いたします。経営とITの問題にビジネス・モデル特許がどうこれから関係してくるのか。単なる情報サービスにとどまらない研究報告を心がけたいと思います。
すでに、ロンドンとニューヨークで海外調査の準備に入りました。 ◇◆◇
さて、今回の本題はマイケル・ポーターです。 ポーターの原点である「競争の戦略」と「競争優位の戦略」は業界構造を5つ(新規参入企業、買い手、供給企業、代替品、競争企業)の競争要因で分析する「ファイブ・フォース・モデル」。企業の基本戦略を3つ(コスト・リーダーシップ戦略、差別化戦略、集中戦略)に分類した「基本戦略モデル」。企業の価値創造過程を分析した「価値連鎖(バリューチェーン)モデル」。企業戦略の環境適応性を強調した「戦略シナリオモデル」。これらのモデルの解説をくどいくらいポーター流の表現で論じています。ただ、ポーターも長い間に考えも変り、自分の提唱する戦略理論にも変化があります。3つの基本戦略について言えば、「競争の戦略」(1980)p61と「競争優位の戦略」(1985)p16と「国の競争優位」(1990)p58ではその内容が微妙に違っています(図1)。もともと3つの基本戦略の分類に無理があったのか知れませんが、「戦略の本質」(1997)では3つの戦略に代わって、ポジショニングが導入されています。経営戦略論のポーターであっても時代とともに、自分の戦略論の修正はありえるのです。 ポーターとITの重要な接点はバリューチェーンです。この10年以上も前のコンセプトはTOC理論やスループット会計ともにサプライチェーンの重要な概念になり、ITの分野でもビジネス・プロセスに注目する手がかりにもなりました。価値連鎖のコンセプトはアウトソーシングやコア・コンピタンス、BPRについても重要なコンセプトでありえたし、今後も企業の価値創造過程の分析におけるポーターのコンセプト影響は大きいでしょう。ただ、ポーターはバリューチェーン(価値連鎖)のコンセプトを明確にITと関連において論じてはいません。重要性は認識していましたが、経営戦略とITとの関連や構造、変化のメカニズムについては、明確ではありません。今後IT業界にいる者として経営とITの問題は重要なテーマとして追求するつもりです。
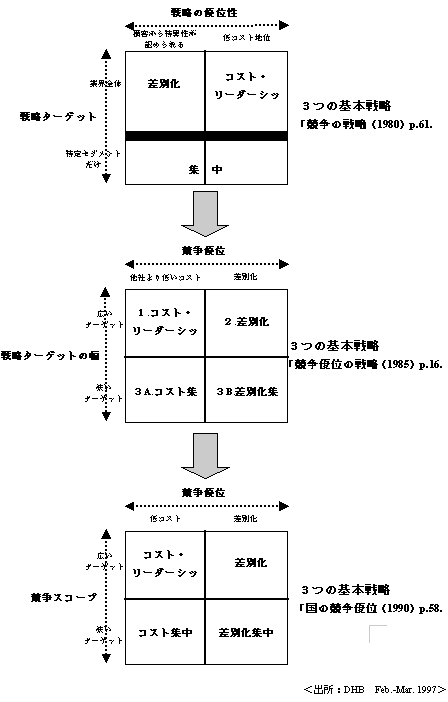 ポーター以降の経営学の歴史は「エクセレント・カンパニー」、「リエンジニアリング革命」、「バーチャル・コーポレーション」、「コア・コンピタンス経営」、「知識創造企業」などの著作によってさらに複雑になりました。1990年代はラーニング・オーガニゼイション(センゲ)、コア・コンピタンス(ハメル&プラハラード)、リエンジニアリング(ハマー&チャンピー)3大経営論がポーターやドラッカーを巻き込んだ時代です。これら経営学の分野にソフトウェア工学、経営工学の歴史を加えたものが、現代の経営におけるITと経営の問題です。経営における問題とITの問題、そして経営とITの関連の解明と融合はまだまだ多くの研究が必要です。ビジネス現場で日々仕事に追われるだけでなく、個人的なライフワークとして学びの時間が必要です。
<経営学年表> 1982年 「競争の戦略」(ポーター) 経営戦略論の原典 1983年 「エクセレント・カンパニー」(ピーターズ&ウォーターマン) エクセレント・カンパニーの原典 1985年 「競争優位の戦略」(ポーター) 1989年 「グローバル企業の競争戦略」(ポーター) 1990年 「国の競争優位」(ポーター) 1990年 「知識創造の経営」(野中) 1991年 「非営利組織の経営」(ドラッカー) 1991年 「ブレイクスルー思考」(ナドラー) ラーニング・オーガニゼイションの原典 1992年 「未来企業」(ドラッカー) 1993年 「ポスト資本主義社会」(ドラッカー) 1993年 「リエンジニアリング革命」(ハマー&チャンピー) BPRの原典 1993年 「バーチャル・コーポレーション」(ダビドゥ&マローン) 仮想企業論の原典 1994年 「フィナンシャル・マネジメント」(ヒンギス) 企業財務論の原典、3レバー・コントロール 1995年 「コア・コンピタンス経営」(ハメル&プラハラード) コア・コンピタンスの原典 1995年 「競争の戦略」(新訂版)(ポーター) 1995年 「最強組織の法則」(センゲ) ラーニング・オーガニゼイション理論 1996年 「乱気流時代の経営」(ドラッカー) 1996年 「戦略とは何か」(ポーター)ハーバード・ビジネス・レヴュー コア・コンピタンス経営やリエンジニアリング革命などで混乱する経営戦略論に 発表された論文は次の5項目を主張しました。 1. 日本的経営の限界 2. 競争優位の再認識 3. 選択こそ永続する競争優位の根源 4. 企業活動の一貫性が永続する競争優位を強化する 5. 戦略は10年スパンで考える 1996年 「知識創造企業」(野中&竹内) ナレッジ・マネジメント 1996年 「マーケティング・マネジメント」(コトラー) マーケティング学の原典 1997年 「戦略の本質」(ポーター)ハーバード・ビジネス・レヴュー ポジショニングの導入 1999年 「未来を支配するもの」(ドラッカー) 1999年 「グローバル戦略の本質」(ポーター)ハーバード・ビジネス・レヴュー クラスター理論の展開 |
|
中嶋 隆 (入稿:1999.10) |
| このページの最初へ |
 トップページ トップページ(http://www.icr.co.jp/newsletter/) |
![[経営とIT]](../../../gif/title_sI2.gif)