| トレンド情報-シリーズ[1999年] |
|
| (1999.7) |
| この1年間にAT&Tが展開したM&A戦略に見るとおり、情報通信融合時代を迎えたメガキャリアーは持てる力を生かしてサーバーやコンテンツ/アプリケーションのホスト業に乗り出しつつある。インターネット革命が企業情報ネットワークにもたらす衝撃は極めて大きいが、厳しい環境下でも日本の通信企業は戦略的課題の解決に挑戦しなければならない。
|
●メガキャリアーの変身 垂直的展開 |
通信企業は電子商取引バリューチェーンを昇進できる
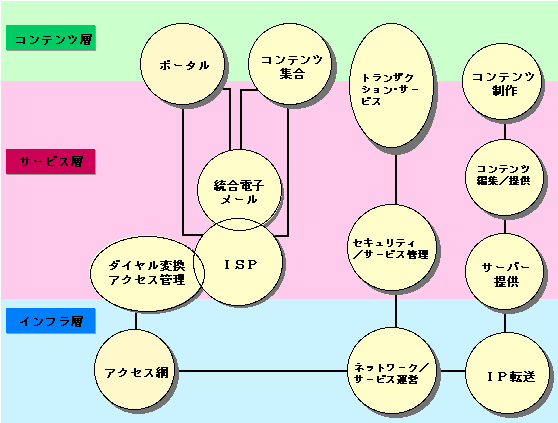
|
『今日インフラ層にある通信企業の伝統的能力はサービス層やコンテンツ層の戦略地点への踏み石である。通信企業は所有するアクセス網を傘下や競争相手ISPのゲイトウェーやアクセス回線に卸売りする。ネットワーク/サービス運営の専門技能はトランザクション・サービスや課金サービスをもたらす。広帯域インフラで通信企業はサーバー/コンテンツ/アプリケーションのホスト業ができる。』 この図に照らすと、AT&TのCATV企業買収・提携やエキサイト・アットホーム設立は電子商取引バリューチェーン革新の代表例であることが分かる。ただ、顧客へ直接リンクするアクセス網の所有が要であることは確かだが、アクセス網と言っても光ファイバ、光/同軸複合、xDSL、移動網など様々ある。また、バリューチェーンのどこまで行くのがベストかはまだ決まっておらず、米欧通信企業の取組みはさまざまであるが、従来自前主義が伝統だった通信企業も自分で全てやること不可能とさとり、共通して提携戦略に注力している。 コミュニケーションズ・インターナショナル誌99年6月号の「電話会社を電子商取引に適応させる方法」は、『電話会社がEビジネスの競争をリードする可能性はほとんどない。電話会社のビジネス・モデルはインフラ、交換機その他に大規模投資を行い、8~10年償却で運営するものだが、電子商取引はイノベーション・ビジネスであり、チャンスは3ヵ月かそこらしか存在しない、運が良くて半年窓が開いてる類いのもの。チャンスが去ればまた一からやり直しと言うビジネスである。万事スローモーの電話会社には向かない』とする。 前回のシリーズ No.22で主要キャリアーの合従連衡は煮詰まってきたと報じたが、それは水平的統合についてであって、今回述べている垂直的展開はこれからである。水平的統合にしても、USウェストとグローバルクロッシングの合併に対して6月13日にクエスト・コミュニケーションズ(Qwest)がフロンティアを含む買収の意思 表示を行い、6月22日に金額を543億ドルに引き上げ、フロンティアになびく気配が出て、しかしUSウェストはなおリジェクトベースと、さぐり合いが続いている。日本のIDCをめぐるNTとC&Wの応酬はC&Wの勝利に終わったが、日本の通信企業の水平的統合はむしろこれからの雰囲気である。キャリアーの合従連衡に当分終わりはない。 |
●インターネット革命が導く未来 |
●日本の通信企業がなすべきこと |
|
(関西大学総合情報学部教授 高橋洋文) (入稿:1999.7) |
| このページの最初へ |
 トップページ トップページ(http://www.icr.co.jp/newsletter/) |
![[メガコンペティションは今?]](../../../gif/title_sM.gif)