| ホーム > ICTエコノミーの今 2012 > |
| 2012年7月19日掲載 |
経済全体の動向をみると2012年に入ってから好調が続いているが、ICT経済に注目すると経済全体に遅れる形で持ち直して来ている。持ち直しをけん引しているのはICT関連サービス業である(詳細はInfoCom ICT経済報告NO.33参照)が、その増加の主役を担っているのは携帯電話サービスを提供する移動電気通信業である。しかし、今回とりあげるのは主役である移動電気通信業ではない。以下では移動電気通信業に比べると影響力は小さいものの着実にICTサービスを押し上げてICT経済持ち直しに貢献している影の主役を紹介したい。 まず、以下のグラフをみて頂きたい。 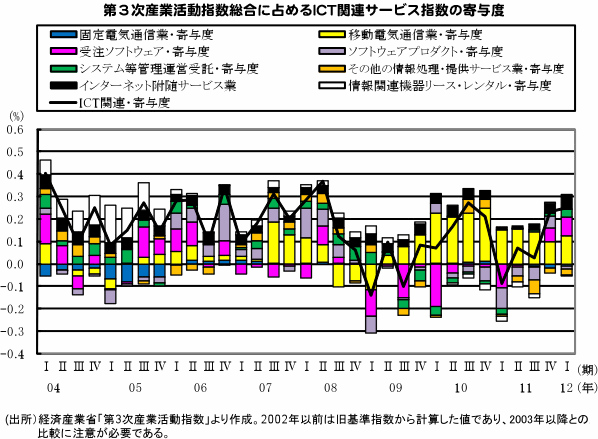 グラフの折れ線はICTサービスが日本国内のサービス全体を前年よりも何%増減させたのかという寄与度を示している。折れ線グラフの数値が大きいほどICTサービスが経済全体に与える影響が大きいといえる。積み上げ棒グラフは寄与度の内訳を示しており、棒グラフの面積が大きいサービスほど影響力が大きいことを示している。 2011年4-6月(グラフでは11Ⅱと表記)以降の動向をみてみよう。ICTサービスの寄与度を示す折れ線は増加を続けているが、その内訳の棒グラフをみると冒頭で主役と述べた移動電気通信業のプラス幅が大きいことが確認できる。ここで注目して頂きたいのがインターネット付随サービス業である。プラス幅は大きくないものの、データが取れるようになった2004年以降一貫して増加を続けている。そして、2011年10-12月~2012年1-3月(グラフでは11Ⅳ~12Ⅰ)はプラス幅が拡大し、ICTサービス増加を通じてICT経済持ち直しの影の主役となったのである。 ここまで読んで頂いた読者の中にはインターネット付随サービス業というワードに違和感をもった方が多いのではないだろうか。インターネット付随サービスと聞いてピンと来るのは私のような統計に関する業務を生業としているものくらいであろう。インターネットに付随するサービスというと、「パソコンの設定とかインターネットへの接続方法を教えてくれるサポートサービスかな?」と思ってしまうかもしれない。そこで、以下ではインターネット付随サービスに含まれるサービス業務の例を紹介していこう。 まず、身近な例ではEコマースやネットオークション等のサイト運営業務が含まれる。最近のインターネット付随サービス増加の背景には、例えば東日本大震災の後Eコマースの利便性が改めて評価されたことや、ソーシャルゲームサイトの利用が増えたことがあると考えられる。最近利用が増えたVODや、その他に着うたや壁紙等を配信するコンテンツ配信業務も含まれる。さらに、Eコマースやコンテンツ購入に関わる課金・決済業務もインターネット付随サービスの一部である。 総務省と経済産業省が行っている『情報通信業基本調査』のアクティビティーベース(企業の営む活動内容に着目したまとめ方)の結果をみると、2010年度の売上高は1.7兆円である。携帯電話サービスやインターネット通信サービスから成る電気通信業の売上高が16兆円なので、その10分の1程度の規模であり、まだまだ小さい。 日本は光ファイバーや3G携帯電話等インフラは整っているのに、韓国やアメリカと比べて利活用が進んでいないという意見を良く耳にするが、このこととインターネット付随サービス業の規模の小ささは無関係では無いだろう。サイト運営業、コンテンツ配信業、サーバハウジング・ホスティング業等が成長し、付随ではなく独立した産業として統計に表れるようになったとき、日本のICT利活用の姿は今とまったく違ったものなっているかもしれない。そのような未来を期待したい。 |
| ▲このページのトップへ
|
| InfoComニューズレター |
| Copyright© 情報通信総合研究所. 当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。 InfoComニューズレターを書籍・雑誌等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。 |
