新たなCSR戦略モデルを創造するグリーンICT
![[tweet]](../../gif/icon_tweet.gif)
|
 |
9月にNY国連本部で開催された国連気候変動サミットにおいて、鳩山首相が表明した国際公約「温室効果ガスを西暦2020年までに1990年より25%削減」を受け、国内企業は、環境経営を重点題目とする動きを見せている。民主党政権下では、縮小する国内市場に固執し、内需主導へと政策転換がなされようとしている。企業は海外市場への積極展開をめざすべく、BRICsを含めた新興国への直接投資を含めた市場開拓を加速させている。企業をとりまく環境が激変する中、海外市場での企業の社会的責任(CSR:Corporate Social Responsibility)は重要な経営要素となってきている。従来のCSRの考え方では、企業は自社の主力事業の補完、企業ブランドの構成要素の一つ、あるいは社会貢献事業と見なし、企業各社はCSR報告書を刊行してきたと言える。しかしながら、近年、主な原因となる温室効果ガスの増加により、地球規模での気候変動問題や、温室効果ガス削減問題が企業経営に多大なる影響をもたらしている。企業はその経営戦略にCSR戦略も取り入れ、企業をとりまく環境を常に意識することで、経営することが求められ、その結果として、企業が環境問題に取り組む手段の一つとして、ICTの利活用が挙げられている。とりわけ、企業が温室効果ガス削減を実現していく中で、環境に配慮したICT「グリーンICT」をどのように活用していくかが問われている。
グリーンICTは環境問題を考慮したICT基盤(製品/機器やネットワークインフラ等)の構築をめざす考え方をいい、さらに、地球環境保護や資源の有効活用につながるICTの利用も含まれる。グリーンICTを産業と市場経済で分類すると次のようになる。
環境問題を考慮したICT産業
<通信事業者/ICT関連企業>
- ネットワーク機器を中心としたグリーン製品の設計・開発
- データセンター運用改善(物理環境改善およびクラウドサービスの導入)
- バーチャルプレゼンス(マイクロソフト社「spatial computing」の3D仮想世界等)
<環境エネルギー産業とICT産業の融合>
- マートグリッド/マイクログリッド
- HEMS*1/BEMS*2
住宅やビルの省エネ、各種エネルギーを家電情報ネットワークと配電網を利用することでの最適化管理
*1 Home Energy Management System
*2 Building and Energy Management System
<市場経済>
- 脱物質化(ディ・マテリアライゼーション)
- 物質の代替化(トランス・マテリアラーゼーション)
- 脱炭素化(ディ・カーボナイゼーション)
グリーンICTは、今後、企業のCSRを実践していく中で、重要な役割を担うとともに、図1に示すように、新たな事業創造や企業価値創造にも貢献することが期待できる。
図1.企業経営の新たなCSR戦略モデル
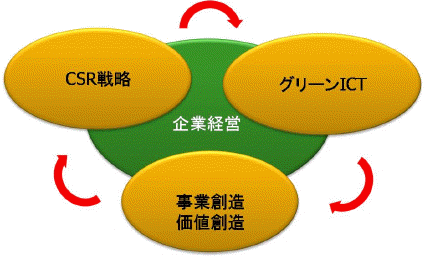
|