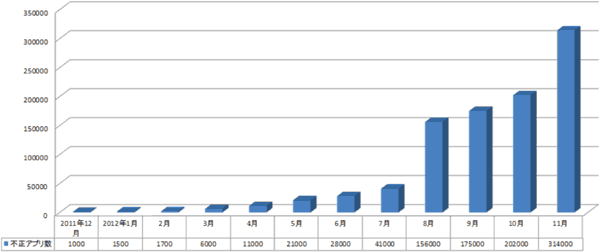| ホーム > Global Perspective 2012 > |
| 2012年12月28日掲載 |
2012年も多くのサイバー攻撃に関して、なりすましや遠隔操作、標的型攻撃など国内外で多数の事例やニュースが目立った。本稿執筆時もGmailアカウントの乗っ取りによる不正アクセスが話題になっている。 急増するモバイル不正アプリと巧妙化する手口2012年12月21日、セキュリティ会社トレンドマイクロは、2012年のインターネット脅威レポートの速報版を発表した(※1)。サイバー犯罪の高度化や日本に特化した犯罪などが挙げられたが、特筆すべきはモバイルを標的にした不正アプリ(マルウェア)が急増したことだ。 その背景には、AndroidOSを搭載したスマートフォンの普及に伴って、マルウェアも多数登場してきたことにある。Androidの不正アプリは、2010年8月に初めて確認された。2011年11月には約1,000個だったが、2012年11月には300倍の31万4,000個まで増加した。 【主な不正アプリの事例】(トレンドマイクロ社の公開情報を元に作成)
(表1)Android端末に感染する不正アプリ数 (出典:トレンドマイクロ社) 求められる危機管理最近ではスマートフォンやタブレットの普及に伴いBYODというワークスタイルが注目されている。これは「Bring Your Own Device」の略で、社員が個人の私物の端末を企業内に持ち込んで業務に活用することである。BYODで利用している端末に不正アプリが見知らぬうちにダウンロードされてしまい、情報漏洩など業務に差し支えがあるような問題にならないよう、万全の注意が必要である。現在では、BYOD向けソリューションでも一番注力しているのがセキュリティ関連である。また個人向けの様々なセキュリティソフトも登場している。 何よりも重要なのは、利用者一人一人の意識と対策である。怪しいサイトからのダウンロードをしない、といった細心の注意が必要になってくる。そしてもし騙されてダウンロードしてしまい被害にあった場合の対応策を平時から検討する必要がある。 スマートフォンは小さなパソコンである。会社のパソコンならシステム管理者が保守管理してくれるだろう。しかし個人のスマートフォンは各人が責任をもって自分の身は自分で守らなくてはならない。様々なセキュリティ対策が講じられているが、今後もますますスマートフォン向けの不正アプリは増加していくことが想定される。 そして、危機管理力はモバイル向け不正アプリだけではなく、あらゆるサイバー攻撃にあてはまる。再度、サイバーセキュリティに対して、
の危機管理体制が万全か確認しておくことを推奨する。 ※1 トレンドマイクロ社「インターネット脅威年間レポート -2012年度(速報)」 *本情報は2012年12月27日時点のものである。 |
| ▲このページのトップへ
|
| InfoComニューズレター |
| Copyright© 情報通信総合研究所. 当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。 InfoComニューズレターを書籍・雑誌等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。 |