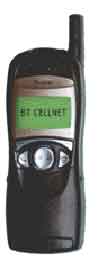T−モビルによると、WAPサービスを積極的に利用しているのは同社の約1,300万ユーザー(2000年6月末現在)のうちの1.4%にあたる17.5万ユーザーとのこと。すでに販売されたWAP対応携帯電話機は約25万台、WAPサービスの利用セッションは1日当たり3.5万回としている。これは、単純計算すればWAPを使うユーザーが平均5日に1回操作していることになる。T−モビルがWAPサービスを開始したのは1999年12月であり、導入から半年以上経った時点でこの状況である。
ミニテルは世界で唯一成功したビデオテックス・サービスとして有名であるが、そのコンテントは多岐にわたっており、普及台数も1998年末で約590万台。ミニテルでテキストベースの情報サービス、チケット予約などに慣れているフランスの人々にとってはWAPコンテントは貧弱に映り、また「わざわざ携帯電話から操作しなくても、家に帰れば扱い慣れたミニテル端末があるから」普及しないのだという指摘である。現在の「iモード」のコンテンツとミニテルのコンテンツは共通する部分も多いが、それは人々の生活に密着した便利なサービスであるという点でサービスの位置付けが似ていることを考えれば至極当然といえる。ミニテルが存在するフランスにおけるWAPサービスと、ミニテルに相当する「キャプテン(CAPTAIN)」が普及しなかった日本とでは、ユーザーが感じる新鮮さに差があっても不思議ではない。
- (1)相互動作性(Interoperability)
- 国をまたがっても同様に使えるサービスとして普及してきたGSMの世界においては、WAPサービスはGSMの付加サービスとしての位置付け、という概念が基礎にある。日本でいうところのユニバーサルなサービスという意識の代わりに、欧州GSM陣営にとってはグローバルなサービスという意識が根底にある。その最たるものが国際ローミングであり、ユーザーは国境を問わず同じ携帯電話端末でほぼ同様のサービスを利用できる。
現在欧州においてはキャリアが提供するサービス間の細かな仕様の違いや、サーバーおよび端末における相性の違いがWAPサービスの相互動作性における問題とされている。現地では「フレーバー(flavour)が違う」と表現されることが多いようである。たとえば、テレコム・イタリア・モバイルの提供するWAPサービスでは、モトローラ製WAP対応携帯電話ではきれいに表示されるが、ノキア製端末では一部のコンテントが上手に表示されないことがあるとの報道もある。
もとよりどこの国でもWAPサービスが同様に利用できるよう開発を進めていたがために標準化が遅れたといえるが、端末によってWAPサービスがうまく利用できない、作動しないという評判が、ユーザーのWAPサービスへの加入意欲を削ぐという影響は少なからずあるのかもしれない。
日本においてこの種の相互動作性はあまり大きな問題としては取り上げられなかったが、実際は開発現場においてこれに類する事象は発生していた可能性はある。しかし仮に発生していたとしても、世界でも類を見ない、日本独特の通信事業者と機器ベンダーの協調性の深さおよびコンテント・プロバイダーへのサポート体制が、この障害を乗り越えるに寄与していたであろうことは想像に難くない。
(補足)通信事業者と機器ベンダーの関係について 日本においては、携帯電話ベンダーと通信事業者が協調して移動機を開発し、通信事業者が端末流通を行うというのが慣例になっているが、一方欧州では、通信事業者はSIMの流通を、移動機ベンダーは移動機の開発および流通をコントロールするというのが基本的な流れである。これはGSMがSIM(Subscriber Identity Module)と移動機を組み合わせて初めて通信ができる仕組みになっていること、本来的にはひとつのSIMを異なる移動機に差し替えて使用できるということが背景にある。そのため欧州では、日本ほどの通信事業者と機器ベンダーの協調関係は見られない。
- (2) データ伝送速度
- データ伝送速度を挙げる向きが回答者全体の約5人に1人もいたことは、少々驚きである。なぜなら、欧州では「iモード」がWAPサービスの最初の成功事例と理解されており、「iモード」に利用されているパケット通信サービス(9.6kbps)は、ほとんどのGSM事業者が提供するデータ通信速度と同等であるからである。
「iモード」の一部サービスにおいてはデータ量の軽い画像を使ったコンテントが普及しつつあるが、あくまでも中心はテキストベースのコンテントであり、WAPサービスの当初のコンセプトと何ら違いはない。WAPサービスが動画配信などを最初から念頭においてサービス開発や仕様の標準化を進めてきたというのであればともかく、「iモード」サービス導入初期と同じ「画面表示能力の限界」「情報入力操作の限界」を前提にしており、ここにWAPサービス普及の障害を認めることは、日本において9.6kbpsで「iモード」が成功したことを考えると理解に苦しむ。
しかし、この回答を「回線交換データ通信をベースにしているためにWAPサービス普及が阻害されており、パケット交換であれば普及が促進されるはず」という意味に解釈するならば、あながち的外れではなかろう。「iモード」が「EZウェブ」「J−スカイ」に対してシェアで圧倒している現状は、パケット通信でのサービスを当初から導入できたことにより通信料に対するユーザーの不安を除去したことが一因であることは、多くの業界関係者より指摘されているところである。すでに英国、ドイツにおいてはGSMにおけるパケット通信サービス「GPRS(General Packet Radio Service)」が導入されており、またGPRSは欧州各国において第3世代携帯電話サービスへのつなぎとしての位置付けであることからも、今後この動きは加速するであろう。
- (3) 端末機能の限界
- 端末機能の限界についてはサービス開発当初からの前提であり、これが普及を阻害しているとするならば、そもそもWAPサービスを何のために開発したのか全く理解できない。日本では端末ディスプレイのカラー化が進んでいるが、モノクロ画面の端末しかない時代にすでに爆発的にヒットしたことから、この指摘はあまり的を得ていないのではないか。
図2:WAP対応移動機
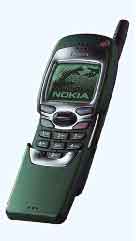 | 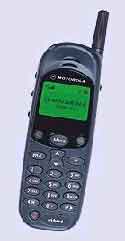 |
|---|
| ノキア「7110」 | モトローラ「タイムポート P7389」 |
- (4) コンテントの不足
- WAPサービスを開始している各通信事業者は、2000年内に100以上のコンテンツ提供を計画しているところも数多く、メニュー数の面では時間が解決するものと思われる。しかし、WAPサービスに関わるベンチャー企業を取り巻く環境が厳しくなっていること(後述)は、コンテント充実への足を引っ張りかねない。もっともNTTドコモが「iモード」開始にあたり、最初からかなりの数のメニューを揃えていたことが成功の一因となったことは事実であろう。NTTドコモはサービス導入当初ですでに十分なコンテンツをメニューに揃えておくことを重要視していた点で、海外の通信事業者の取り組み方とは一線を画す。
(補足)コンテント購入について NTTドコモは「iモード」でのコンテント提供にあたり通信事業者がコンテント・プロバイダーから購入するというスタンスをとっていない。これはNTTドコモが従来より提供している音声での情報提供サービス「ドコモ情報ダイヤル」(「#+4桁」で各種の情報を聞くことができるサービス)や、ポケットベルで提供されているテキストベースの情報配信サービス(A-ctiveチャネル、B-usinessチャネルなど)におけるような、コンテント・プロバイダーから情報を購入するビジネスモデルとは全く異なる。
- (5) WAP対応端末の不足
- 端末の不足に関しては、WAPサービスのスタートダッシュに大きな影響を与えたと私は考えている。欧州の多くの通信事業者は1999年第4四半期から2000年第1四半期にWAPサービスを開始しているが、最初に市場に出回った機種はノキア製「7110」1機種だけであった。この「7110」はWAP機能を十分に活用できるよう、操作性やディスプレイなどに工夫をこらした高機能機であり、1999年第1四半期に発表されて以来業界の注目を集めていた。ところがなかなか競合他社がWAP対応機を市場投入できなかったのである。現在でも端末流通の少なさを指摘する記事が数多く見られ、このボトルネックが解消されるには時間がかかるようである。
ARCグループの報告書ではWAPサービスの障害要因としてこれら5つが挙げられているが、他にも指摘すべき点がある。
- (6) 高価なWAP端末
- ノキア製「7110」は高機能を売りにしており、2000年2月のフランスでは量販店で5万円以上で販売されていた。これは消費者向け携帯電話機の多くが1万円程度で販売されていたことを考えれば手を出しづらい価格である。もっとも3月あたりからモトローラがライバル機種として廉価版のWAP対応機を投入、その後他ベンダーも続々WAP対応機を市場投入している。
たしかに発売当初から爆発的需要も見込めない状況の中、通信事業者が販売奨励金を積んで端末販売価格を抑えることもできないという事情はある。しかし、この価格設定の背景には「WAPは当初ビジネスユーザーから普及し、その後消費者層へ広がっていく」という欧州での市場の見方が存在していたことがある。これはARCグループの報告書にも見てとることができ、企業層と消費者層でどちらが収益に貢献すると考えるか、という問いに2000年末であれば企業層という答えが53%、2003年末では消費者層が70%、という回答である(図3参照) 。
図3:WAPサービスで収益を生むユーザー層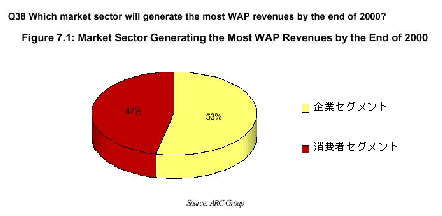
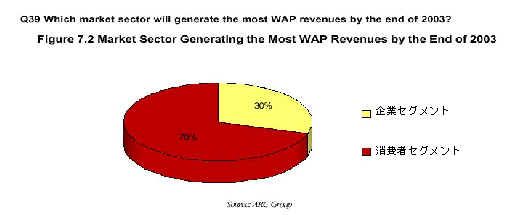 出典: ARC Group WAP 2000 Industry Survey
出典: ARC Group WAP 2000 Industry Survey
www.arcsurveys.com
- (7) ポストペイド・サービス用端末として販売
- ほとんどすべての通信事業者がWAPサービスおよび対応機をポストペイド専用で販売開始したということは、導入時において消費者層への普及を狙っていないこととほぼ同義であるといって差し支えないだろう。その西欧においては、プリペイドサービスの導入が契機となって携帯電話加入者が急増したのである。現在多くの通信事業者において新規加入者のほとんど、累計加入者の半数以上はプリペイドサービスを利用しているとの報道が数多くなされている。この制限が解消されない限りはWAPサービスを消費者ユーザーが利用するカルチャーは育たないのでは、と危惧されるところである。
その面から見ると、2000年4月にWAPサービス対応プリペイド携帯電話を発売した英国BTセルネットの戦略は注目に値する。三菱電機製「Trium GEO」1機種だけであるが「インターネット・ペイ・アンド・ゴー(Internet Pay and Go)」と名付け、99.99英ポンドで販売している(図4参照)。
図4:BTセルネットのプリペイWAPホン
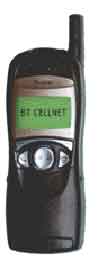
三菱「Trium GEO」
- (8) 第3世代携帯電話免許の存在
- さらに加えて指摘すべきは、WAPの将来を広げるであろう第3世代携帯電話(3G)の存在が、結果的に欧州の携帯電話事業者のWAPへの取り組みを鈍らせているというジレンマである。
今年に入ってから欧州各国では第3世代携帯電話免許の付与が始まっており、2000年末までにほとんどの国で付与が完了すると見られる。しかし多くの国はオークション形式での付与プロセスを採用する方向にあり、これが既存の携帯電話事業者にとって非常に大きな経済的負担となっている。すでに付与が完了した英国における3G免許料の高騰(5免許合計で約3兆7,000億円)が、他国の政府にとっては比較審査(ビューティー・コンテスト)方式による免許付与でなくオークションによる免許付与を選択するインセンティブとなってしまった。3G免許に数千億円を支払うことは、現在進行している通信事業者間の企業買収での金額より小規模であるが、企業買収は株式交換で行われることがほとんどであり、企業がキャッシュで支払う免許料とは同等に扱えない。
この結果、3Gサービス導入にあたっての経済的負担および通信事業者間の合併・買収によるグローバル化の流れから、通信事業者の経営陣の関心の中心はWAPサービスから3Gサービスへ奪われることとなってしまったとの指摘も現地報道に見られる。
- (9)ITバブルの崩壊
- また、昨今のITビジネス企業の株価急落等もあり、WAPサービスを支えるであろうと期待されていたWAPベンチャー企業の資金繰りが悪化しているとの指摘も一部メディアでなされている。日本においても携帯電話向けコンテンツを支えている企業には「MTI」「サイバード」といった新興企業が多いことを考えると、欧州のWAPベンチャーの事業活動を支援することがWAPサービスの発展に必要な時期に来ているのかもしれない。
このように見てくると、サービス導入への構造的な違い、携帯電話事業を取り巻く環境の違いなど日本と欧州では様々に異なっており、「iモード」のビジネスモデルを採り入れた国でWAPサービスが普及する、とは言いきれないことは明白である。「iモード」のサービス開始から約1年半。欧州の移動通信事業者が日本を手本にするのは結構なことであるが、日本は欧州の動きにあわてることなく独自にサービス開発を進めることで、この1年半の欧州とのアドバンテージをさらに広げることができる可能性は十分にある。
![[世界の移動・パーソナル通信T&S]](../../gif/title_sTS.gif)
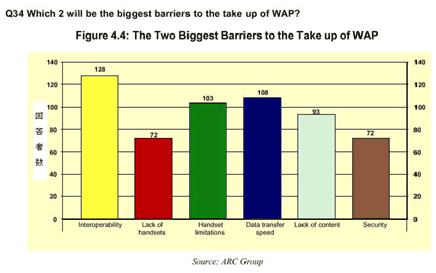
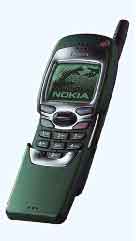
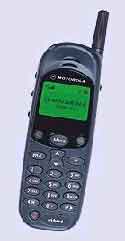
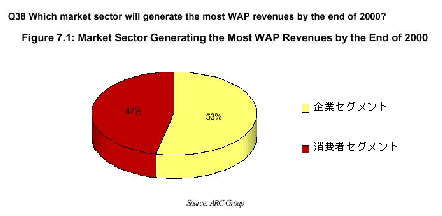
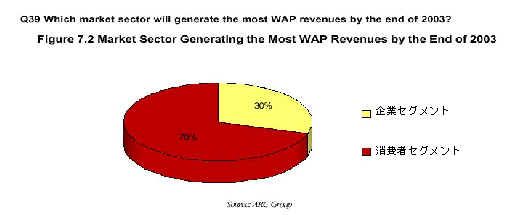 出典: ARC Group WAP 2000 Industry Survey
出典: ARC Group WAP 2000 Industry Survey