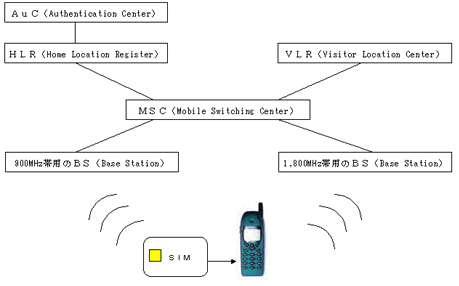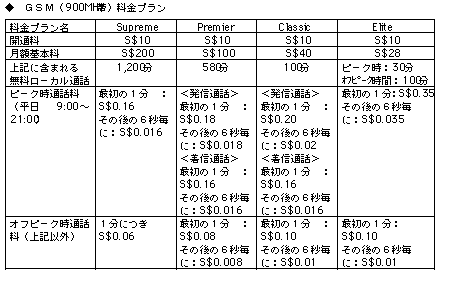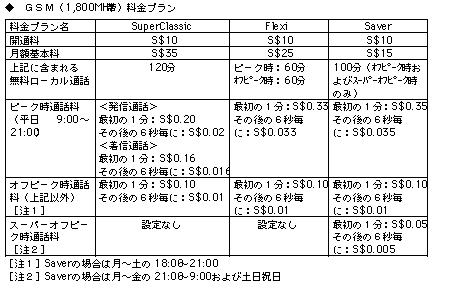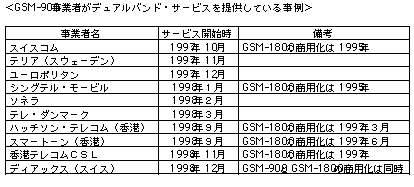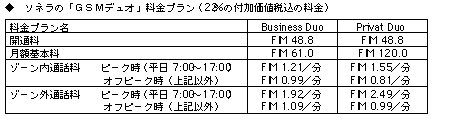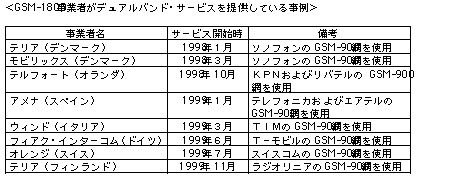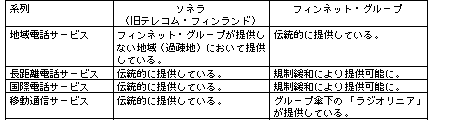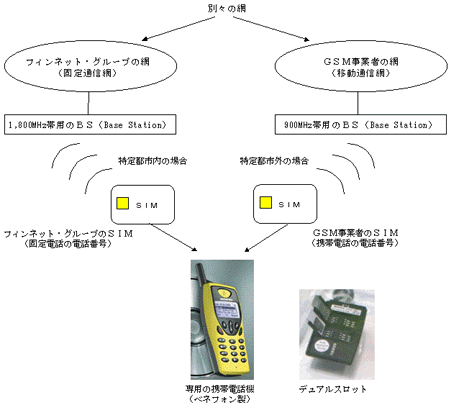僩僢僾儁乕僕
> 儗億乕僩
> 悽奅偺堏摦丒僷乕僜僫儖捠怣T&S
> 2000擭6寧崋乮捠姫135崋乯
>
![[悽奅偺堏摦丒僷乕僜僫儖捠怣T&S]](../../gif/title_sTS.gif)
僩儗儞僪儗億乕僩
|
|
丂擔杮偺堏摦捠怣帠嬈幰傪椺偵庢傞偲丄椺偊偽NTT僪僐儌偺応崌丄PDC偺800MHz懷丄PDC偺1.5GHz懷丄PHS乮1.9GHz乯懷偲3庬椶偺揹榖栐傪曐桳偟偰偍傝丄偙傟傜3偮偼暿乆偺僒乕價僗偲偟偰採嫙偝傟偰偄傞丅傕偭偲傕丄1戜偺揹榖婡偱PDC乮800MHz懷乯偲PHS偺椉曽偺婡擻傪旛偊偨乽僪僢僠乕儌乿偑1999擭4寧偐傜採嫙偝傟偰偄傞偑丄揹榖斣崋偼PDC偺傕偺偲PHS偺傕偺偑椉曽晅梌偝傟偰偍傝丄偟偐傕乽宊栺忋偼2夞慄偺宊栺乿偲側傞偙偲偐傜丄夞慄巊梡椏偲偟偰偼PDC亄PHS偺擇廳偺椏嬥偑偐偐傞巇慻傒偵側偭偰偄傞乮僼傽儈儕乕妱堷偑揔梡偝傟丄庒姳埨偔偼側傞偑乯丅傑偨丄僌儖乕僾偲偟偰PDC偺800MHz懷乮僙儖儔乕揹榖夛幮乯丄PDC偺1.5GHz懷乮僣乕僇乕乯丄PHS乮DDI億働僢僩揹榖乯偺3庬椶偺揹榖栐傪帩偮DDI僌儖乕僾偱傕丄奺僒乕價僗偼暿乆偵採嫙偝傟偰偄傞丅 丂堦曽丄奀奜偺GSM帠嬈幰偵栚傪揮偠偰傒傞偲丄僗僀僗僐儉丄僥儕傾丄僔儞僌僥儖丒儌乕價儖側偳丄1帠嬈幰偱暋悢偺懷堟偺揹榖栐乮GSM偺900MHz懷偲GSM偺1,800MHz懷乯傪曐桳偟偰偄傞帠椺偑尒庴偗傜傟傞丅偙偺拞偵偼丄擔杮偺傛偆偵偦傟偧傟偺懷堟偱偦傟偧傟暿屄偺僒乕價僗偑採嫙偝傟偰偄傞働乕僗傕偁傞偑丄傎偲傫偳偺応崌偼1戜偺実懷揹榖婡偱900MHz懷乛1,800MHz懷偺暋悢偺栐傪棙梡偱偒傞丄偄傢備傞僨儏傾儖僶儞僪丒僒乕價僗偲側偭偰偄傞丅NTT僪僐儌偺乽僪僢僠乕儌乿偲堎側傞偺偼丄揹榖斣崋偼偁偔傑偱1偮偱偁傝丄乽宊栺忋偼1夞慄偺宊栺乿偲側偭偰偄傞揰偱偁傞丅娙扨側栐峔惉恾偼埲壓偺捠傝偱丄岎姺嬊乮MSC亖Mobile Switching Center乯傗儂乕儉丒儊儌儕乕乮HLR亖Home Location Register乯丄奺SIM偵彂偒崬傑傟偨IMSI乮International Mobile Subscriber Identity丟揹榖斣崋偵1丗1偱懳墳乯偼丄偄偢傟傕1偮偲側偭偰偄傞丅
丂1,800MHz懷偺廃攇悢傪妱傝摉偰傪庴偗傞懳徾偲偟偰丄嫞憟偺懀恑偺偨傔偺怴婯嶲擖幰埲奜偵丄偄偔偮偐偺崙偱偼婛懚偺堏摦捠怣帠嬈幰傕岓曗偲側偭偨丅偙傟偼丄婛懚偺900MHz懷偱儐乕僓乕偑憹偊偰偔傞偲廃攇悢偑昇敆偡傞壜擻惈偑偁傞偙偲偐傜丄偦傟傪杊偖偨傔偵怴偟偄廃攇悢偲偟偰1,800MHz懷傪妱傝摉偰傞偙偲偲偟偨傕偺偱偁傞丅偙偺揰偵娭偟偰丄900MHz懷偲摨偠GSM曽幃傪1,800MHz懷偱傕嵦梡偟偨偙偲偼丄椉幰偺栐傪摑崌偡傞忋偱桳棙側嵽椏偲側偭偨丅 丂1,800MHz懷傪梡偄偨実懷揹榖僒乕價僗偼丄1993擭9寧偵塸崙偺儚儞2儚儞偵傛偭偰嵟弶偵彜梡壔偑峴傢傟丄偦偺屻丄塸崙偺僆儗儞僕乮1994擭4寧乯丄僪僀僣偺E亅僾儖僗乮1994擭5寧乯丄僼儔儞僗偺僽僀僌丒僥儗僐儉乮1996擭5寧乯偲採嫙奐巒偑憡師偄偩丅偙傟傜偺帠嬈幰偼丄偄偢傟傕偦偺崙偵偍偗傞怴婯嶲擖帠嬈幰偱偁傝丄採嫙偝傟偨僒乕價僗偼僔儞僌儖僶儞僪乮1,800MHz懷偟偐巊梡偱偒側偄乯偺実懷揹榖婡偵傛傞丄婛懚偺900MHz懷偲偼偁傑傝娭傢傝傪帩偨側偄僒乕價僗偱偁偭偨乮桞堦丄SIM偺嵎偟懼偊丄1,800MHz懷梡偺実懷揹榖婡偐傜900MHz懷梡偺実懷揹榖婡傊偺岎姺偵傛傞儘乕儈儞僌丄偄傢備傞乽僾儔僗僠僢僋丒儘乕儈儞僌乿偼壜擻乯丅偙傟偼丄摉帪偼傑偩丄900MHz懷乛1,800MHz懷偺椉曽偺懷堟偵懳墳偟偨僨儏傾儖僶儞僪実懷揹榖婡偑幚梡壔偝傟偰偄側偐偭偨偙偲偵傛傞丅
偡偱偵900MHz懷傪塣梡偟偰偄傞堏摦捠怣帠嬈幰偑怴偨偵1,800MHz懷偺彜梡壔傪峴偭偨偺偼丄1995擭10寧偺僗僀僗僐儉偑嵟弶偱偁傞丅偙偺帪揰偱偼僕儏僱乕僽偱偺尷掕揑採嫙偵偲偳傑傝丄900MHz懷偲偼暿屄偺僒乕價僗偲偟偰採嫙偝傟偨丅懕偄偰1995擭12寧偵僔儞僌僥儖丒儌乕價儖偑1,800MHz懷偺彜梡壔傪奐巒偟偨偑丄偙偺応崌傕900MHz懷偲偼慡偔暿屄偺僒乕價僗偲偟偰採嫙偝傟偨丅師暸偺僔儞僌僥儖偺椏嬥昞偱傢偐傞傛偆偵丄1,800MHz懷偺僒乕價僗偼僇僶儗僢僕偱900MHz懷傛傝楎傞斀柺丄900MHz懷傛傝埨壙側椏嬥愝掕偲側偭偰偄傞丅偙偺偁偨傝丄NTT僪僐儌偺PDC乮800MHz懷乯偲PDC乮1.5GHz懷乯偲偺娭學偵椶帡偟偰偄傞丅 丂実懷揹榖婡偺柺偱偼丄傛偆傗偔1997擭偵擖偭偰僨儏傾儖僶儞僪実懷揹榖婡偑彜梡壔偝傟偨丅嵟弶偺婡庬偼儌僩儘乕儔偺乽儅僀僋儘僞僢僋8800乿偱丄僆儗儞僕偲儚儞2儚儞偑摨擭4寧偐傜偙偺婡庬傪梡偄偨崙嵺儘乕儈儞僌丒僒乕價僗乮奀奜偺900MHz懷傊偺儘乕儈儞僌乯傪奐巒偟偰偄傞丅側偍丄偙偺儅僀僋儘僞僢僋8800偵偼懷堟傪傑偨偑傞応崌帺摦揑偵愗傝懼傢傞婡擻偑側偐偭偨偑乮儅僯儏傾儖偱愗傝懼偊傞昁梫偑偁偭偨乯丄摨擭6寧偵敪昞偝傟偨夵椙斉乽儅僀僋儘僞僢僋8900乿偵傛偭偰丄偙偺揰偼夵慞偝傟偨丅 亙僔儞僌僥儖丒儌乕價儖偺GSM椏嬥僾儔儞亜
仏Classic乮900MHz懷乯偲SuperClassic乮1,800MHz懷乯偲傪斾傋偨応崌丄捠榖椏偼摨偠偩偑丄寧妟婎杮椏偺埨偝丄柍椏捠榖暘悢偺懡偝偵偮偄偰偼SuperClassic偺曽偵孯攝偑忋偑傞丅傑偨丄Elite乮900MHz懷乯偲Saver乮1,800MHz懷乯偲傪斾傋偰傕丄摨條偺偙偲偑尵偊傞丅
丂廃攇悢偺昇敆懳嶔偲偟偰偼丄忋婰偺傛偆側僨儏傾儖僶儞僪偵傛傞埲奜偵傕丄擔杮偱幚巤偝傟偰偄傞傛偆側儅僀僋儘僙儖偵傛傞曽朄傕偁傞丅偙傟偵偮偄偰偼丄儅僀僋儘僙儖偺僇僶乕丒僄儕傾偼1僽儘僢僋掱搙側偺偵懳偟丄1,800MHz梡偺僙儖偼傛傝峀斖埻側僇僶儗僢僕傪採嫙偡傞偺偱丄僐僗僩揑偵僨儏傾儖僶儞僪偵傛傞曽偑桳棙偲偄偆堄尒偑弌偰偄傞丅
乮拲乯乽僝乕儞撪乿偲偼1,800MHz懷偺懷堟傪巊梡偡傞応崌偺椏嬥丅
丂嵟嬤敪惗偟偨暣憟偱戝偒偔栤戣偲側偭偨偺偼丄僼傿儞儔儞僪偺働乕僗偱偁傞丅1998擭3寧偵奐嬈偟偨僥儕傾丒僼傿儞儔儞僪乮1,800MHz懷帠嬈幰乯偼丄婛懚偺900MHz懷帠嬈幰偱偁傞僜僱儔偍傛傃儔僕僆儕僯傾偵儘乕儈儞僌傪怽偟擖傟偨偑丄椉幮偐傜嬌傔偰崅偄儘乕儈儞僌椏傪掓帵偝傟偨丅偦偺偨傔丄僥儕傾丒僼傿儞儔儞僪偱偼戙懼慬抲偲偟偰奀奜帠嬈幰偺僗僀僗僐儉偲採実傪寢傃丄僗僀僗僐儉亅僜僱儔娫偺儘乕儈儞僌嫤掕偵偺偭偲傝丄僜僱儔偺900MHz懷栐偵忔傝擖傟傞偙偲偲偟偨乮偮傑傝丄僜僱儔偐傜尒傟偽崙嵺儘乕儈儞僌偺宍偱僥儕傾丒僼傿儞儔儞僪偺実懷揹榖婡偑忔傝擖傟偰偔傞偙偲偵側傞乯丅偙傟偼丄僼傿儞儔儞僪偺実懷揹榖椏嬥偼悽奅揑偵傕埨偄悈弨偵偁傞偙偲偐傜丄儘乕儈儞僌帪偵壽偝傟傞儅乕僋傾僢僾乮忋忔偣乯傪峫椂偟偰傕丄偦傟傎偳崅偔側傜側偄偙偲偵栚傪晅偗偨乽曽曋乿偱偁傞丅 丂偙傟偵婥晅偄偨僜僱儔偑1999擭4寧偵僗僀僗僐儉偲偺儘乕儈儞僌傪懪偪愗偭偨偙偲偐傜丄憶偓偑戝偒偔側偭偨丅暣憟偼僼傿儞儔儞僪偺婯惂婡娭偵帩偪崬傑傟丄摨擭10寧偵僜僱儔丄儔僕僆儕僯傾椉幮偺峴偄偑斀嫞憟揑偱偁傞偲偺嵸掕偑壓偭偨丅偦偺屻丄僥儕傾丒僼傿儞儔儞僪偼儔僕僆儕僯傾偲偺娫偵儘乕儈儞僌嫤掕偺掲寢偱崌堄偟偰偄傞丅 側偍丄崙撪儘乕儈儞僌偱僱僢僩儚乕僋傪傑偨偑傞応崌丄堦扷実懷揹榖婡偺揹尮傪愗偭偰擖傟捈偡昁梫偑偁偭偨偑丄僥儕傾丒僨儞儅乕僋偑1999擭9寧偐傜帺摦儘乕儈儞僌傪採嫙偟偰偄傞丅
丂偙偺偆偪丄僼傿儞僱僢僩丒僌儖乕僾偼丄僿儖僔儞僉丒僥儗儂儞乮HTC乯側偳僼傿儞儔儞僪偺奺抧堟枅偵愝棫偝傟偨抧堟揹榖夛幮46幮偺楢崌懱偐傜峔惉偝傟偰偄傞丅僼傿儞儔儞僪偱儐僯乕僋側偺偼丄1,800MHz懷偺廃攇悢柶嫋偑婛懚900MHz懷帠嬈幰偺僜僱儔丄儔僕僆儕僯傾埲奜偵丄抧堟揹榖夛幮偱偁傞僼傿儞僱僢僩丒僌儖乕僾偵傕妱傝摉偰傜傟偰偄傞揰偱偁傞丅 丂僼傿儞僱僢僩丒僌儖乕僾偼偙偺1,800MHz懷偺廃攇悢傪巊梡偟偰丄1997擭偐傜抧堟尷掕偺僒乕價僗乽僔僥傿儂儞乿傪採嫙偟偰偄傞丅偙偺僒乕價僗偼丄巊梡僄儕傾偑尷掕偝傟傞丄儘乕儈儞僌婡擻偑側偄乮椺偊偽丄僿儖僔儞僉偱宊栺偟偨傕偺偼懠偺搒巗偱偼棙梡偱偒側偄乯戙傢傝偵旕忢偵埨偄椏嬥偱採嫙偝傟偰偄傞乮HTC偺応崌偺捠榖椏偼 FIM 0.45乛暘丟偪側傒偵屌掕揹榖偼 FIM 0.49乛7暘乯丄偲偄偭偨摿挜傪帩偭偰偄傞丅偮傑傝丄実懷揹榖偺媄弍丒愝旛傪巊梡偟偨屌掕揹榖揑側僒乕價僗偲尵偊傞丅揹榖斣崋偵偮偄偰傕丄屌掕揹榖偲摨懱宯偺傕偺偑晅梌偝傟偰偄傞丅 丂慜弎偺傛偆偵僼傿儞僱僢僩丒僌儖乕僾偼GSM帠嬈幰儔僕僆儕僯傾偺恊夛幮偱傕偁傞偑丄採嫙摉弶偙偺乽僔僥傿儂儞乿偼儔僕僆儕僯傾偺GSM僒乕價僗偲偼慡偔暿屄偺僒乕價僗偲偟偰採嫙偝傟偨丅偟偐偟丄搒巗娫偺堏摦偑懡偄儐乕僓乕偵偲偭偰偼丄抧堟尷掕偺僔僥傿儂儞乮1,800MHz懷乯偲慡崙僒乕價僗偺GSM乮900MHz懷乯偺椉曽偺実懷揹榖婡傪帩偪曕偔偙偲偼晄曋偱偁偭偨偨傔丄1戜偱2枃偺SIM乮偮傑傝2偮偺夞慄宊栺乛2偮偺揹榖斣崋乯偵懳墳偡傞実懷揹榖婡偵傛偭偰丄偙偺晄曋傪夝徚偟傛偆偲偟偨傕偺偱偁傞丅暋悢偺SIM偵懳墳偡傞丄偄傢備傞僨儏傾儖丒僗儘僢僩宆偺実懷揹榖婡偺奐敪丒惢憿偵偼丄僼傿儞儔儞僪偺儊乕僇乕偱偁傞儀僱僼僅儞幮偑実傢偭偰偄傞丅
丂摿偵栤戣偲側偭偰偄傞偺偼忋婰匒偱偁傝丄偙傟偵偼墷廈彅崙偱3G偺柶嫋偑婛懚帠嬈幰偺悢傛傝傕懡偔敪峴偝傟傞偲偄偆帠忣偑攚宨偑偁傞丅婛懚偺帠嬈幰偺応崌偼3G偺彜梡壔偵偁偨偭偰帺幮偺2G栐偲偺僨儏傾儖丒僒乕價僗偵傛偭偰僄儕傾傪曗姰偟偨僒乕價僗偑採嫙偱偒傞偺偵懳偟丄怴婯嶲擖幰偺応崌偼偦傟偑偱偒側偄丅偙偺揰偵偮偄偰嫞憟忋晄岞暯偱偼側偄偐偲偺堄尒偑偁傝丄偦傟傪夵慞偡傞偨傔丄婛懚偺2G帠嬈幰偵偼怴婯嶲擖偺3G帠嬈幰偐傜儘乕儈儞僌傪怽偟崬傑傟傟偽偙傟偵墳偠傞媊柋傪壽偡傋偒偱偼側偄偐偲偺媍榑偑婲偭偰偄傞丅 丂偙偺栤戣偑尠嵼壔偟偨偺偑塸崙偱偁傞丅塸崙偺婯惂婡娭偱偁傞僆僼僥儖偼1999擭7寧23擔偵丄3G柶嫋傪曐桳偡傞帠嬈幰偵懳偟偰丄婛懚偺2G帠嬈幰偼儘乕儈儞僌傪採嫙偡傞媊柋傪晧偆偲偡傞寛掕傪敪昞偟偨丅庡梫側億僀儞僩偼埲壓偺捠傝偲側偭偰偄傞丅
丂忋婰偺儚儞2儚儞偺庡挘偺傛偆偵丄婛懚帠嬈幰傊偺儘乕儈儞僌媊柋晅偗偱傑偢栤戣偲側傞偺偼丄婛懚2G偱偺柶嫋忦審偱偁傞丅偦偺偨傔丄揹婥捠怣偵娭偡傞惌嶔婡娭偱偁傞杅堈嶻嬈徣乮DTI乯偼10寧8擔丄儃乕僟儂儞偍傛傃BT僙儖僱僢僩偲偺娫偱丄儘乕儈儞僌採嫙媊柋偵娭偡傞柶嫋忦審偺堦晹傪廋惓偡傞偙偲偱崌堄偟偰偄傞丅儃乕僟儂儞偲BT僙儖僱僢僩偑帺幮偵晄棙偵側傞儘乕儈儞僌媊柋晅偗偵崌堄偟偨偺偼丄媍榑偑挿堷偔偙偲偵傛偭偰3G柶嫋偺晅梌帺懱偑抶傟傞偙偲傪寽擮偟偨偨傔偱偁傞丅 丂塸崙偱偺媍榑傪庴偗偰懠偺墷廈彅崙偱傕丄怴婯嶲擖偺3G帠嬈幰亅婛懚偺2G帠嬈幰娫偺儘乕儈儞僌偵偮偄偰偺媍榑偑妶敪偵側偭偰偒偰偄傞丅椺偊偽僼儔儞僗傗僗僂僃乕僨儞偱偼丄塸崙偲摨偠傛偆偵3G柶嫋偑婛懚偺2G帠嬈幰悢傛傝1偮懡偄4幮偵妱傝摉偰傜傟傞偙偲偵側偭偰偄傞偑丄婛懚帠嬈幰偵傛傞怴婯嶲擖幰傊偺儘乕儈儞僌媊柋晅偗偑帎栤暥彂偵惙傝崬傑傟偰偄傞乮僗僂僃乕僨儞偵偮偄偰偼朄惂壔偑梊掕偝傟偰偄傞丟暿峞傪嶲徠乯丅堦曽僪僀僣偱偼丄尰嵼僼傿傾僋丒僀儞僞乕僐儉偲T亅儌價儖偲偺娫偱峴傢傟偰偄傞儘乕儈儞僌偑岎徛儀乕僗偱幚巤偝傟偰偄傞偙偲偐傜丄儘乕儈儞僌媊柋晅偗偵偮偄偰偼斲掕揑側柾條偱偁傞丅 |
|
惓奯 妛 乮擖峞丗2000.5乯 |
| InfoCom僯儏乕僘儗僞乕乵僩僢僾儁乕僕乶 |