| ホーム > レポート > マンスリーフォーカス > |
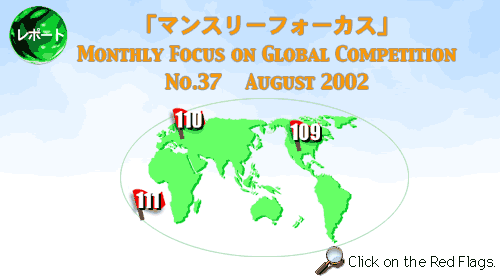
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109. ワールドコム破綻の原因と対策(概要)粉飾決算ショックで株価が急落したワールドコム(WCOM)は、2002年7月21日にニューヨーク連邦破産裁判所に連邦破産法第11条の適用を申請した。$1,070億の資産を保全し$410億の債務返済を停止し再建計画を裁判所に認めてもらうためである。再生期間中は例えば年間$20億の利払いも停止される。 資産規模から見て史上No.1の倒産であり、No.2 Enron(電力・ガス$633億)、No.3 Texaco(石油$358億)、No.4 Financial Corp.of America(金融$338億)、No.5 Global Crossing(通信$255億)などに抜きん出て大きい。融資などを通じてWCOMと関係が深いとされるドイツ銀行の株価が7月22日に7%下がったのを始め、通信企業の社債を多く保有すると見られる通信機メーカーの株安を誘った。7月23日以降も株価の動揺は続き、米国のダウジョーンズ工業平均が1998年10月以来の低レベルに達し英国のFTSE100種平均が6年振りの低位を記録するなど主要株式市場株価平均指数を下げ、企業不信のうねりを起こすなど大きな影響をもたらした。 電気通信の倒産はドットコム・クラッシュの10倍も大きい。過去2年間に米国通信産業でレイオフされた従業員数は50万名、下がった通信企業の時価総額(投資家の損失)は$2 兆、総債務残高は$1兆に達する。何故このような倒産が起きたのか、最も単純な説明は、多くの企業が“インターネット熱”に取り付かれトラフィックを運ぶネットワーク建設したが、その建設ブームの根拠が間違っていたと言うのである。(1)投資をしたのに需要は出なかった、(2)「ネットワークの相互接続点、従って網の有用性はノードまたはユーザの数の二乗に比例する」というメトカーフの法則を鵜呑みにして大規模投資に走った、(3)インターネットと言えども製品開発と利用者の受容には時間がかかるのに、インターネットは一夜にして需要に転化すると賭けた誤りである。 米国のインターネットバブルが2000年3月にはじけ、以来ITバブル崩落不況が長引き、2001年9月の対米テロ突発により未曽有の不況が進行し、四半期毎の業績と株価の相互影響が続く環境下で、このような間違いが起きた。 相次ぐ不祥事で「信頼の危機」を生まれたことに対して米国の官民の反応はすばやく、資本主義システムが悪いのでは無く規律を失ったところに問題があるとの危機感に基づき、連邦議会で「企業改革法(Sarbenes-Oxley Act)」が2002年7月25日に成立し、同月30日ブッシュ大統領が署名した。 企業改革法は、(1)企業の会計書類改竄・破棄やインサイダー取引・相場操作といった証券詐欺に対する罰則の強化、(2)監査法人を監督する独立監視機関の設置、(3)重要情報の即時開示など企業の情報開示義務の強化など中心とする膨大なルールである。 FBIは2002年8月1日にS.サリバンWCOM前CFOとD.マイヤーズ(David Myers)前経理部長を不正な会計処理で投資家に虚偽の情報を与えた証券詐欺の容疑で逮捕した。 債務総額$410億は社債$290億、銀行融資$26.5億、及びメーカー金融(vender finance)などで構成されるが、債務株式交換(debt-equity swap)によれば、社債保有者は財務健全な事業に見合う株式を受け取れば希望が持てるし経営側も債務の大幅削減が望めるからである。問題はワールドコムの三つの中核事業、(1)世界データ網UUNET、(2)企業向け長距離通信サービス事業、(3)個人向け長距離通信サービス事業のどれに見合う株式が割り振られるかである。連邦破産法に定められた検討期間は4カ月だが、関係者は最低9カ月かかると見ているようである。 110. 低迷するヨーロッパ通信業界(概要)ヨーロッパの通信業界は需要低調ながら2001年業績は予想外に良かったが、大規模投資や3G免許取得に伴う巨額債務及び買収企業の株価値下がりなどへの対応から2002年第1四半期に経営収支が悪化し、その業績発表の頃に問題が表沙汰になってきた。西欧の通信サービス企業で政府出資がなお高いドイツテレコム(DT、43%)やフランステレコム( FT、55%)の場合は政治がからむ面もある。 経済環境が悪化した時巨額債務の圧迫で通信サービス企業の株価がどのように変動するか、西欧主要国の実態をまとめると次表の通りである。 西欧主要通信サービス企業の株価状況
ドイツではDT経営の不振と株価低迷のなか総選挙を控えた与党の支持を失ったDTのR.ゾンマーCEOが7月11日に辞意を表明し、6カ月暫定を条件に後任者が決まった。 過剰投資と巨額債務の削減に苦しみながらなおグローバルキャリアーの野望を捨てていないDTやFTと違って、新生BTは完全な民間会社として再建策に取り組んでいる。 イタリアでは1999年5月以来政府がTIの黄金株3.4%を所有し、オリベッティが株式の過半数を保有していたが、2001年7月にピレリ(Pireli SpA)とベネトンファミリーが$61.4億でオリベッティ保有TI株式を買収した。TIは移動通信子会社TIM(Telecom Italia Mobile)の稼ぎは良いが支出も多いため、2001年決算は増収率13%だが赤字という経営状態であるものの、株価は安定している。 スペインの通信自由化は比較的遅いが1997年2月に完全民営化されたTEFは、最近ドイツ、イタリア、スイス、オーストリアへの携帯電話事業進出がコスト上問題として一時凍結する措置をとっている。 ここ2-3年でヨーロッパ通信業界の伝送容量過剰問題は解決され需給バランスは回復されるとして、IP時代にはトラフィック増が売上増につながらない面があるので、高付加価値サービスの創出が重要である。 111. 伝統メディア勢に復讐されたインターネット推進派(概要)2002年4月からAOL部門の指揮をとり5月にAOL TWの事業運営責任者(CCOO)に任命されたR.ピットマンは7月28日に辞任し、同日ドイツのベルテルスマン(Bertelsmann)のT.ミッデルホフ(Thomas Middelhoff)会長兼CEOが辞任した。その理由は将来戦略に関する意見の相違があったとだけ発表されたが、7月3日のJ-.M.メシエVU会長兼CEO辞任とあわせると同じ月にメディア・コングロマリットのトップ交代、しかもインターネット推進派が伝統的メディア派に復讐されたという図式が浮か上がる。 しかしミッデルホフ辞任の根本原因は彼の証券市場に対する態度であろう。ミッデルホフはメディア・コングロマリットの雄として生き残るためには将来株式を公募することもあり得ると考え、2001年に欧州一の放送ネットワークRTLグループを傘下に収めたとき合弁事業の25.1%株式について2005年までの買い増しオプションをベルギーの金融業者GBLに与えようとしてモーンファミリーに拒否されたことがあった。その時ミッデルホフは企業戦略と企業文化のあいまいな一線を越えたのではないか。 混乱のうちに退いたメシエや就任間もなく去ったピットマンと違い、ミッデルホフは限界を悟って名誉ある撤退をスマートに演じたと思われる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <寄稿> 高橋 洋文(元関西大学教授) 編集室宛 nl@icr.co.jp |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲このページのトップへ
|
| InfoComニューズレター |
| Copyright© 情報通信総合研究所. 当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。 InfoComニューズレターを書籍・雑誌等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。 |