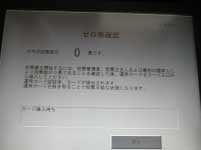新見市の電子投票レポート
2002年6月23日、岡山県新見市で、全国初となる電子投票が実施された。
本稿は、選挙前日から当日の開票終了までの取材結果をもとにしたレポートである。
- 新見市の概要
- 電子投票への備え
- 投票当日:2002年6月23日(日)
- 開票
- 新見市の電子投票によって示された今後の課題
- まとめ
1. 新見市の概要
2002年6月23日、おりしも全国でワールドカップ・サッカーが盛り上がる中、日本では最初となる電子投票が岡山県新見市の市長選挙および市議会議員選挙において実施された。新見市は、人口約24,000人(当日有権者数19,381人)、岡山空港から倉敷経由で、バスと電車を乗り継ぎ2時間程度、鳥取県との県境に位置する。
新見駅で降りると、駅前には「全国初 電子投票のまち 岡山県新見市」と書いたPR塔が立つ。投票日前日とあって、候補者の「最後のお願い」が街中にこだましているが、それ以外は静かな週末であり、市民の間で「電子投票だから」という特別な期待感や不安感は特段感じられない。但し、市内の宿泊施設やタクシー会社は、全国から押し寄せる取材や視察の利用客により、大変な賑わいを見せていたようである。
以下、投票日前日までの新見市の取組みと、投票当日の投票時間帯について整理する。
2. 電子投票への備え
(1)新見市の取組み
そもそも新見市では下記のような経緯で、電子投票への取組みを進めてきた。
電子投票の取組み経緯
| 時期 |
経緯 |
| 2001年2月 |
電子投票制度の創設について、国・県に要望書を提出 |
| 2001年9月 |
新見市電子投票導入研究会による調査研究に着手する。 |
| 9月7日 |
第1回 新見市電子投票導入研究会の開催
委嘱書交付、役員の選出、電子投票の概要について説明 |
| 9月25日 |
第2回 新見市電子投票導入研究会の開催
電子投票機器のデモンストレーション(電子投票普及協業組合)
機器について質疑、模擬投票結果について意見交換 |
| 10月21日 |
市民を対象に電子投票機器のデモンストレーション
(電子投票普及協業組合・富士通機電(株)) |
| 10月23日 |
第3回 新見市電子投票導入研究会の開催
電子投票機器のデモンストレーション(富士通機電(株))
機器について質疑、模擬投票結果について意見交換 |
| 11月27日 |
第4回 新見市電子投票導入研究会の開催
2回の研究会で体験した模擬投票の結果について、意見交換 |
| 12月7日 |
第5回 新見市電子投票導入研究会の開催
調査研究結果について、取りまとめに着手 |
| 12月18日 |
第6回新見市電子投票導入研究会の開催 |
2002年
1月10日 |
新見市電子投票導入研究会報告書提出 |
(2)模擬投票
新見市では、電子投票の実施が決まった後に、電子投票への備えとして、市民への広報や、いち早く電子投票に慣れてもらうことを目的として、2002年4月9日から6月14日までの約2ヶ月にわたって、市内各地で投票端末を利用した模擬投票を実施した。この間、模擬投票を行った市民は、のべ12,239人である。
この模擬投票の効果は予想以上に大きいようで、投票を終えて投票所から出てきた投票者(特に高齢世代)からは、「当日までに何回も練習したので何も困ることなく投票できた」という声が多く聞かれた。
模擬投票体験者数
出所:新見市ホームページ
| 移動巡回啓発車 |
1,765人 |
| 常設会場(本庁・市民センター等) |
2,424人 |
| 各会場(集会所・市内各会場) |
8,050人 |
| 合計 |
12,239人 |
(3)広報、PR

電子投票の懸垂幕 |

電子投票記念まんじゅう |
新見市選挙管理委員会では、市民のみならず全国に向けて、「全国初の電子投票のまち」をアピールするため、市内に電子投票巡回啓発車を走らせると同時に、市役所庁舎に懸垂幕(写真)を新見駅前にはPR塔を、開票所となる「まなび広場にいみ」には、アドバルーンを設置し、新見市のホームページ上で公開している。また、市内の商店に働きかけ、「電子投票記念まんじゅう」(写真)や「電子投票記念弁当」、「電子投票クッキー」など地域振興の観点も忘れていない。
ちなみに、「電子投票まんじゅう」は、ブルーベリー味の餡子が饅頭の皮に包まれている。電子投票は、候補者名を記入するのではなく、電子的な画面を見て候補者を選択することから、目に優しいと言われるブルーベリーを取り入れた饅頭としたそうだ。
3. 投票当日:2002年6月23日(日)
(1)投票の手順
投票当日は、朝7:00から、新見市内43の投票所で投票機152台を用いて実施された。
投票の手順は、記事「電子投票のアウトライン 第3項 電子投票のイメージ」に記したものと大差はない。また、今回の新見市における電子投票は、以下の新見市のホームページ内でも擬似体験が可能である。
(2)投票開始直前
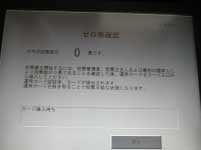
ゼロ票確認画面 |

ゼロ票を確認し署名する投票者 |
午前6:00、市内のある投票所では、選挙事務の従事者が、やや緊張した面持ちで最終的な事前チェックを行って、投票開始を待っている。一方、投票者は、この時点で一人の男性が全国初の電子投票において、一番乗りを果たそうと待っていた。投票所内では投票管理者を中心として、電磁的記録式投票機や投票カードの発券機などが正常に起動していることを確認し、手順を確認し合う。
投票開始の7:00直前、従来の自書式投票では、投票箱の中に票が入っていないことを最初の投票者に確認してもらう、いわゆる「ゼロ票確認」が行われるが、電子投票でも同様の手順が取られる。もちろん、電子投票では投票箱はなく、相当するのは投票内容を記録する電磁的記録媒体(新見市で採用した端末機では「コンパクトフラッシュ」という媒体)を内蔵している電磁的記録式投票機である。先程の一番乗りの男性が投票所の中に通され、すべての投票端末に表示された「現在の投票総数は0票です」の画面を確認した後に、「ゼロ票であること」を承認し署名する。無事にゼロ票確認が済み、投票が開始された。
(3)投票者の反応
新見市では、投票開始から1時間程度(7:00〜8:00頃)の投票率が非常に高い。市内のある投票所では、投票開始時点で20人程が入口の前に並び、はじめの1時間は次々に投票者の車が駐車場を出入りする。余談であるが、あまりの混雑に、投票を終えた人が、選挙事務従事者に駐車場の車の誘導を依頼するほどであった。

投票機設置所 |

電子投票カード |
さて、模擬投票でかなりの市民が電子投票を体験したとはいえ、実際の選挙では、模擬投票と違って、選択した候補者名が表示されている状態で操作方法を尋ねたところで、投票管理者は画面を見るわけにはいかず、投票者が操作のどの部分に途惑っているかを想定して説明するしかない。実際に、途惑う投票者が多かったのは、投票カードの挿入口がどこなのかといった点や、カードを逆向きに挿入する、あるいは投票終了後にカードを取り忘れるといったことであった。朝の混雑する時間帯で、次々に来る投票者に対して、投票管理者は、休みなしに繰り返して操作の手順を説明する。投票者の中には、操作方法が分からず、隣の端末で操作中の知人に聞こうとして、投票管理者が慌てて止めに入るシーンも見られた。
しかし、そうは言っても、模擬投票の成果であろうか、このように投票に途惑う人は高齢の投票者の中に散見される程度である。投票の一連の流れに掛かる時間も、平均で約30秒程度、筆者が確認した中では、もっとも時間の掛かった高齢の投票者でも100秒程度であった。また、投票所の外には新聞・テレビ等の記者が、投票を終えて投票所から出てきた投票者にインタビューを行っていたが、それらに答える投票者の話では、概ね電子投票に好意的であったと言える。
また、今回の投票端末には、障害者に配慮したバリアフリー機能(車椅子での投票に配慮した画面設計や、視覚障害者への音声ガイダンス機能等)が備えられている。こうした機能に対しても、確実に投票者の意思を結果に反映させるという効果から、歓迎されたようである。
(4)当日のトラブル
日本で初めての電子投票ということで、本番では、想定外のトラブルなどが懸念されたが、一部の投票所で、選挙事務従事者が、先の「ゼロ票確認」の手順を誤り、投票開始が40分程度遅れるという人為的なミスや、投票端末が、投票カードを読み取らなくなってしまい、予備の端末機で対応するという機械的なトラブルが発生したものの、投票されたデータに異常はなく、大きな障害とはならなかった。
また、投票者が投票所に着いてから、受付を済ませ、カードを受け取って投票機設置所の前に立つまで、待ちなしの状態で約30秒である。混雑時に、すべての投票機が埋まっている場合には、受付からカードの受け渡しまでの時間を調整しているようにも見える。
さて、投票開始から1時間を過ぎた辺りから、投票所を訪れる投票者の数もペースダウンし始めた。投票所の混雑がピークを過ぎ、選挙事務従事者にとっては一山を超えたという安堵感が伺える。
(5)投票終了
時計の針が午後8:00を指し、投票管理者が投票終了を宣言すると、電磁的記録媒体は正本、複製ともに、端末からの取り出しと封印が行われる。管理簿など必要な書類を整理し、封印された電磁的記録媒体は、開票所である「まなび広場にいみ」へ運ばれる。あとは、投票結果が無事に開票・集計されるのを待つばかりである。
4. 開票

電子投票の開票・集計 |
開票所は、新見市役所前の「まなび広場にいみ」である。開票所には、全国初の電子投票の開票・集計を一目見ようと、新見市民、選挙事務従事者、他の地方公共団体職員、マスコミ各社が大勢詰めかけている。午後9時20分、選挙管理委員長が挨拶し、電磁的記録媒体の装置箱の開錠、開票立会人の確認、媒体の封印解除が手際良く進められ、午後9時35分に、いっせいに開票・集計が開始された。また、同時に、前日までに従来の自書式投票で行われた不在者投票についても、手作業による開票・集計も開始された。
電子投票分の開票担当者は、不正が行われないように配置された監視担当者を背にしながら、封印を解除された記録媒体を開票用のコンピュータで次々と読み取っている。そしてついに午後9時50分、電子投票分の開票・集計結果が発表された。もちろん、自書式で行った不在者投票分については、この時点では結果が判明していないが、それでも電子投票分だけで約90%の途中経過が明らかとなり、市長選挙の結果と、市議会議員選挙の結果の一部が定まることとなった。
その間、わずか25分。電子投票は、大きなトラブルもなく、その効果の大きさを見せつけた結果となった。翌日、全国紙・地方紙を問わず、新聞各紙は、全国初の電子投票の成果を一面で取り上げた。当日、現地に視察に来ていた他の地方公共団体も、新見市の成功を見て、実施に前向きとなったことであろう。しかし、失敗は許されないという状況で、無事に電子投票の先駆者の役割を全うした関係各者の並々ならぬ働きがあってこそであると思う。投票終了の午後8:00、投票管理者の投票終了の宣言直後に、投票所の外へ出てきて煙草を一服していた選挙事務従事者の、あの安堵の表情は忘れられない。
開票・集計の経緯
| 時間 |
開票・集計手順 |
| 午後8時00分 |
投票終了 |
午後8時00分
〜午後9時20分 |
電磁的記録媒体の封印
投票所の撤収作業
電磁的記録媒体等の開票所への送致 |
午後9時20分
〜午後9時25分 |
選挙管理委員長の挨拶 |
午後9時25分
〜午後9時26分 |
全投票所分の電磁的記録媒体の送致箱を開錠、不在者投票分の開封
(開票開始) |
午後9時26分
〜午後9時31分 |
開票立会人によって、開錠された送致箱と電磁的記録媒体(封印)の確認を行う。 |
午後9時31分
〜午後9時35分 |
電磁的記録媒体の封印を解除 |
| 午後9時35分 |
電磁的記録媒体の読取りの開始 |
| 午後9時48分 |
電子投票分の開票・集計結果のレポートの打ち出し |
| 午後9時50分 |
新見市長選挙/新見市議会議員選挙の電子投票分の結果発表
(電子投票分の開票・集計の終了) |
| 午後11時20分 |
不在者投票分の開票・集計の終了 |
5. 新見市の電子投票によって示された今後の課題
我が国で初めての電子投票ということで日本全国から注目を浴びている中、今回の新見市が大過なく無事に成功させたことは、今後の電子投票の普及を考える上で非常に大きな収穫であると思う。選挙事務に携わられたすべての関係各位にあらためて敬意を表したい。
また、同時に今回の新見市の電子投票によって明らかとなった検討課題について整理することが、今後の電子投票の普及に向けて重要である。以下に、電子投票の普及に向けて新見市の電子投票によって示された今後の検討課題について整理した。
(1)不在者投票の電子化

不在者投票の開票 |
先述のように、午後9時50分の時点で、投票の約9割にあたる電子投票分の開票結果は判明した。しかし、残る1割にあたる不在者投票分の開票結果が判明したのは、電子投票分に約1時間半も遅れた午後11時25分である。前々回(1994年)の市長・市議会議員選挙では開票開始から終了まで約4時間半かかったことを考えれば、大幅な時間短縮であるものの、当日の電子投票分が25分で終了したことを踏まえれば、終了までの2時間は長いと言わざるをえない。
また、電子投票は、開票・集計に係る事務従事者を従来に比べて格段に減らすことが期待できるが、上の写真のように、約1割(市長選挙:1,761、市議会議員選挙1,763)とはいえ、不在者投票分の開票は手作業であるため、開票開始当初には、大勢の担当者が開票作業を行っている。
不在者投票に関する現行の制度が関連するため、課題の解決には時間を要するかもしれないが、実現した場合にはその効果は大きいと考えられる。
(2)オンラインによる伝送
今回の電子投票ではセキュリティ上の観点から、投票機を電気通信回線に接続することは認められていない。そのため投票されたデータは、電磁的記録媒体に保存され、複製とともに開票所へ運ばれる。
しかし、仮にセキュリティ上の課題を解決して、専用線やISDN等の電気通信回線を利用して各投票所から開票所へのデータ伝送が認められれば、開票開始時間を前倒しすることができ、それに伴って、必然的に開票終了時刻を早めることも可能となる。電磁的記録媒体の送致作業も省くことができ、時間的にも、また作業の手間としてもその効果は大きい。
6. まとめ
以上、わが国初となった新見市の電子投票について、事前の準備から開票・集計が終了するまでの一連の流れに沿ってとりまとめた。新見市は、他の自治体に先駆け、国政選挙への導入も見据えた試金石としても大きな注目を浴びる中、無事に大役を果たしたと言えよう。今後の電子投票の普及に向けて、大きく2つの課題があることも示したが、いずれも制度的な課題もあり、その解決には今後さまざまな観点からの議論が必要である。新見市の成果を生かすため、より一層の議論・検討が進むことを期待したい。