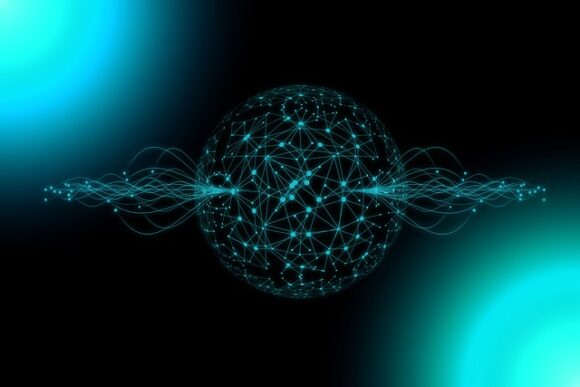組織論再び、IP網へのマイグレーションに逆行?~英国でBTとOfcomがOpenreachの法的分離を合意

英国のBTとOfcomは、3月10日にBTのアクセス事業部門Openreachを100%子会社として分離する「法的分離」の導入を合意したと発表しました。合意した法的分離とはOfcomが用いている分離モデル8段階のうち7番目のレベルに当たり、“卸売事業部門はグループの中で法的に分離された法人として設立される。ただし、同じ資本の元に残る。”という内容で、最後の8番目のレベルには資本関係までを制御する構造分離だけが残る厳しい分離モデルです。欧州を始め世界の通信先進各国では、日本を例外として、固定通信とモバイル通信の一体運営(又は100%子会社)に結局戻っているし、固定アクセス網でも同一の卸条件などの規制下にあるものの事業組織は一体で運営されているのが常態なのに、英国では何故、固定アクセス網の分離論がいつまでも消えないのでしょうか?
これにはBTのOpenreachのサービス水準が利用者の納得するレベルに達しておらず、かつ、光ファイバーの展開が大きく遅れてしまっていることが背景にあるようです。卸売事業部門の利益率は高いにもかかわらず、設備投資が進まずサービス向上が図られていないという事業経営サイドへの不満が規制当局にあるとも言われています。組織論が再燃といったところです。
日本ではどうなのでしょうか。現在、規制当局にも事業者の間にも固定アクセス網の分離論は聞こえてきません。ただし、NTTグループに対しては競合各社は常に、固定アクセス網およびモバイル通信事業の構造分離を求める声が止まないのが実状です。市場競争が始まって30年以上経過してもなお、事業(企業)組織に対して規制を強化しようとする考え方には依然として根強いものがあると感じます。今回の英国のBTとOfcomとの法的分離合意レベルのものは日本では既に1999年のNTT再編成で実現されており、制度論としては参考になるところはありませんが、サービス論、設備投資等のイノベーション論としては事業者は肝に銘ずべきものです。利用者・消費者の声こそが結局事業運営形態を制約するということです。
例えば、NTTグループ(NTT東西)の光回線卸サービスの開始にあたっても競合会社から異論が出されましたが、公平性の担保などの下で実施されて、消費者・ユーザー(利用者)からはサービスの複合化によって新たな市場競争が生じ、ユーザー利益の向上が図られています。また、英国でも固定とモバイルの一体運営によるサービスの複合化ではBTがEEを買収し完全子会社化していて進んでいますが、固定アクセス網の分離問題は今日まで続いてしまっています。結局のところ、ユーザー利益の向上に重きを置く規制当局の主張が通った印象ですが、Openreachの部門利益率が高い割には光ファイバーカバレッジの遅れが顕著なだけに、事業経営に対する政治的・政策的な思惑を感じざるを得ません。
翻って、我が国では1999年に実施されたNTT再編成においては、地域通信部門(県内)を運営するNTT東西の業務範囲は地域電気通信である本来業務と目的達成業務とに制限されていましたが、2年後の2001年のNTT法の改正によって、例えば、県内/県間区分のないインターネットに対応した低廉かつ多様なサービスが「活用業務」として提供できるようになっています。もちろん、活用業務には(1)地域電気通信業務等の円滑な遂行に支障のない範囲であること、(2)電気通信事業の公正な競争の確保に支障のない範囲であること、との要件が課されているものの、今日までにIP通信網始め多くの活用業務が行われています。このように日本ではNTTの再編成は法的分離を伴って実施されたものの、インターネット時代のIP網構築や次世代ネットワークサービス (NGN) といったイノベーションを現実に踏まえて実現してきました。
英国のBTとOfcomとの論議や妥協などは特殊英国的なサービス/事業運営事情によるので、もはや参考になるところはほとんどありませんが、むしろIP網への全面移行が目前に姿を見せ始めている日本では、地域通信部門と長距離通信部門、さらには(固定)無線通信部門との垣根がオールIP化によって意味を無くすことが顕在化しつつあると思います。IP網への移行、即ちオールIP化については日本は通信先進国・地域としては世界で先頭集団を引っ張る位置にあります。既に総務省の有識者による検討委員会で具体的な方法や手順、関係者の協議内容等が報告されています(注)。
(注)2017年6月21日、情報通信審議会電気通信事業政策部会 電話網移行円滑化委員会報告書案
「固定電話網の円滑な移行の在り方~最終形に向けた円滑な移行の在り方~」を参照。
これによれば、2025年1月にPSTNからIP網への移行を完了するとの移行工程が整理されています。現行のメタル電話はメタルIP電話へと2024年1月にサービス移行が一斉に行われます。日本のIP網への移行は今回の英国での固定アクセス網の法的分離措置に比べると先進的であり挑戦的なものです。2020年頃から本格化するモバイル通信の5G導入に加えて、固定ネットワークのオールIP化によって2025年には日本の通信ネットワークは大きな変貌を遂げることになりますので、IoT、ビッグデータ、AIによる経済・社会構造の変化、生産性向上、国際競争力強化などの政策課題に今から注力する必要があります。再度、今回の英国でのBTの法的分離の動向は我が国のIP網へのマイグレーションとは異次元のものではありますが、サービス論やイノベーション論が事業運営や経営形態を拘束するという本質を捉えていることには関係者は改めて注意を払うべきでしょう。この点、直近に興味深い出来事がありましたのでそれを取り上げて本稿を終えたいと思います。
それは、今年6月に開催されたNTTの株主総会での株主からの質問とそれに対する経営陣からの回答で示されました。「2025年に固定電話がIP網に移行する中で現行のNTT東日本・西日本、NTTコミュニケーションズという通信を地域に分けた業務運営のあり方」(2017.6.28付 日刊工業新聞)について会場の株主から質問があり、「会社の形態より、まず先にサービスが融合しており、グループ会社がそれぞれの商材を持ち合って(中略)お客様に提供できる環境が整っている」(同前)ので3社を再編成する考えはないと経営陣が回答していたのが印象的でした。2025年のIP網移行完了を見据えてのサービス融合先行(優先)方策をNTTグループが取っていることがよく理解できた出来事でした。
しかし、いずれオールIP化が完了すれば現行の地域通信と長距離通信の区分や固定通信と無線(モバイル)通信の区別などについて、事業構造や産業政策、サービスやイノベーション論からの見直し・検討は必至になることでしょう。現状固定型の利害調整ではなく、課題先取り・達成型の前向きな取り組みが望まれます。まさに「組織は戦略に従う」(アルフレッド・チャンドラー)のですから。
※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部無料で公開しているものです。
調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。
ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード
平田 正之の記事
関連記事
-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上
- WTR No441(2026年1月号)
- ヘルスケア・医療
- 日本
-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる
- WTR No441(2026年1月号)
- オーストラリア
- 世界の街角から
-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに
- 5G/6G
- AI・人工知能
- ICR Insight
- WTR No441(2026年1月号)
- モバイル通信事業者(国内)
- モバイル通信事業者(海外)
-

中国におけるロボット産業の進展
- WTR No441(2026年1月号)
- ロボット
- 中国
-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜
- WTR No441(2026年1月号)
- ポイントビジネス
- 日本
- 経済
- 金融
InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧
ランキング
- 最新
- 週間
- 月間
- 総合