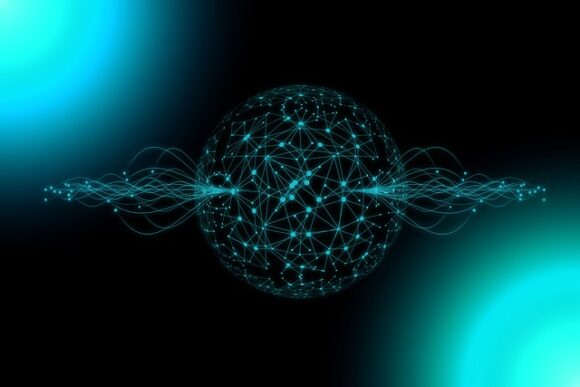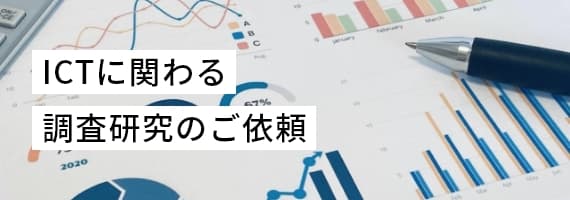デジタル産業の確立 ~デジタルトランスフォーメーション(DX)による価値創出

デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進が言われるようになってから久しい。DXという言葉は2004年にスウェーデンのウメオ大学のエリック・ストルターマン教授が提唱したもので「ITの浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」と定義しています。既に提唱から20年近くになり、世界中で企業活動に取り入れられるようになってからも10年以上が経過していますが、ビジネスの世界から見ると用語が多義的で定義も曖昧なので経営戦略上の方策として採用するにはどうしても困難が伴います。例えば、経済産業省のDX推進ガイドラインでは「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズをもとに、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と極めて長い定義付けをしています。これでは内容が多岐にわたる上、文脈が複雑で分かりにくいのでそのままでは何をどこからどうしたらよいのか判断がつきにくく、直ちに実行とはならないのが実情でしょう。そこで、複数の組織が用いている定義の中から共通しているキーワードを整理してみると、DXの目標はビジネスモデルを変革して競争優位を達成すること、その手段・方法はIT(データとデジタル技術)の活用、プラットフォームの利用、ネットとリアル(サイバー空間とフィジカル空間)での顧客体験の変革を通してとなります。グローバルなビジネス環境に比べて日本では残念ながらこうした新しい手段・方法への経営トップの理解が十分でなく、IT化はシステム部門が行うコストとの認識が通例でしたので新しい価値創出にはつながってきませんでした。
これに対し経産省は、2018年9月の「DXレポート」でDX推進の必要性と遅れへの危機感を、老朽化・複雑化・ブラックボックス化した既存システムがDXを本格的に推進する際の障壁となると指摘して明らかにしました。このDXレポートには“ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開”との副題が付いていることからも実態が窺えます。それから2年が経過した昨年12月にその続編となる「DXレポート2(中間取りとめ)」を発表して、DX推進の遅れが目立つと今度はむしろ焦燥感を表しています。即ち、2020年10月時点でDX推進指標の自己診断結果を収集した約500社の取組状況を分析した結果、全体の9割以上がDXに未着手か一部部門での実施状況であると焦燥感を顕にしています。このままではDX推進の本旨であるレガシーな企業文化からの脱却が進みません。この現状から見て、DXの推進に向けては体制整備や戦略策定・進捗管理といった短期的な企業内に閉じた実践だけでは根本的な課題解決は困難で、さらに進んで産業変革の加速や共通プラットフォームの形成、人材の育成・確保という中長期方策への挑戦が必要と同レポートは提起しています。ITシステムという個別分野のテーマから離れてデジタル企業に変身して迅速に変わり続ける能力を獲得する方策を追求するということです。具体的には、①ユーザー企業での内製化とアジャイル開発体制、②ユーザー企業とベンダー企業の協創、③企業の協調領域での共通プラットフォーム、④ジョブ型人事制度、スキルのマッチングとアップデートなどの取り組みです。どれを取っても個々のユーザー企業やITベンダーにとっては大変に難しい課題ばかりで、企業や産業全体の既存のエコシステムがそうなっていないことが根本要因となっています。企業内ではIT部門はコストセンターとの扱いで発言力が弱く、それぞれのラインのバランス調整がせいぜいの役割で全体をリードする機能を果していないのが実情です。またシステム構築はもっぱらITベンダーへの委託(ベンダーの受託)開発を続けているし、ITベンダー業界では多層的な請負関係が成立していて、人月商売の用語のとおり人件費ベースに利益を上乗せするコスト回収型の事業構造が続いています。こうなると前述のDX推進の中長期方策には結び付きにくく、従来型の基幹系システム中心の対応に終始することになり、それこそ2025年の崖に遭遇する事態に陥ることになります。
そこで経産省では今年2・3月に「デジタル産業の創生に向けた研究会」と「半導体・デジタル産業戦略検討会議」を立ち上げて急遽検討を行っています。DX推進という個別企業の変革の観点から進んで産業政策として方向性を取りまとめるという目線に移行していることに注目しています。デジタル産業という用語は新しく、戦略として新鮮な意気込みを感じます。政府の成長戦略においてグリーンとデジタルが2本柱となっているだけにデジタル産業の枠組みを定めて成長の道筋をつけることは理解し易く、DXの推進・浸透に大きく寄与すると思います。ただ私は前述のとおり受委託型の基幹系システムでのエコシステムが成立している現状から見て、新しい方策ではクラウドベースの革新性を追求する協創型のローコード開発やアジャイルなアプリ・サービス開発の方向が重点課題であると考えています。従来の企業の基幹系システムでもSoR(System of Records)に加えてSoE(System of Engagement)が求められて分散処理やリアルタイム制御が重視されるように変化してきていますが、どうしてもリアル=フィジカル空間が中心でミッションクリティカルな機能からは逃れられません。もちろん、この重要性が失われることはありませんが、今後はネットを通じてサイバー空間上で価値創出する課題解決型のソリューション提供がITシステムの中核となっていきます。もはやITではなくデータとデジタル技術に基づく領域です。
このデジタル産業を構成するのは製造業のITセクターに加えて、ソフトウェア開発企業やITベンダーなどが該当すると思いますが、厳密には他社にデジタルケイパビリティを提供する企業という定義になるでしょう。そうすると産業分類上の整理が難しいので、あえて情報サービス業、インターネットサービス業、情報通信関連製造業を加えてみると生産規模は約40兆円、雇用者数で約200万人となり、まだそれほど大きな存在とは言えません。ただ世界的には既存のシステム会社やコンサル企業の変身や新規企業の参入が続いて大きな勢力地図を構成しています。デジタル産業の確立を通じて通信インフラやプラットフォーム、クラウド、データセンターなどデジタルインフラの整備と共通化が進み、デジタルケイパビリティに関する情報共有や評価方法などを整備することで、個々の企業のDX推進も格段に取り組み易いものとなるはずです。
また、日本のソフトウェア業界ではパッケージソフトは今日までそれほど目立つ存在ではありませんが、リアルとネット、フィジカルとサイバーとを連動したクラウド、エッジ、組み込みソフトをデジタルでつなぐデジタル産業の下ではパッケージソフトには大きな成長が期待できます。そこでは企業や業界を貫く共通化がキーワードとなります。個別システムへの作り込みではなく共有要素への適用という変革が求められるからです。他方、既存のITベンダーもユーザー企業のローコード開発などによる内製化の動きに応じて協創型開発に移行していく必要があります。その場合の中心技術と中核人材はデジタルであり、ネット=サイバー空間への習熟です。DXによるビジネス変革はユーザー企業だけでなく、ITベンダー自身の課題でもあるし、通信インフラ、特にモバイル通信事業者の企業向けサービスの変革でもあることを忘れてはなりません。デジタルケイパビリティの提供はクラウドファーストとモバイルファーストの組み合わせで進めるのが近道だからです。
※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部無料で公開しているものです。
調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。
ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード
平田 正之の記事
関連記事
DX 年月別レポート一覧
ランキング
- 最新
- 週間
- 月間
- 総合