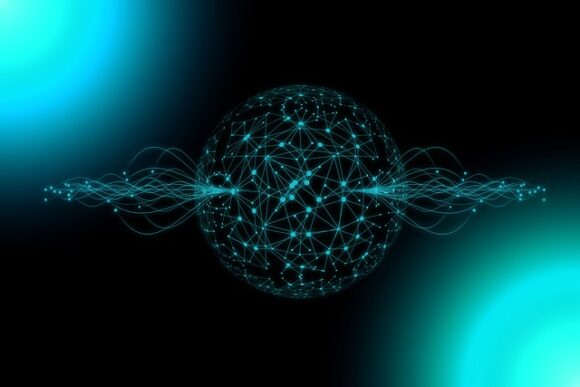働き方改革の本質 ~人事制度・組織改革とICT利活用

本年4月1日から働き方改革関連法の多くの規定が施行されています。働き方改革関連法は労働基準法や雇用対策法などの労働法制にかかわる法令の改正を通して、労働者が多様な働き方を選択できる社会を目指すものです。働き方改革の実現には、賃金など処遇の改善、時間・場所などの制約の克服、キャリアの構築という目標が掲げられているなか、それぞれ細かな条文が規定されています。なかでも、すべての企業で義務となるのが、時間外労働の上限規制(大企業-2019年4月から、中小企業-2020年4月から)、年次有給休暇の年5日取得の義務化(2019年4月から)、中小企業への60時間超過残業割増賃金率の猶予措置の廃止(2023年4月から)の3項目で、個々の会社では就業規則の改正や社内の周知・研修など対応が進められているところです。特に前の2つは直ちに従業員の労働時間に影響があるだけに職場の労働時間管理にあたる管理職の負担感も増しているように見受けられます。
前述の3項目以外にも、(1)高度に専門的な職務に就き、一定の年収がある労働者について、本人の同意があれば労働時間等の規制対象外とする高度プロフェッショナル制度の創設や、(2)フレックスタイム制の労働時間を精算する期間を最長3か月まで任意に変更可能とすること、また、(3)裁量労働制の労働者や管理監督者を含めて、労働時間の客観的把握の義務付け(労働安全衛生法、2019年4月から)など、さまざまな規定が盛り込まれているので、違反企業が罰則の対象となるだけに要注意です。
ところで、こうした労働関連法令の改正・整備が国の施策として進展していることが、直ちに働き方改革の実現になっていくのかどうか、両者の間には大きな隔たりがあるように感じます。それは日本の労働市場の現状は、深刻な人手不足、長時間労働、さまざまな格差の存在に加えて、何よりも低迷する労働生産性をどう解決するのかが課題となっているからです。政府が進める働き方改革の方策も労働関連法令の改正で枠組みを定めるだけで、同一労働同一賃金の実現も長時間労働の是正も、柔軟な働き方がしやすい環境の整備や高齢者の雇用促進もまた、すべて民間の雇用・労働関係の改善努力にかかっています。働き方改革は民間企業(組織)の問題であり、それも長期にわたって低迷している我が国産業の労働生産性をどうやって高めていくのかという課題設定には異論は見受けられません。解決すべき課題が分かっているのに具体的な方策が進まないのは何故なのかをここで考えてみたいと思います。正規・非正規の格差是正と長時間労働の是正を中心課題とする政策論議、即ち分配と時間管理への対処だけでは問題が解決しないことは理解できますが、一体どうすればよいのでしょうか。取り組みとしては単純に言えば、働き方改革をいかに生産性改革に結びつけるか、そして未来にも通用する生産性改革としていくにはどうすればよいのかに個々の企業・組織が取り組むことに尽きます。
日本の労働生産性は、日本生産性本部の「労働生産性の国際比較2018」によれば、時間当たり47.5ドルでOECD加盟36カ国中20位、1人当たり84,027ドル(年間)で同じく36カ国中21位となっていて、主要先進7カ国中で最低のレベルで推移しています(過去50年間、同時期のトップは米国)。ものづくり大国日本の象徴となっていた製造業だけを見ると1人当たりの労働生産性はOECD加盟国の中で、2000年までの1位から2016年の15位に急激に低下しています。もちろん近年に限れば為替レートの影響でドルベースの水準が伸び悩んでいる事情があると思いますが、それにしても日本の労働生産性の低さは際立っています。OECD加盟国の中には企業を国外から呼び込む税制や豊富な資源によって労働生産性を高めている国がある一方で、オランダ・ドイツ・フランスでは日本より労働時間が10~20%短く、時間当たり労働生産性が日本を上回っているのが注目されます。短い労働時間でより多くの成果を生み出すことで経済的に豊かな生活を実現しているのです。長時間労働が評価されず、短い労働時間内に極力無駄を省いて仕事を進める意識が浸透しているといわれる所似です。また他方、労働力の企業間、産業間の流動性が高いので、労働生産性の低い企業や産業は構造的に淘汰される経済構造が成立していることが見逃せません。
こうしてみると、真の働き方改革とは、一人ひとりの能力開発改革と環境変化に対応する組織変革に尽きると思います。企業は多様性ある働き方ができるようにして従業員をひきつける魅力ある場を提供しないと良い人材は集まらないと心得るべきです。そのためには、何より職場環境を魅力あるものにし、能力アップの機会をオープンに提供することが必要でしょう。当社情総研のアンケート調査をもとにした推計(2019.1.17報告発表)では、ホワイトカラーの就業者がICTを高度に利活用し、かつ積極的に働き方改革に取り組んでいる企業では、約3割の従業員が月間20.9時間の労働時間削減効果を得ているとの報告があります。遠隔会議システムや在宅勤務制度の導入などICTと勤労制度の改革とが相まって大きな成果が期待できることが分かります。
加えて、さらに人事評価や人材配置などの人事制度改革と環境変化に対応できるようにする組織の大幅な変革は避けられません。会社内外での労働力の流動性は高まっていくでしょうし、個々人の能力アップも進んでいきますので、成果がすべて社内にとどまるといった良いとこ取りはできないとの経営の覚悟が求められ、短期的な成果が出なくても長期的なキャリアのための教育研修システムを人事制度にしっかり組み込んでおく改革が必要でしょう。政府は働き方改革の実現のために、各種の労働法制の改正を行い法令の施行まで進めてきましたが、これを単純な労働者保護法制による規制強化と捉えていては改革は進みません。日本の労働生産性は国際的に見て低位にあって産業の国際競争力低下の主要因となっていることと、日本の1人当たり年間実労働時間(2017年全就業者平均)は1710時間で、OECD加盟国中22位であり、平均的水準で特に長いという訳ではありませんが、週49時間以上の長時間労働の割合(2016年、全就業者を対象)は、男性28.6%、女性9.1%、計20.1%でOECD主要国中で香港、韓国を除いて最高の値となっています。特に男性の長時間労働が際立っているので、ここに着目した働き方改革が進むことを期待しています。それぞれの企業・組織で人事制度と組織改革、具体的には評価の仕組みと配置、教育研修の改革が進むこと、さらに、これまで指摘されながらなかなか進んで来なかったICTの利活用が特に働き方改革の場面で実現することを願っています。
経営者はこれまで人材重視と言いながら、その実、どうしても人件費、即ちコストとして捉えがちで、人材=財産(人財)との認識が十分とは言えませんでした。今こそ、経営者のマインドセット、覚悟が問われていると感じています。働き方改革を進める本質はそこにあると思います。
※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部無料で公開しているものです。
調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。
ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード
平田 正之の記事
関連記事
-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上
- WTR No441(2026年1月号)
- ヘルスケア・医療
- 日本
-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる
- WTR No441(2026年1月号)
- オーストラリア
- 世界の街角から
-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに
- 5G/6G
- AI・人工知能
- ICR Insight
- WTR No441(2026年1月号)
- モバイル通信事業者(国内)
- モバイル通信事業者(海外)
-

中国におけるロボット産業の進展
- WTR No441(2026年1月号)
- ロボット
- 中国
-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜
- WTR No441(2026年1月号)
- ポイントビジネス
- 日本
- 経済
- 金融
ICT利活用 年月別レポート一覧
ランキング
- 最新
- 週間
- 月間
- 総合