大学におけるデジタル教科書の導入から見えるDX化の現状と今後の方向性
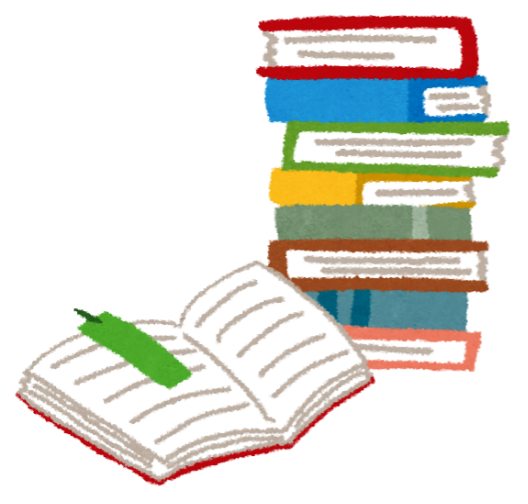
大学のDX化のポイント
大学におけるDX化(Digital Transformation)は、構想段階から実装・導入の段階に入り、各大学や関連企業等の取り組みが加速化している。そうした中で、デジタル教科書についても、導入が始まっており、今回は、その現場最前線の取り組みを紹介し、導入後の現場の声や課題、そしてその先に見えるものを考察していきたい。
最初に確認しておきたいことは、新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、やむなく、そして、それ故に急速に、授業のオンライン化が進んだという側面があるものの、本来の大学におけるDX化の目的は、「デジタルを活用した大学・高専教育高度化プラン」(2021年文部科学省)[1]にも記載されているとおり、「学修者本位の教育の実現」、「学びの質の向上」である点だ。デジタル化やICT・AI活用等は目的ではなく、あくまでもツールであること。また、従来の教育を効率化するためだけに活用するのではなく、教育の高度化・質的変革を通じて、未来を支える人材の育成のために、質の高い教育を提供することが目的であることを忘れてはならない。以上を念頭に、事例として、NTT EDX社の現場最前線の取り組みを紹介しながら考察を進めていきたい。
デジタル教科書導入の事例
NTT EDX社は、その名のとおり、Education × DX(Digital Transformation)をミッションとする会社であり、NTT西日本・NTT東日本・大日本印刷が出資して、2021年10月に設立した会社だ。具体的には大学に対して、デジタル教科書・教材等の学習用コンテンツを配信するプラットフォームサービスを提供している。
注目すべき1点目は、主要な教科書出版社や書店等と連携のスキームができている点だ。デジタル教科書は出版社ごとに提供プラットフォームが異なると、ユーザーである学生や教員は利用するごとにプラットフォームを切り替える必要が生じ、使い勝手が悪くなることは明確である。そこを各出版社や書店と合意を形成し、ユーザー目線でプラットフォームを統一したことは重要なポイントだ。さらに教員が作成したオリジナル教材にも対応可能だ。
そして2点目として挙げられるのが、プラットフォームを統一化したことにより、単に紙をデジタル化するだけではなく、冒頭に記載した「学修者本位の教育の実現」、「学びの質の向上」を目的とした教育DX実現に向け、様々な機能・サービスを展開できるようになったことである。主な事例は以下のとおりである。
反転学習への活用
- 予習復習に有効なメモ書きや全文検索、辞書参照、音声読み上げ、マーカーやコメントの共有が可能で、反転学習(デジタル教材で授業前に自宅で学習し、授業では演習や議論を中心に行う授業形態)が効果的に実現可能
電子図書館との連携
- 図書館蔵書のデジタル書籍(専門書/参考書)とデジタル教科書・教材を連携することで、更なる学生への学習サポートが可能
デジタル教科書・教材利用ログデータの活用
- デジタル教科書を用いた学習時間の可視化、学生別のページ閲覧状況の可視化、デジタル教科書にマーカーを引いた単語の可視化等が可能
著作物の権利を保護する機能の提供
- デジタルコンテンツの著作権を管理する技術であるDRMシステムを搭載
教科書選定用データベースとして教員と出版社のマッチングサービスの提供
- 場所や時間を問わずWeb上で、様々な出版社の最新教科書の内容を検索、閲覧、試読することが可能
以上のように各種の便利な機能やサービスが提供され始めている。利用したユーザーの生の声を紹介すると以下のとおりだ。
<学生の声>
- パソコンやスマホ一つで教科書を持ち運ぶことができ、ペーパーレスにもつながる
- パソコンを持ち歩けばよいだけなので荷物が減ってうれしい
- 教科書と教材を全部管理できるからなくさない
- 空きコマ等の隙間時間に他の科目の勉強をしたい時、いつでもどこでも気軽に教科書を開ける
- デジタル教科書内の検索やページ移動機能など、デジタルならではの機能がある
- 探したいワードがリストになって出てくるので便利
(紙も索引があるが、初出時のページのみで、それ以外は自分で探す必要がある) - 紙よりも気軽に付箋を張り付けたり、マーカーを引いたりできる(書き直し、引き直しができる)
- 先生のコメントを見ることができる
- 事前に学んだことを深めるための受講が可能で、もっと勉強したくなる
<教員の声>
- 単なる知識伝達型ではない授業が可能(効果的な反転授業が可能)
- 学生が教科書に記載したポイントや事前課題に対する回答を授業で共有可能(LMS連携)
(学生が自分の回答を取り上げてもらえるわくわく感を味わうことができる) - パワーポイント中心の授業からの脱却で、教科書が知識習得の入り口になる
(教科書(本)の読み方も教えることができる) - DRM機能で、教材がダウンロード不可となり閲覧のみというのは安心
- 複数のテキストの組み合わせができるのは電子ならでは
(章単位で購入してもらうことが可能) - データを取得することが可能
(学生がどのように教科書を見て、勉強しているのかがわかる) - 紙の図書館では冊数に制限もあり、順番待ちになることもあるが、それがなく、いつでも閲覧可能なので、学習の効率化が図られる
以上が、利用者である学生や教員の生の声であり、概ね、反応は良いようだ。興味深いことは、学生が抵抗感なく受け入れている点で、学習の質的変革を実現し、更なる進化に向け自律的な取り組みに変貌する可能性を感じる。
課題と今後の方向性
上記の事例を見て気になる点は、各大学で導入が進んでいるLMS(Learning Management System)との関係だ。LMSを一言でいうと、「学生や教員がオンライン授業での学びを効率的に行うことをサポートする便利なシステム」ということになるが、実現できる主な機能として、①学生がログインして自らの授業を受講する機能 ②教員が教材の指定や共有・事前の課題提供・成績管理等を行う機能 ③学生と教員がコミュニケーションを行う機能 等を有しており、オンライン授業を実施する際に、なくてはならない中核的なシステムとなっている。
したがって、デジタル教科書もLMSと連携し、LMSの中でワンストップに動作することが必要となる。具体的な利用イメージは、①認証連携によりシングルサインオンを実現 ②LMS上からワンストップでデジタル教科書・教材を登録 ③LMS上にデジタル教科書の起動リンクが自動設定 ④LMSから該当のデジタル教科書・教材の該当ページを開いて利用といったものだ。
さらには、デジタル教科書・教材の利用ログデータをLMS上の学習データ(成績等)と連携させることで、学生ごとに様々なビックデータをクロス分析し、それぞれの学生に合った学習プログラムを作成し指導することが学習の質を向上させることにつながる。デジタル教科書・教材の利用ログデータから得られる細かな学習プロセスデータは貴重なビックデータということだ。
また、デジタル教材を学生が自由に大学外等の他者と共有することを防止するDRMシステムの仕組みは、教材の著作権管理の観点からも重要でありLMS連携の重要なポイントとなる。
実際、NTT EDX社には、大学側からLMS連携のニーズが数多く寄せられており、既に一部連携機能は実装されているが、更なる連携機能の拡充を進め、同社は利便性の向上を目指している。数多くあるLMSとの更なる連携がどのように進んでいくのか注目していきたい。
また、残る課題として、教科書の著作権者の理解が深まり、多くの教科書や教材がデジタル化されること、大学の教員も紙にこだわらず、いかに思い切って切り替えられるかもポイントであり、さらには、教科書や教材のみならず、大学側から学生や教員へ渡す各種資料やシラバスとの連携等、デジタル化の範囲の拡大も注目すべきポイントだ。
最後に、通信環境について述べておく。授業のオンライン化が進むと通信トラフィックが増大し、その対策が課題となる。各大学ではWi-Fi環境の整備・拡大やLAN環境の増速により対応を進めているところであり、最近ではローカル5Gをキャンパスに設置する事例も見受けられる。また、学生の大事なデータをどこに保管するのかも大事なポイントであり、パブリッククラウドの利用も進むが、プライベートクラウド等の活用も検討する必要があるのではないかと考える。例えば、NTT EDX社では、学術情報ネットワーク(SINET)と接続した高セキュアかつ低遅延なプライベートクラウドを地域に近い場所に設置して(エッジコンピューティング)、自らが管理して提供する等、データの安全や通信速度を確保するための工夫を行っている。当然のことながら、ネットワークとクラウドの設計・運用には、通信トラフィック・通信速度・コスト・安全性・効果等を総合的に考慮して、システムの専門家だけではなく、ネットワークとクラウドの専門家による定期的な検証や改善が引き続き必要となる。
以上、デジタル教科書の導入状況を通して、大学のDX化について考察してきたが、まもなく、GIGA世代(小中高校でデジタル教科書や教材で学修した世代)が大学に入学してくることを考えると、更なるDX化は待ったなしの状況だ。現在、「デジタルを活用した大学・高専教育高度化プラン(2021年文部科学省)」では、全国で54の大学・高専が選定され、各校とも独自に様々なデジタル化のチャレンジを行っている。また多くの大学・高専で独自の取り組みも実施されている。試行錯誤の中で、良い点も課題も整理され、理想的な仕組みが出来上がっていくことを期待したい。
[1] https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/sankangaku/1413155_00003.htm
※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部無料で公開しているものです。
当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。
調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。
ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード
神谷 直応の記事
関連記事
-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上
- WTR No441(2026年1月号)
- ヘルスケア・医療
- 日本
-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる
- WTR No441(2026年1月号)
- オーストラリア
- 世界の街角から
-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに
- 5G/6G
- AI・人工知能
- ICR Insight
- WTR No441(2026年1月号)
- モバイル通信事業者(国内)
- モバイル通信事業者(海外)
-

中国におけるロボット産業の進展
- WTR No441(2026年1月号)
- ロボット
- 中国
-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜
- WTR No441(2026年1月号)
- ポイントビジネス
- 日本
- 経済
- 金融
DX 年月別レポート一覧
ランキング
- 最新
- 週間
- 月間
- 総合








