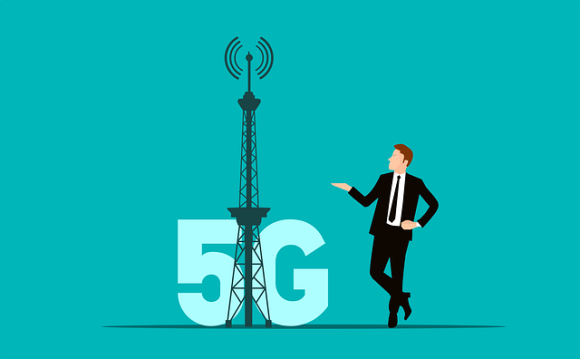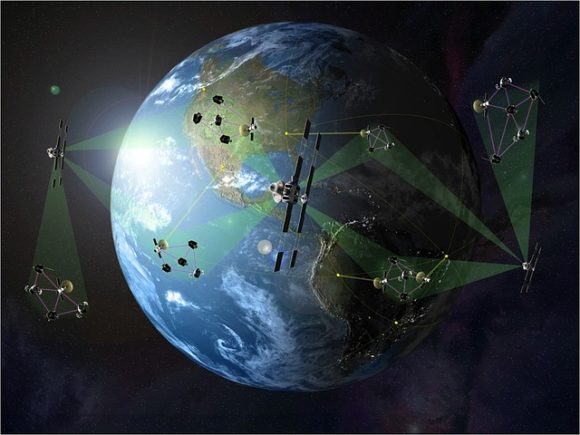迫られるグローバル通信企業の戦略転換
「欧州のTMT(テクノロジー・メディア・通信)分野では、市場の細分化や過剰な規制、業界の収益性の低さが技術の進歩を妨げる要因となっている」。
世界の通信事業者の代表者が一堂に会するMWCバルセロナ2025の初日である3月3日、スペインの大手通信事業者テレフォニカの新会長兼CEOに1月就任したマルク・ムルトラ氏が基調講演「The Gateway to a New Future」に登壇し、欧州通信業界の現状についてこのように危機感をにじませました。
ムルトラ氏は特に、市場の細分化や規制がスケールメリットを阻害し、欧州の通信業界全体として技術競争力の低下につながっていると指摘。この見解は、Financial Times紙による2月26日付インタビュー記事でも取り上げられており、「欧州が戦略的自律性を確保するためには、米国のテクノロジー企業への依存を抑えつつ、通信業界の統合を進めることが重要」との発言が紹介されていました。
こうした現状認識のもと、テレフォニカは国際競争力を維持・強化するために経営資源の選択と集中を推進しています。実際に、同社は2月24日、アルゼンチン子会社を約12億4,500万ドルで同国の通信大手テレコム・アルゼンチーナに売却すると発表しました。この決断は、非中核市場からの撤退と欧州本拠地への資源集中を進める従来からの戦略の一環とみられ、グローバル通信企業が直面する構造的な課題への対応事例として注目されます。
また、欧州を代表する通信事業者によるこうした問題提起や具体的な戦略展開は、新興国市場でのビジネス方針や、日本を含む他の通信事業者や各国の通信政策を検討する上でも、多くの示唆を与えています。
中南米市場からの戦略的撤退
テレフォニカは1990年代から中南米市場に進出し、スペイン語圏では「Movistar」ブランドを中心に事業を展開してきました。しかし、2019年11月、当時の会長兼CEOであったホセ・マリア・アルバレス=パジェテ氏は「5つのアクションプラン」と呼ばれる事業再建計画を発表しました。
この戦略の柱となったのは「選択と集中」です。グループ全体の収益の約80%を占めるスペイン、ドイツ、イギリス、そして南米で唯一のポルトガル語圏であるブラジル(Vivoブランド)を「主要市場」と位置づけ、経営資源を集中させる方針を示しました。
一方で、中南米のスペイン語圏市場については、経済の不安定性、規制の変化、為替リスク、競争の激化といった課題があるとして、段階的な撤退方針を示しました。アルバレス=パジェテ氏は「テレフォニカは30年間、ラテンアメリカ市場とともに成長してきた」と振り返りながらも、「各市場の環境が事業に影響を及ぼし、収益への貢献が低下している」と述べ、長期的な戦略の見直しが必要であると説明しました。
この方針に基づき、2019年初頭にはグアテマラ、エルサルバドル、パナマ、ニカラグア、コスタリカの中米事業を売却。さらに、南米スペイン語圏市場(アルゼンチン、チリ、コロンビア、エクアドル、ペルー、ウルグアイ、ベネズエラ)についても、市場状況を見極めながら撤退や統合を進める方針が示されました。今回のアルゼンチン事業売却も、この長期戦略の一環として進められたものです。
テレフォニカは、アルゼンチン事業の売却に続き、コロンビア事業についても中南米で事業を展開するルクセンブルクの通信企業ミリコム(Millicom)への売却を進めており、現在は規制当局の承認を待っている段階とされています。チリやペルーを含む他の国々についても、同様の撤退戦略が進められているとみられます。こうした一連の動きは、欧州戦略の強化に向けた資本の再配分の一環と位置づけられます。
アルゼンチン事業売却における戦略的意図
アルゼンチン市場は、高インフレ、政府による価格統制、資本規制など、外資系企業にとって事業環境が厳しい状況が続いています。今回の売却には、こうした不確実性からの撤退という側面があります。
目を引いたのは、「契約の締結とクロージング(最終的な資金決済および所有権移転)が同日に行われた」と公式発表に補足されている点です。通常、大型の事業売却では契約締結から完了まで数カ月を要しますが、今回は契約締結と同時に手続きを完了したと説明されています。この背景には、少なくとも二つの戦略的意図があると考えられます。
一つ目は、2月27日に予定されていた2024年通期決算発表に間に合わせることで、新CEOムルトラ氏が早期に実績を示す狙いがあったとみられます。市場では当初、売却額が約10億ユーロと見積もられていましたが、最終的に約11億9,000万ユーロ(12億4,500万ドル)での取引が成立し、発表後にテレフォニカの株価は上昇しました。
二つ目は、アルゼンチン当局による規制介入の回避です。テレフォニカは中南米で長年にわたり事業を展開しており、各国のカントリーリスクを十分に把握しているとみられます。特にアルゼンチンでは、政府の対応を見越し、規制当局が介入する前に手続きを完了したと考えられます。
実際、売却発表と同日の2月24日、ミレイ大統領府はすぐさま公式声明を発表し、「この買収により通信サービスの約70%が単一の経済グループ(テレコム・アルゼンチーナの親会社)に集中する可能性がある」と懸念を示し、国家通信機関(ENACOM)および国家競争防衛委員会(CNDC)が審査を行う方針を示しました。しかし、スペインメディアの報道によれば、テレフォニカはすでに売却代金を受け取っており、政府がこの取引を覆すことは難しいとみられています。
一方、規制リスクを抱えるのは買収側のテレコム・アルゼンチーナであり、独占回避のための事業分割や売却を求められる可能性も指摘されています。また、一部報道では、同社は政府の強い圧力を受ける「毒された資産(activos envenenados)」を抱え込んだ可能性があるとも報じられています。
このあたりの現地の反応は、中南米市場ならではの事業環境の複雑さを象徴する事例ともいえそうです。
欧州戦略の強化と市場統合への意欲
Financial Times紙によると、ムルトラCEOはテレフォニカがこの欧州通信市場の統合・再編において主導的な役割を果たしたいとの考えを示しています。中南米市場からの撤退で得た資金を活用し、「欧州内での市場統合、さらには欧州全体での統合が進むと考えており、その中で主導的な立場を確立したい」と述べています。
MWCバルセロナ2025の基調講演でムルトラ氏は、「欧州の大手通信企業が統合し、成長し、技術力を生み出す時期に来ている」と指摘。欧州委員会や各国の規制当局に対し、通信企業の統合を可能にする規制環境の整備を求めました。「これが実現しなければ、欧州の国際的な競争力は低下し続け、自律的な意思決定が難しくなる」とも述べ、業界の現状に懸念を示しました。
欧州委員会がこれまで制限してきた合併規制の緩和を検討しているタイミングで、ムルトラ氏がテレフォニカの経営を担うことになった点も注目されます。MWCでの講演の最後には、「時間が誰かを待つことはないように、技術も待つことはない」と述べ、変革のスピードが重要であることを強調しました。
日本の通信産業への示唆
テレフォニカの一連の戦略は、日本の通信企業にとっても参考になる点が多くあります。総務省の「2030年頃を見据えた情報通信政策」によれば、日本のブロードバンド環境は世界有数の水準にある一方、情報通信産業全体の成長鈍化や国際競争力の維持が課題として指摘されています。
「戦略的自律性」の確保や成長分野への重点投資の必要性は、日本の通信企業や政策当局にとっても重要なテーマです。テレフォニカが30年以上にわたり事業を展開してきた市場からの撤退を決断し、欧州市場への経営資源の集中を進める戦略は、海外市場での事業選択や資本配分を考える上で、一つの指針となり得ます。
通信業界は世界的に成熟期を迎えており、かつての高成長産業から、持続可能な成長を模索する段階へと移行しています。規制強化、競争の激化、インフラ投資負担の増大などにより、「どの市場に注力すべきか」「どこから撤退し、資本を最適化すべきか」といった判断は、すべての通信事業者にとって避けて通れない課題となっています。
テレフォニカの中南米スペイン語圏市場からの撤退と欧州市場での統合戦略は、グローバル通信企業の戦略転換を示す事例の一つとして、今後の動向が注目されます。
調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。
ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード
池田 泰久 (Yasuhisa Ikeda)の記事
関連記事
ICR研究員の眼 年月別レポート一覧
ランキング
- 最新
- 週間
- 月間
- 総合