ICT雑感:「生成AIの音楽にときめいて?」
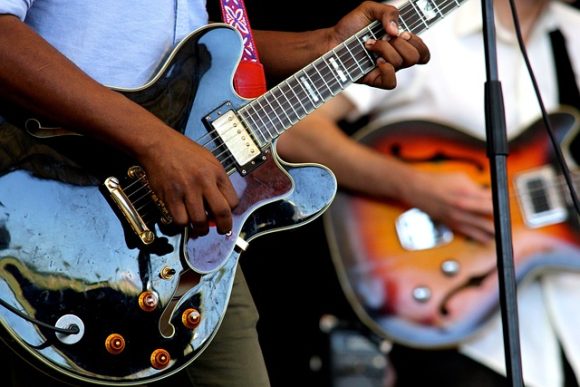
「駐車場のネコは~アクビを~しな~がら~♪」
私が中学生だった90年代後半、バンドブームしかり、日本の音楽シーンは非常に盛んだったけれど、アコースティックギターがメインの楽曲も人気だった。我もと実家の物置で埃を被っていたヤマハのギターを引っ張り出し、最初に練習に励んだのは冒頭の歌詞でおなじみの、フォークデュオユニットゆずのヒット曲「夏色」だった。指の皮が破けては厚くなり、ようやくFコードがきれいに響いたときの喜びは今も覚えている。
そんなブームに乗って、友達と放課後や週末によく集まった。「よし! 俺らもオリジナル曲で路上デビューだ!」と、今や恥ずかしさ極まりないピュアな夢を見たこともあった。
ただ、いざ曲作りとなると、これは相当に難しい。そもそもまともな形にもならなかった。曲作りのために親に頼み込んで買ってもらった小型のマルチトラックMDレコーダーは今や行方不明となり、仮に見つかってもそのまま葬り去るだろうけれど、そこには確かに創作の努力が刻まれた。当時、私はトップアーティストが紡ぎ出すキャッチーなメロディとフレーズ、そしてその世界観に共感を覚え、唯々その才能と努力に深い敬意を感じていた。
そんな経験をしたのは私だけでないはず。ところが今は作詞・作曲を生成AIでできる時代になった。コードが分からなくても、例えば米国Suno Incが開発した音楽生成AI「Suno AI」を使ってみると、「オリジナル曲」がいとも簡単にできてしまう。モノは試しとやってみたが、驚くほどに簡単だ。年末に初めて訪れた石垣島が、以前暮らしていたブラジルにどこか似ていたことが印象に残っており、思い付いたままに以下のプロンプトで出力してみた。
「石垣島とブラジルの景観やサウダージ(郷愁)をテーマに、ジャズ、サンバ、ブルースなどの曲調を合わせた南米チックな曲を作ってください」
すると瞬く間に1分強程の曲が生成された。郷愁を誘う落日の海辺のイメージ画像と合わせて生成された曲名と歌詞を含め、何だか昭和の歌謡曲にありそうな雰囲気だ。肝心の仕上がりはというと、どこかで聞いたことがありそうでなさそうな女性ボーカルの発声に所々ぎこちなさは感じられたものの、想像の斜め上を超えてくるメロディラインは少し癖になりそうで、不思議な世界観が示された。
それで試しにブラジルの公用語であるポルトガル語でも出力してみた。すると、韻を踏んだ歌詞で曲が生成された。曲のイメージ画像が何故に誰もいない部屋とその大きな窓から見える山合の風景なのかAIの真意は分からなかったが、曲自体は落ち着いたサンバ調のメロディで、こちらもブラジル人女性歌手10人を足して割り直したような雰囲気の女性ボーカルがそれっぽく歌い上げてくれた。
今回は適当に生成してみたが、Sunoにはカスタムモードが実装されており、コツを掴んでうまく使いこなせば、よりイメージに沿った楽曲が作れそうだ。公式サイト上でトレンド曲として紹介されているSunoの楽曲を聴いていると、事前に知らされなければ生成AIが作り出したとは気づかないだろう。やろうと思えば、様々な生成AIツールを組み合わせ、素人でも数時間ほどでミュージックビデオまでも制作することができるようだ。
米国の市場調査会社Market.usによると、生成AI音楽の市場規模は2022年の2億2,900万ドルから2032年に26億6,000万ドルに達すると予測されている。このような見通しに音楽業界も無関心ではない。一つは著作権や倫理的な懸念だ。日本音楽著作権協会(JASRAC)は2023年7月、生成AIと著作権の問題に関する基本的な考え方を発表し、「人間の創造性を尊重し、創造のサイクルとの調和を図ることが必要」としたうえで、「AI開発事業者によるフリーライド(ただ乗り)が容認されるとすればフェアではない」との見解を示した。Sunoでは、具体的なアーティスト名や曲名ではなく、あくまでイメージする曲のジャンルや雰囲気を入力するよう記載があったが、こうした懸念に多少の配慮を示したものなのだろう。
興味深いデータもある。フィンランドの音楽関連団体が2023年8月に国内の13歳から75歳の約1千人を対象に実施した調査によると、「AIによって創作される音楽の割合はそれほど増えない」との見方に37%が同意した。賛成・反対のどちらでもないは33%、反対は30%との結果だった。今後、生成AIが生み出す音楽のクオリティは上がっていくだろうが、私たちはこれらをどの程度受け入れていくのだろうか。
米国の経済誌Forbesは「Orchestrating The Future―AI In The Music Industry」と題した記事(2023年12月5日付)で、AIは単なるトレンドではなく、パラダイムシフトを引き起こしていると指摘した。音楽業界をダイナミックに変容する可能性を秘めており、大きなチャンスと同時にチャレンジをもたらしているという。Financial Times紙も「AI in the music industry」と題した記事(同年7月20日付)で、AIは作曲や音声クローン、リスナーへの楽曲推薦などを可能にしつつも、そもそも人間の創造性や感情的なつながりまでも置き換えることはできるのだろうかとの疑問にも触れていた。
確かにAIは、プロのアーティストにとっても創作の可能性を広げてくれる革新的なものであろう。ただ、私たちは実際のアーティストの音楽に惹き込まれるとき、その楽曲に込められた想いや背後にある社会的・文化的な文脈にも触れている。そしてその楽曲を通じ、他者との深い感情的なつながりや喜びを覚える。こうしたことは、AIが生成する音楽でも得られていくものなのだろうか。
ChatGPTにこの問いを投げかけてみたところ、迷わずに次の回答があった。
「AIが音楽を生成する能力は、音楽という芸術形式の新たな可能性を開く一方で、人間のアーティストの重要性を否定するものではないと言えるでしょう。それぞれが音楽という芸術形式を豊かにする独自の価値を持っています。この観点から、AIと人間のアーティストが共存し、互いに影響を与え合う未来が見えてきます。それは、音楽がさらに多様で豊かなものになることを意味します。それは、私たちが音楽を通じて経験する感情的なつながりや喜びをさらに深めることを可能にするでしょう」
なるほど、生成AI自身が最も冷静に未来を見据えているのかもしれない。私自身は容易に答えが出ないけれど、とりあえずは実家から、また埃を被ってしまったあのギターを引っ張り出してきて、考えようかと思う。
※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部抜粋して公開しているものです。
当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。
調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。
ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード
池田 泰久 (Yasuhisa Ikeda)の記事
関連記事
-
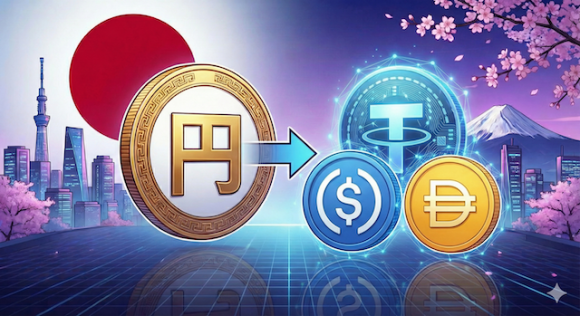
「信頼」と「ポイント文化」が融合する: 日本型ステーブルコインが描く資金決済の未来
- WTR No440(2025年12月号)
- 暗号通貨
-

スマホ特定ソフトウェア競争促進法の意義と課題(5)
- WTR No440(2025年12月号)
- 日本
-

世界の街角から:「欧州のパタゴニア」、世界自然遺産ドロミテアルプスはやっぱり凄かった
- WTR No440(2025年12月号)
- イタリア
- 世界の街角から
-

眠れる資産から始まる未来 ~循環価値の再発見
- ICR Insight
- WTR No438(2025年10月号)
- 日本
- 環境
-

自治体DXを実現するのは”公務員” 〜デジタル人材育成の実態と解決策
- DX(デジタルトランスフォーメーション)
- nihon
- WTR No438(2025年10月号)
- 地方自治体
- 日本
InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧
ランキング
- 最新
- 週間
- 月間
- 総合








