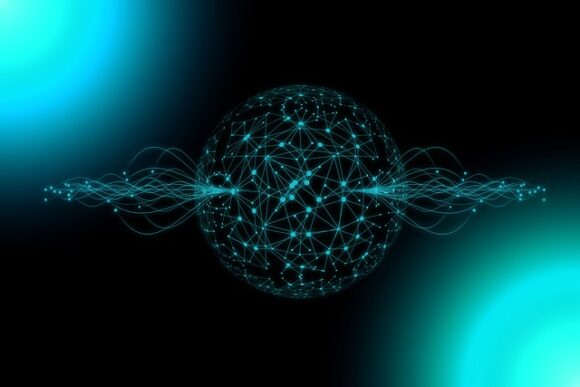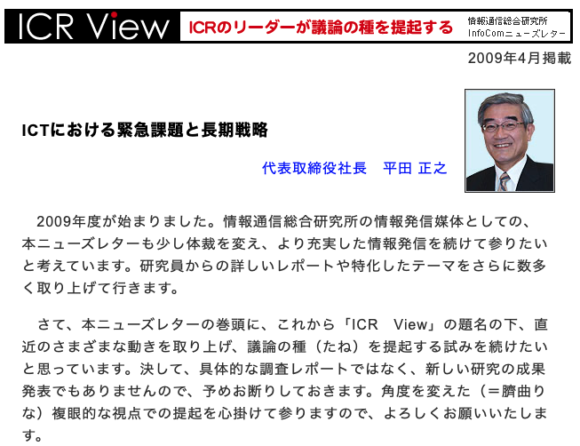標題の言葉は、江戸後期の田原藩家老で画家・学者としても著名な渡辺崋山の残した「八勿(ぶつ)の訓」の2番目にあるもので、私の座右銘となっています。この八勿の訓の第1には「面後の情に常を忘れるなかれ」とあるように、これらの教えは交渉の要諦を説いたものです。要は目先の取り組みと長期計画とのバランスをとる重要性を指摘していて、企業経営にも通ずるところです。渡辺崋山は蛮社の獄で幕府から蟄居を命ぜられ、その後、藩に災が及ぶのを恐れ、天保12年(1841年)、49歳で自刃しています。

田原城跡-小さな城の立派な城門(復元)
田原藩は愛知県の渥美半島の付け根を治めていた小藩でしたが、天保の飢饉の時に食料の蓄えにより1人も餓死者を出さずに済み、これこそ家老渡辺崋山の藩政改革の成果と称えられています。こうした歴史の事蹟を踏まえると標題の言葉の重みが伝わってきます。私は手帖に書いていつも持ち歩いています。
今回の“風見鶏”にいきなり渡辺崋山の言葉を取り上げたのは、先日2月中旬に急に春の息吹を感じたくなって渥美半島の先端まで菜の花を見に行った時に、田原市に立寄って城跡や博物館を訪れたためです。田原市は渥美半島全域をカバーしていますが、その中心は半島の入口にあり落ち着いた静かな街です。半島の各所に菜の花が植えられていて早春の冷たい風の中、黄色い花をたくさん咲かせて訪れる人々を楽しませていました。中核となっているのは、先端の伊良湖岬に近い「伊良湖菜の花ガーデン」で平日にも拘らず結構多くの人を集めていたのには驚きでした。観光による地域振興策として1月中旬からの菜の花まつりに始まり、12月までに約30のイベントを組んで渥美半島各地を取り上げて農業と漁業、即ち食につなげた町おこしが行われていました。

伊良湖菜の花ガーデン
今回は日頃、話題となることがほとんどない渥美半島を取り上げましたが、最後にこのエリアでは風の強さと日当りの良さ、土地の広さを利用して風力発電と太陽光発電が盛んに行われていて風景としても珍しい印象でした。帰途に立ち寄った浜名湖周辺でも鰻の養殖池に交じって太陽光発電パネルが数多く設置されていました(以前は養鰻場だった?)ので、海に近く風と太陽に恵まれた地域は土地さえあれば自然エネルギーの宝庫なのだと思います。

養鰻池に隣接する太陽光発電パネル
改めて、取り残されがちな半島や沿岸地域の振興に農業と漁業と観光、加えて自然エネルギーの組み合わせがあることを感じた次第です。ICTの利活用もこうしたことを探らないといけません。百年の計を決して忘れてはいけません。
調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。
ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード
平田 正之の記事
関連記事
風見鶏 “オールド”リサーチャーの耳目 年月別レポート一覧
ランキング
- 最新
- 週間
- 月間
- 総合