フリーランス新法施行にあたり考える

昨今、ビジネスの現場やマスコミ報道などで人手不足が話題にならない日はない。数値的にも今年9月の有効求人倍率は1.24倍の高い水準だ。また、同月の日銀の全国企業短期経済観測(短観)では、雇用が「過剰」と答えた企業の割合から「不足」と答えた企業の割合を引いた「雇用人員判断」(全規模全業種)は−36で、1991年11月調査以来およそ33年ぶりの水準だ。
このような人手不足の状況は平成のバブル期以来であるが、バブルの好景気が原因だった当時と異なり、今日の人手不足は働き手となる人口の減少が主たる要因であり問題はかなり深刻だ。近年の人手不足を補ってきたのは主に60歳以上の高齢者、女性、非正規労働者だ。しかし、既に高齢者と女性の労働参画は一定程度進んでいることに加え、非正規労働者数も今後の20年で約20%減少するとも言われている。長期的にはこうした特定の属性の労働者頼みでは人手不足は一層顕著になり、経済成長は言うに及ばず現在のGDP規模の維持すら難しくなるであろう。
こうした中、ライフスタイルや価値観の多様化に伴い柔軟な働き方が広がっていることや、インターネット上でビジネスの受発注をマッチングするデジタルプラットフォームの拡大などに伴い、雇用契約に基づかない働き方をする人が増えている。人手不足を補う労働力としても注目されているが、その中でも、発注主から個人で仕事を受注して働くフリーランスへの関心が高まっている。
内閣府によるとフリーランスの人数は462万人程度だ。フリーランスという言葉に法的な定義はないが、大工の一人親方など職種も多様で、実は古くからある働き方の一つでもある。フリーランスには自由に働けるなどのメリットがあるが、相対的に弱い立場であることから契約の一方的な打ち切り、不当に低い報酬設定、支払い遅延、さらにはハラスメント、偽装請負など様々な問題が生じている。また、「労働者性」が認められないため、労働基準法などの労働者を保護するための法律も適用されない。こうしたことから、近年、その法的保護をいかに図るべきかという議論がわが国だけでなく、デジタルプラットフォーマーが台頭する欧州、米国などの海外諸国においても高まっている。
こうした中、フリーランスに業務を委託する発注事業者に対して最低限の規律を設けることにより、フリーランスに係る取引の適正化やフリーランスが安心して働ける環境を整備することを目的に、2023年4月に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号、以下、「フリーランス新法」)が成立し、今年11月1日に施行された。
フリーランス新法は大きくは、①特定受託事業者に係る取引の適正化、②特定受託業務従事者の就業環境の整備、の2つから構成されている。基本的な枠組みとしてフリーランスに業務を委託する委託者に対し下請代金支払遅延等防止法(下請法)と同様の規制を課すとともに、限定的に労働者と類似の保護を規定するものだ。所管は①は公正取引委員会と中小企業庁、②は厚生労働省となっている。
具体的な内容としては、事業者として業務を受託する個人を「特定受託事業者[1]」と定義し、特定受託事業者に業務を委託する事業者に対して、取引条件の書類等による明示や給付受領日から60日以内の報酬の支払いを義務付けるとともに、特定受託事業者の就業環境の整備を図るため、募集情報の的確な表示、育児介護等に対する配慮、ハラスメントに係る相談体制の整備義務などを定めている。下請法の適用対象外だった資本金1,000万円以下の発注事業者にも適用される。これらにより特定受託事業者に法的保護が与えられることとなり、法律に違反した事業者に対しては公正取引委員会などが指導・助言・勧告を行い、勧告に従わない場合には命令・公表を行うこともある。命令違反等には罰則も適用される。
本稿ではフリーランス新法の詳細に踏み込むことはしないが、今後の課題と考えられる事項について述べておきたい。第一に「労働者性」の判断基準の見直しについてである。そもそも労働関係法上の「労働者」の概念は2つある。ひとつは労働基準法第9条に規定された「労働者」(「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」)であり、もうひとつは労働組合法第3条に規定された「労働者」(「職業の種類を問わず、賃金、給料、その他これに準ずる収入によって生活する者」)である。
労働基準法上の労働者の「労働者性」については、「労働基準法研究会報告(労働基準法の『労働者』の判断基準について)」(昭和60年12月19日)に判断の枠組みが整理されている。概括すれば、「労働者性」の有無は「使用される=指揮監督下の労働」という労務提供の形態と「賃金支払」(報酬の労務に対する対償性)によって判断される(この2つを総称して「使用従属性」と呼ぶ)。一方で、これらのみで判断することが困難な場合もあることから、「専属性」や「収入額」などの補強要素も考慮して総合的に判断するというものである。
一方、労働組合法上の労働者の「労働者」性については、①事業組織への組み入れ、②契約内容の一方的・定型的変更、③報酬の労務対価性、④業務の依頼に応ずべき関係、⑤広い意味での指揮監督下の労務提供・一定の時間的場所的拘束、⑥顕著な事業者性により判断することとされている。しかしながら、これらの判断基準はインターネットや現在のような多様な働き方が普及した社会を想定したものではない。これらの判断基準では「労働者」に該当しないが、実態は「労働者」の働き方をしているフリーランスは多いと考えられる。労基法・労組法上の判断基準を再検討すべき時が来ているのではなかろうか。
第二にセーフティーネットの問題である。フリーランス新法が施行されたことによりフリーランスの法的保護の第一歩が踏み出されたことは評価したい。一方で、労働者と比較するとフリーランスのセーフティーネットはまだ脆弱である。例えば、労災保険に特別加入できることになったが、厚生年金保険の被保険者にならないため老後の保障の充実といった課題も残る。労働者と同等の社会保障制度を整備することは容易ではないが、今後、フリーランスを含めた多様かつ柔軟な、雇用によらない働き方をする人々が安心して働けるセーフティーネットの法的整備は社会的に極めて重要な課題だ。
第三に法執行体制の問題である。前述のとおり、フリーランス新法は公正取引委員会と中小企業庁、厚生労働省が所管官庁である。しかし、市場における競争の監視・監督を役割とする公正取引委員会と、厚生労働省において労働基準行政を担う労働基準監督署とでは組織の規模、体制などの面で大きな差がある。全国各地で労働者保護のための指導などを行っている労働基準監督署のような機能・役割を、直ちに公正取引委員会に求めることが可能なのか疑問の声もある。また、これら行政機関間で二重行政や隙間行政などが生じることを憂慮する声もある。
ようやく施行されたフリーランス新法だが、その認知度が依然として低いことも課題だ。公正取引委員会と厚生労働省が今年10月に公表した調査結果[2]によると、この法律の内容を知らないという回答の割合はフリーランス側で76.3%、委託者側で54.5%となっており、認知度不足が浮き彫りになっている。特に「一人親方」が多い建設業(80.2%)や医療、福祉(77.4%)において認知度が低く、早急な改善が求められる。また、法の付帯決議[3]に見られるように多くの課題も残されており、各行政機関が連携して実効性を高めるための適切な措置が講じられる必要があろう。
今後、インターネット上のプラットフォームやAIによるジョブマッチングはさらに多様化が進み、「使用者」と「労働者」間の雇用契約を前提としない「雇用類似」の就労形態で働く人々やその職種は一層拡大するであろう。そうなれば、こうした人々の「労働者性」の判断や法的保護はより重要な社会的テーマとなる。これらの人々の法的保護を図りつつ活躍の場をさらに広げ、発注者側にとっても働く側にとってもWin-Winの関係となる新たな労働市場を形成することがデジタル化と人口減少がさらに進むこれからの社会には必要だ。
そのためには、まずはフリーランス保護の第一歩であるフリーランス新法の実効性を確実に高めることが重要となる。公正取引委員会などには違法行為を厳しく監視、摘発することを求めたい。そして、今後、さらに多面的な保護策が講じられていくことにより、フリーランスや雇用契約に基づかない多様な働き方をする人々が安心して生活し、それぞれのスキルを活かして活躍できる社会が早期に実現することを期待したい。
[1] 業務委託の相手方である事業者であって、①個人であって、従業員を使用しないもの、②法人であって、一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。)がなく、かつ、従業員を使用しないもの、のいずれかに該当するものをいう。
[2] 公正取引委員会 厚生労働省「フリーランス取引の状況についての実態調査(法施行前の状況調査)結果 概要(令和6年10月18日)https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/001317763.pdf
[3] 「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案に対する附帯決議 (衆議院・参議院 内閣委員会)」(令和五年四月)https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001144662.pdf
※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部抜粋して公開しているものです。
当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。
調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。
ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード
村松 敦の記事
関連記事
-
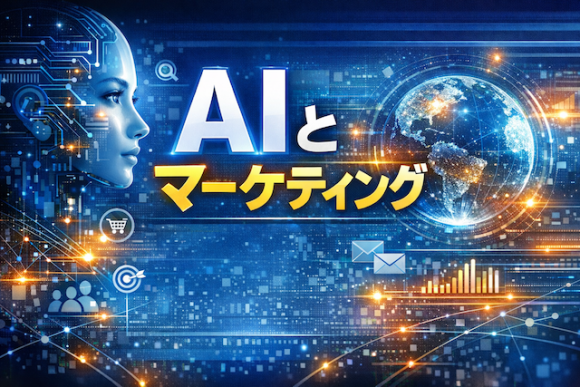
AIとマーケティング
- AI・人工知能
- ICR Insight
- WTR No442(2026年2月号)
- 生成AI
-

ICTが変える授業の形 ~複線型授業とICT
- GIGAスクール構想
- ICT利活用
- WTR No442(2026年2月号)
- 教育
- 日本
-

世界の街角から:真夏の海に浮かぶ"立体都市" ~長崎・軍艦島、半世紀後の生活の輪郭
- WTR No442(2026年2月号)
- 世界の街角から
- 日本
-

ソブリンAIを巡る各国の動向 ~制度・投資・地域連携に見る多様なアプローチ~
- AI・人工知能
- WTR No442(2026年2月号)
- 生成AI
-

超高齢社会における介護DXの可能性と課題
- DX(デジタルトランスフォーメーション)
- WTR No442(2026年2月号)
- 介護
- 医療
- 日本
- 福祉







