ロボットCA固有の問題〜季刊連載第4回 ~

第1 はじめに
約1年にわたり月刊連載を継続した後、これまで1年にわたり季刊連載を継続してきた。そして、昨年12月には、松尾剛行『サイバネティック・アバターの法律問題:VTuber時代の安心・安全な仮想空間にむけて』(弘文堂、2024)が出版された。これは、月刊連載13回と前回までの3回の季刊連載合計16本の論文をまとめた上で、既に現時点ではアウトオブデートとなっているところを改訂し、例えばVTuber関する名誉毀損(第3回)等の裁判例については連載当時19裁判例あったものを28裁判例まで増加させ、それに基づき議論したものである。同書の刊行にご協力頂いた弘文堂様及び電気通信普及財団様に感謝したい。
1 サイバネティックアバター(CA)にロボットが含まれること
季刊連載4回目である本稿においては、あるCAがロボットであるという場合に生じる問題のうち、ロボットではないCA、例えばメタバース上のアバターであるCAでは少なくとも典型的には生じないという意味において、ロボットCA「固有」の法律問題について取り上げていきたい。
月刊連載第1回でも既に述べたとおり、CAは、「身代わりとしてのロボットや3D映像等を示すアバターに加えて、人の身体的能力、認知能力及び知覚能力を拡張するICT技術やロボット技術を含む概念で、Society 5.0時代のサイバー・フィジカル空間で自由自在に活躍するもの」(強調筆者)とされている1。即ち、CA概念は元々身代わりロボットや、能力拡張ロボット(いわゆるサイボーグ技術等)を含む概念である。これまでの月刊連載・季刊連載においては、それがCAである限り、メタバース上のアバターであれ、ロボットCAであれ適用されるような議論を主に行ってきたつもりである。そこで、ある意味では、少なくともメタバース上のアバター「にも」適用可能な議論を行っていたと評することが可能である。
しかし、このような双方に適用され得るものだけがCAの法律問題のすべてとは言えない。来るCA時代を支える法解釈論や立法論を現時点で検討しておく、というムーンショット研究や季刊連載の趣旨に鑑みると、ロボットであるCAについて正面から研究し、ロボットCA固有の法律問題に取り組むことは、非常に重要であると考える。
2 分身ロボット・身代わりロボット・テレイグジスタンスロボット
読者の皆様は、OriHimeというロボットをご存知だろうか。OriHimeは、遠隔操作で動くロボットであり、例えば、寝たきりの人が、OriHimeを通じてカフェで接客等の活動を行うことができる。2019年には、「ICTや分身ロボットを活用した『社会参加』の実現を目指す社会実験の視察」として、当時の厚生労働大臣が、OriHimeを遠隔操作してカフェで働く人の様子を視察に来ている2。
このように、自分自身の分身として機能するロボットを分身ロボットと呼ぶ。また、そのロボットが自分の身代わりとして位置付けられる点を強調する意味で、身代わりロボットと呼ぶこともある。また、その目的が、テレイグジスタンス、つまり、本人が物理的には異なる場所に存在しながらも、ロボットを通じて遠隔地に同時に存在することであれば、それをもってテレイグジスタンスロボットと呼ぶことがある。これらは、場合によっては異なるロボットに対する呼称であり得るが、場合によっては、同じロボットについても、その機能や利用目的のどこに着目するかによって異なる呼称が用いられることがある。
そして、サイバネティック・アバターの定義は分身ロボット・身代わりロボット・テレイグジスタンスロボット等を含んでいる。現在、ドローンを所有しているとかドローンを操作したことがあるという人は増加傾向にあるものの、分身ロボットを所有しているとか分身ロボットの操作経験があるという人はまだ少ないかもしれない。しかし、分身ロボットが将来的に安価かつ高性能になると、今までは人がリアルで参加し、又は、オンラインで参加していたような会議に、ロボットが参加するようになるかもしれない。例えば、会社には分身ロボットを置いておいて、会議の際には、ロボットが会議室に入り、本人は例えば自宅からそれを操作し、身振り手振り等も含めてより臨場感をもって会議に参加するといった将来像が想定される。
また、メタバース上のアバターを利用した就労3ではなく、ロボットCAを利用した就労を行うことも考えられる。即ち、職場にはロボットが設置され、それを例えば自宅から遠隔で操作して就労することも、今後のアバター社会においては十分に考えられる。もちろん、そのロボットをメンテナンスする人等は必要であるから、現場に誰も人がいなくなる訳ではないのだろう4。しかし、例えば1人1台、例えば100人なら100台のロボットを利用して就労し、その100台のロボットのメンテナンス等の現場業務を1人が担当するようになる社会は十分にあり得るだろう。
3 能力拡張ロボット(サイボーグ)
CAは、例えば、6本目の指5や、第三の腕6等の人の身体的能力、認知能力及び知覚能力を拡張するロボット技術を含む概念である。「人類初のサイボーグ」等とも呼ばれたピーター・スコットモーガン博士が、全身の筋肉が徐々に動かなくなる難病に罹患し、余命宣告を受けたことを機に、身体を次々と機械に置き換えていったことは有名である7。このような能力拡張ロボットは、従来サイボーグとして論じられていたところ、こうした問題についてもCAの問題として正面から検討を行うことが必要である。
第2 出席等の概念の再検討
1 国会における「出席」
例えば国会における「出席」(憲法56条1項8)については、「原則的には物理的な出席と解するべきではあるが、国の唯一の立法機関であり、かつ、全国民を代表する国権の最高機関としての機能を維持するため、いわゆる緊急事態が発生した場合等においてどうしても本会議の開催が必要と認められるときは、その機能に着目して、例外的にいわゆる『オンラインによる出席』も含まれると解釈することができる」とするのが衆議院憲法審査会の大勢だったとされている9。現在、出産前後の女性議員や、障がいのある議員との関係での出席要件の緩和が検討されている10。
この点は、なぜ憲法が出席を求めるかという理由の根源に遡るべきである。例えば、実質的な討議を本会議場で行うべきということであれば、そのような実質的討議を行うことができる限り、議員本人が本会議場内において物理的に存在する必要は必ずしもないかもしれない。しかし、完全にオンラインで参加するよりは、本会議場に分身ロボットが物理的に鎮座し、その上で、本人が自宅や病院等からコントロールするということの方が、より物理的出席に近づくのではないか、という議論があり得る。とはいえ、会議場で物理的に出席すれば、寝ている政治家が誰か分かるが、ロボットCAで出席すると、寝ていても分からないのではないかといった問題意識等から、どのような条件の下でロボットCAの利用を認めるべきかについて、例えばオンライン出席の経験を踏まえて、さらに精緻化を行うべきである。
2 民事訴訟法における「出頭」等
また、民事訴訟法には「出頭」概念が存在する。例えば、民事訴訟法192条1項は不出頭の証人に対する制裁を定める11。そのような中で、例えば、分身ロボットを物理的に法廷に「出頭」させるものの、証人本人は自宅等他の場所から遠隔で尋問を行うことを希望する場合、これは「出頭」しないに該当するとして同項に基づく制裁を科すことができるのだろうか、それとも「出頭」したとみなされ、制裁は科すことができないのだろうか。
ここで、民事訴訟法204条(なお、現行法12と未施行規定13の間では一定以上相違があることに留意されたい)は、証人尋問をオンラインで(「映像等の送受信による通話の方法」により)実施するための所定の要件を定めている。そこで、この要件を満たす限りオンラインで尋問を行うこと自体は可能である。しかし、オンラインの尋問の場合には、証人の表情が見にくく、裁判官として心証が取りにくい等の課題が存在する。その意味では、物理的に証人席に分身ロボットが鎮座し、身振り手振り等も含む非言語コミュニケーションも交えて分身ロボットを通じて証人尋問を行った方がよいのではないかという問題意識は存在する14。
そこで、証人の「出頭」として分身ロボットによるものも含むとか、少なくとも、オンライン尋問の要件を満たす限り分身ロボットによる出頭を認めるといった解釈を明確化することが望ましいと考える。
3 その他
これら以外にも、アバター(典型的にはロボットCA)が出席する授業は大学設置基準における遠隔授業(同25条2項)か、対面での出席か等の問題もある15。
さらに、デジタル庁がアナログ規制の見直しを行い、その中で「対面」規制等が是正中であるため16、今後変化が生じる可能性があるが、多数の対面での実施を必要とする規制のうち、どれがロボットCAを通じた実施も「対面」に含まれるとして許容されるのかは重要な問題である。
第3 入国概念の再検討
南澤は「ロボットアバターでの入国は、入国にあたるのか」17と問題提起する。
出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)1条は、同法が「本邦に入国」するすべての人の出入国管理の適正化のための法律であることを謳う。そして、ここでいう「入国」については、「人が日本の領域内に入ること」(強調筆者)18と解されている。
分身ロボットを例えば国際宅配便を利用して日本に送り、その後インターネット等を利用して分身ロボットと接続して日本国内で活動したとしても、本人が未だに物理的に外国に存在していれば、(ロボットは日本の領域内に入っていても、)「『人』が日本の領域内に入る」とは言えない。よって、現行法の解釈としては、未だに「入国」はしておらず、その結果、入管法は適用されず、日本の入国管理の対象とはできないことになるだろう。
しかし、将来のアバター社会を見据える場合、例えば日本の業者が日本に存在する分身ロボットを外国人に貸し出し、会議参加や観光旅行等の活動を安価かつ手軽に行えるようにするような状況は容易に想定可能である。そのような社会においては、もしかすると物理的に来日する人は1%に過ぎず、99%の外国人の日本における活動は分身ロボットを通じて行われる等といった状況が生じるかもしれない19。
そのような状況が生じた場合において、出入国管理の方法として、従来どおりの「人」が物理的に入国したかを基準とした管理を継続してしまうと、例えば日本への入国が禁止される外国人が分身ロボットを利用して日本国内において自由に活動してしまう等の問題を生じさせかねず、入管法の目的が害されてしまいかねない。そうすると、立法論としては、外国人による一定の分身ロボットによる活動を入国管理規制又はそれに準じた規制の対象とすることも考えられる。
一例を挙げれば、入国させると問題のある可能性のある者に対しては、これまでは、例えば、入管法5条による上陸の拒否等により対応してきた。即ち、一定以上の刑に処せられたことのある者(同条1項4号)、人身取引関与者(同7号の2)、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者(同11号)等については、本邦に上陸することができないとする。しかし、同条1項各号に定められている者は現行法上、必ずしも、分身ロボットを利用して国内で活動することが禁止されていない。そこで、同条の趣旨を実現するためには、同条1項各号に該当する場合に上陸拒否だけではなく、分身ロボットを利用して国内で活動することも禁止する立法論があり得るだろう。
第4 居住概念の再検討
外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という)は居住者概念を重視している。例えば、「居住」者から非「居住」者への技術提供を規制している(外為法25条20)。例えば、日本居住者の甲が、乙、丙及び丁に規制対象の技術情報を提供する事例を考えよう。そして、乙は、日本に物理的に所在し、勤務はしていないものの長期間(6ヶ月以上。以下同じ)生活しているA国籍者としよう。また、丙は、A国に物理的に存在するものの、分身ロボットを使って日本の例えば東京にあるカフェで勤務しているA国籍者としよう。さらに、丁は、勤務はしていないものの日本で長期間分身ロボットを使って生活するA国籍者としよう。この3人の間でどのような相違が生じるのか、現行法に沿って検討していこう。
通達21によると、外国人(A国籍者)の場合、原則として非居住者として取り扱うとした上で、(イ)本邦内にある事務所に勤務する者及び(ロ)本邦に入国後6月以上経過するに至つた者を例外的に居住者として取り扱う22。
このような通達の内容をそのまま適用すると、乙は、「本邦に入国後6月以上経過するに至つた者」である。そこで甲が乙に技術を提供しても、居住者同士の技術提供であって、原則として外為法の規制対象ではない23。また、丙は「本邦内にある事務所に勤務する者」として、居住者となる。そこで甲が丙に技術を提供しても、居住者同士の技術提供であって、原則として外為法の規制対象ではない24。しかし、丁は「本邦内にある事務所に勤務する者」でもなければ「入国後6月以上経過するに至」っていない。そこで、甲が丁に対して技術情報を提供することは、外為法の規制対象になり得る。しかし、丁の生活実態は乙や丙とほぼ変わらない。丁と乙との差異はロボットCAを通じて日本で生活するか、物理的に日本にいるかだけである。また、丁と丙との差異は「本邦内にある事務所に勤務する」かだけである。それにもかかわらず、現在の外為法の解釈を前提とすると、上記のような差異が生じるのである。
CA社会においてはこのような取り扱いの不平等が問題となることから、「居住」概念についても再検討が迫られるだろう。
第5 法の国際適用
1 はじめに
南澤は「ロボットのアバターを海外から遠隔操作して日本に入国する場合、肉体は入国していないが、アバター越しに犯罪行為もできてしまう」25と問題提起する。そこで、以下、不法行為及び犯罪行為を例に、ロボットCAと法の国際的適用について検討しよう。
2 国際不法行為
まず、不法行為について見ると、原則として結果発生地の法が適用され、例外的にその地に結果が発生することが通常予見できなければ行為地の法が適用される(法適用通則法17条26)。
例えば、物理的にはA国にいる甲が、分身ロボットを利用して日本にいる乙に怪我をさせた場合、結果は明らかに日本で発生しているところ、分身ロボットが日本に存在すること自体は甲も理解していると思われるので、「結果が発生することが通常予見できな」いとは言えず、原則どおり日本法が適用されるだろう。また、その甲が日本に置いた分身ロボットを壊されたという場合も、その分身ロボットが日本で破壊されている以上、日本が結果発生地と理解されるのではないか。もちろん、甲の居住するA国が損害発生地だという解釈もあり得るものの、その場合には、日本に存在するロボットを壊したことによって、A国で損害が発生することを「通常予見することのできない」とされる可能性はあるだろう27。
3 国際犯罪
刑法1条1項は、「日本国内において罪を犯したすべての者」を刑法の適用対象とする。A国に居住し、引き続き物理的にA国に存在する甲が日本に分身ロボットを持ち込んで日本を旅していたところ、犯人がその分身ロボットを壊したとなれば、器物損壊行為は日本で行われたとして、日本の刑法が適用される。
では、甲が逆に、分身ロボットを利用して、他人を殴る(暴行罪、208条)等、日本国内で犯罪を犯したらどうか。この場合、「構成要件該当事実の一部」が日本で生じれば、犯罪の場所が日本とされ、日本法が適用される28。確かに、暴行したいと考えて、甲が遠隔操作をしているのはA国内においてである。しかし、実際に「暴行」が加えられ、構成要件該当事実が生じているのは日本である。よって、このような事案であれば、日本法の適用を肯定することができるだろう29。
第6 不法行為・製造物責任
1 不法行為
テレイグジスタンスと不法行為については既に研究が存在する30ものの、重要なのは慰謝料(民法710条31)の問題であろう。即ち、愛着のある自己と一体化する分身ロボットについては、それが壊された場合に、「同じロボットをもう一台買うための費用が賠償されればそれでいい」ではなく、ペット32と同様に、まさにその分身ロボットへの愛着等の精神的苦痛が生じたとして、慰謝料を認めるべきである。
2 製造物責任
なお、製造物責任については、既に季刊連載第2回33において消費者法の文脈で、ロボットCAはその物に価値があるので、「その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない」とする同法3条但書に立法論的な疑義が存在することを説明したところであるから、これを参照されたい。
第7 刑法
刑法との関係では、分身ロボットに対する危害について、それを「器物損壊罪」(刑法261条)と見て良いのかが問題となる。もちろん物理的には分身ロボットは「物」なのだろうが、それは少なくとも心情的には被害者自身と一体化している。そのような特殊な「物」については、立法論として、身体と同様の保護や、動物と同様の保護をすべきではないだろうか。
なお、現行法では器物損壊罪の法定刑は「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料」であるところ、相対的には刑が軽いと評さざるを得ない。ここで、身体と同様に保護する場合、傷害罪の法定刑は「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」(刑法204条)であるし、愛護動物と同様に保護する場合、「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた」場合の法定刑は「五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金」(動物の愛護及び管理に関する法律44条1項)である。
なお、その人が殺されてもいい人だ等と表明する趣旨でその人の利用する分身ロボットを壊すことを通じて、被害者の名誉感情を侵害することはできる。しかし、名誉毀損罪・侮辱罪は社会的評価(外部的名誉)を保護しており、名誉感情を保護していない34。そもそも名誉毀損罪でも「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」(刑法230条)と、器物損壊罪よりもわずかに刑が重くなるにとどまり、令和4年改正による法定刑引き上げ後も侮辱罪の法定刑は「一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」(231条)と、器物損壊罪よりも刑が軽くなる。そこで、分身ロボットの破壊をもって名誉毀損罪・侮辱罪が成立したとみなすことのできる場合は少なく、かつ、その議論の実益もあまり大きくはないだろう。
第8 就労
1 OriHimeを利用した就労の2つの問題
分身ロボットを利用した就労として、障害者雇用その他の就労が考えられる。ここで、OriHimeを利用した就労には以下の2つの問題が指摘される。
1つ目は、障害者雇用に関するルールの不合理性である。即ち、確かに一部、OriHimeを利用することでフルタイムで勤務することができるという人も存在するものの、OriHimeを利用してOriHimeカフェ等で勤務する人の典型例は、まさに、これまでは仕事をすることは不可能と思われていた寝たきりの人等である。そこで、少なくとも最初からフルタイムでの勤務は難しいことも多い。そして、このような場合、障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」という)上、障害者を雇用したとして雇用率の算定対象とならないことが問題となった。このため、令和6年4月からは、週所定労働時間10時間以上20時間未満で働く重度の身体・知的障害者、精神障害者の算定特例(障害者雇用促進法69条以下)が適用されるようになり、その結果として、分身ロボットを通じて週10時間以上働くことができる人の就労が推進されることになる。しかし、週10時間未満から働き始めたいという人もいるところ、その場合に同法が適用されないことは重要な課題である。また、そもそもOriHime を利用する場合、単なるテレワークと異なり、現場でロボットの管理を行う人が必要であるから、通常よりも受け入れる企業側としてハードルは高まる。受け入れる企業として分身ロボット就労者の受け入れは、大変な反面、フルタイム就労が難しいので、障害者雇用促進法上はあまり評価されない、となると、分身ロボットによる障害者の就労が促進されない。そこで、そのような部分をいかに適切に加味するかは立法論として重要な課題となるだろう35。
2つ目は、寝たきりの人等は重度訪問介護制度を利用していることが多いところ、このような人がOriHimeで新たに就労できるようになると、この重要な重度訪問介護制度を就労中に利用することができなくなる点が問題として指摘される。OriHimeの利用によって、確かに就労自体はできるようになるのかもしれないが、実際には就労中においても、介護者による様々な支援が必要である36。このような状況の就労者に対する一定の支援制度は存在するものの37、現行制度には大きな不足がある。
2 ロボットを利用して就労する権利
さらに、OriHimeに限らず、ロボットを利用して就労する権利が問題となるかもしれない。例えば、私傷病で重傷を負った労働者が、休職後に復職を希望する際、実務では、例えば、片山組事件38に倣って、「現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が完全にはできないとしても、その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における 労働者の配置・移動の実情及び難易等に照らして、当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供をすることができ、かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供がある」という考え方から、他の業務として何が配置される現実的可能性があるかを検討してきた。
今後、ロボット就労が一般化すると、例えば、「確かに自分はロボットなしでは就労できないものの、当該企業においてロボット就労を行う業務は『配置される現実的可能性がある』業務であり、それであれば提供可能だ」という主張が出てくるかもしれない。このような主張をどのように受け止めるかについては、現実にそのような主張をする者が出てきた段階になってから、あわてて検討をするのではなく、現時点から検討を開始すべきである。
第9 サイボーグ
1 実は身近な「サイボーグ法」
筆者はサイボーグである。こう述べると、読者の皆様は「筆者が狂ってしまったのではないか?」と思われるのかもしれない。しかし、視力が弱く、眼鏡を手放せない筆者は、まさに眼鏡という能力拡張技術を通じた、能力拡張がなされてはじめて社会生活を送ることができる。このように、サイボーグの問題は実は極めて身近な重要な法律問題である39。
2 サイボーグ刑法
例えば6本目の指や3番目の手といった能力拡張デバイスを破壊した場合、傷害罪(204条)となるか。これらの能力拡張デバイスを破壊しても、被害者に痛覚が伝わらないのであれば、身体の完全性説からは傷害罪だが、生理的機能侵害説からは傷害罪ではないとされる40。この点は、既に痛みを感じる義手が開発されている41。そこで、そのような痛みを感じさせるデバイスが利用されていれば、生理的機能を侵害したと評価できる可能性が全くないとは言えない42。とはいえ、なぜ痛みを感じさせることが検討されているかと言えば、その能力拡張デバイスが壊れる危険がある物理力を受けている状況を察知できるようにすることが、その重要な目的の一つである。そうであれば、伝達するものを「痛覚」としなくても、何らかの方法でそのデバイスが物理力を受けていることが分かればいいという判断もあり得る。例えば、デバイスが物理力を受けた場合に、痛みの代わりに特定の波長の光を伝えるという場合において、それを生理的機能の侵害と言えるかは引き続き問題となる。
もし、そのような能力拡張デバイスを身体の一部だと解する場合、物理的に離れれば財物、一体となれば身体とされる43。しかし、例えば複数人で同じ身体拡張ロボット(例えば3本目の手)を共有する場合において、ある人と完全に一体化させると、取り外しが面倒である。そこで、3番目の腕のようなものについて、ドローン技術等を利用して、今はAさんの身体から5ミリ離れたところで活動するが、必要となればすぐBさんの身体から5ミリ離れたところで活動するといった状況も想定できるだろう。物理的に少しでも空間があれば、それだけで「一体化」してないと評価されるのか、それとも機能的に一体化していれば身体なのか等は引き続き検討すべき課題だろう44。
3 サイボーグ民法
身体拡張ロボットが他人を傷つけた場合の不法行為責任(民法709条)においては、なぜそのような事態が発生したかが問題となる。例えば、腕の特定の筋肉を動かす信号を読んで6本目の指を動かすところ、その6本目の指が他人を傷つけたという場合、その筋肉の動かす信号の読み方のミス45なのか、それとも、本当にそのような指令を出したのか(装着者の故意不法行為)は問題となる。このような点について立証責任を負う被害者が証明できないが故に敗訴してしまわないよう、①強制保険、②立証責任の転換、及び③記録義務等を検討すべきである46。
4 サイボーグ憲法
自己決定(憲法13条)との関係では、身体能力拡張ロボットを利用する権利が問題となる。この点は、弊害がなければ利用を認めることで問題はないと思われるものの、例えば身体的侵襲を伴う手術が必要な場合に、拡張される能力の内容によって公序良俗に違反するから承諾は無効として、手術する医師が傷害罪(民法204条)とされたり47、そもそも、医師の手によらない能力拡張ロボットとの接続が、医師法17条を理由として禁止されたりする可能性もある48。このような場合、自己決定権との関係でこのような行為を禁止する法令が違憲となる可能性がある。
また、平等原則(憲法14条)の関係で、能力を拡張した人としていない人の間の平等が問題となる49。例えば、能力拡張デバイスを接続することが一般化し、高価な、ハイグレードの能力拡張デバイスを利用できるか否かで様々な不平等が生じる事態は容易に想定し得る。例えば、国立大学の医学部に合格する上で、1,000万円かかる手術用の3番目の腕を利用することが事実上必須だ、となれば、「生身の身体による能力をもって評価すべきであって、能力拡張後の能力をもって評価することは不平等」といった議論はあり得る。そのような状況においては、(障害者雇用促進法に類似した、)身体拡張ロボットを持っていない人を一定割合で雇用することを義務付けるような動きが生じたり、生活保護(憲法25条)の支給対象に一定の能力拡張デバイス購入費用が含まれたりする時代も到来するかもしれない。なお、私人間においては、能力を拡張したことを理由とする解雇50等が問題となり得る。
その他、サイボーグ技術が駆動するために読み取られる情報の保護や、視力を拡張して服を透かして見える能力を実現する等のプライバシーの問題、身体を機械に置き換えていった場合の人間の尊厳や人権共有主体性の問題等、多数の憲法問題が発生し得る。
第10 おわりに
本稿をもって、2024年5月から2025年2月までの第一期季刊連載が終了する。それぞれ約1万字という紙幅の制限から、言い尽くせていない部分もあるものの、AITuber(季刊連載第1回)、消費者法(季刊連載第2回)、労働法(季刊連載第3回)及び今回のロボット(季刊連載第4回)と、2023年からの13回にわたる月刊連載に含まれない内容を補充することができたと考えている。また、関係者のご好意で第二期季刊連載を行えることになった。第二期においては、CA認証等の将来のCA社会において「基盤」となると思われる技術に伴う法的課題について、研究を深めていきたい。今後も、筆者のアバター研究をご期待頂きたい。
◇◆◇
本研究は、JSTムーンショット型研究開発事業、JPMJMS2215の支援を受けたものである。本稿を作成する過程では慶應義塾大学新保史生教授、情報通信総合研究所栗原佑介主任研究員及び酒井基樹弁護士に貴重な助言を頂戴し、また、早稲田大学杜雪雯助手に脚注整理等をして頂いた。加えて、T&S編集部には詳細な校閲を頂いた。ここに感謝の意を表する。
- 内閣府「ムーンショット目標1―2050年までに、人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現―」<https://www8.cao. go.jp/cstp/moonshot/sub1.html>(2025年2月4日最終閲覧、以下同じ)
- 厚生労働省「ICTや分身ロボットを活用した『社会参加』の実現を目指す社会実験の視察」<https://www.mhlw.go.jp/photo/2019/10/ph1018-03.html>
- 松尾剛行「季刊連載第3回〜CAと労働法」InfoCom T&S world trend report 428号(2024)20頁 <https://www.icr.co.jp/newsletter/wtr 4 28-20241129-keiomatsuo.html>
- ロボットをメンテナンスするロボット等も考えられるが、メンテナンスロボットの故障への対応等を考えると、人間の必要性はゼロにはならないだろう。
- 草下健夫「体は機械で拡張できる!? 『第6の指』独立に動かすことに成功 電通大」Science Portal(2022年3月15日)<https:// scienceportal.jst.go.jp/gateway/clip/20220315_g01/>
- 岩田浩康「【『特集 Feature』16-2 人の機能を拡張せよ!人間支援ロボットテクノロジー2回目配信】身体装着型ロボット『第3の腕』」早稲田大学(2017年7月26日)<https:// www.waseda.jp/top/news/52266>
- 稲見昌彦「64歳で逝去『人類初サイボーグ』が世界に遺した物」東洋経済Online(2022年7月6日)<https://toyokeizai.net/articles/-/601582>
- 「両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。」
- 衆議院憲法審査会「憲法第56条第1項の『出席』の概念について」(2022年3月3日)<https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/2080303haihusiryou.pdf/$File/2080303haihusiryou.pdf>。その他、東京大学法学部「現代と法」委員会『いま、法学を知りたい君へ -- 世界をひろげる13講』(有斐閣、2024)[宍戸常寿]等も参照。
- 衆議院憲法審査会事務局「『国会におけるオンライン審議の導入』に関する資料」(2022年2月)<https://www.shugiin.go.jp/internet/itd b_kenpou.nsf/html/kenpou/shukenshi097.pdf/$File/shukenshi097.pdf>14-15頁
- 「証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、十万円以下の過料に処する。」
- 「裁判所は、次に掲げる場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。
一 証人が遠隔の地に居住するとき。
二 事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人との関係その他の事情により、証人が裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるとき。」 - 「裁判所は、次に掲げる場合であって、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。
一 証人の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、証人が受訴裁判所に出頭することが困難であると認める場合
二 事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人との関係その他の事情により、証人が裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合
三 当事者に異議がない場合」 - 但し、Web期日においては、裁判官の顔を正面から見ても違和感がないので、裁判官の顔をよく見ることができ、その心証を予想しやすくなった、という声もある。そうすると、Web会議形態の尋問であれば、裁判官としてモニター上に映る証人の顔を見つめて心証を取ることがしやすいが、ロボット出頭尋問であれば目の前にロボットの顔があることでそれが阻害される、という可能性はあるかもしれない。
- 新保史生「アバターによる講義は対面授業か?」おかしら日記(2022年6月14日)
<https://www.sfc.keio.ac.jp/magazine/016386.html > - デジタル臨時行政調査会「デジタル原則に照らした 規制の一括見直しプラン」(2022年6月3日)<https://www.digital.go.jp/assets/ contents/node/basic_page/field_ref_resources/34a225ed-03be-4408-b00d-f9b88a5a254 3/7f6adee4/20230314_policies_digital-extra ordinary-administrative-research-committee_ outline_01.pdf>
- 南澤孝太「『もう1つの身体』での活動を通じて制約から解放され生きられる社会へ」ムーンショット型研究開発事業@JST(2023年12月15日)<https://note-moonshot.jst.go.jp/ n/n2376381da314#90778d95-290d-4798-a494-4b030a7fa6fa>
- 坂中英徳=斎藤利男『出入国管理及び難民認定法逐条解説』(日本加除出版、改訂第四版、2012)3頁。
- そして最近は一部地域における「オーバーツーリズム」が問題視されているところ、このようなロボット観光はオーバーツーリズム対策にもなるといったメリットもあるだろう。
- 1項「国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術(以下『特定技術』という。)を特定の外国(以下『特定国』という。)において提供することを目的とする取引を行おうとする居住者若しくは非居住者又は特定技術を特定国の非居住者に提供することを目的とする取引を行おうとする居住者は、政令で定めるところにより、当該取引について、経済産業大臣の許可を受けなければならない。」但し「みなし輸出」管理がされており、居住者への機微技術提供であっても当該居住者が、非居住者へ技術情報を提供する取引と事実上同一と考えられるほどに当該非居住者から強い影響を受けている状態(特定類型)に該当する場合には、「みなし輸出」管理の対象である。
- 外国為替法令の解釈及び運用について(昭和55年11月29日付蔵国第4672号)
- 但し、いわゆる「例外の例外」として、(イ)外国政府又は国際機関の公務を帯びる者及び(ロ)外交官又は領事官及びこれらの随員又は使用人(ただし、外国において任命又は雇用された者に限る)はなお、非居住者として取り扱うとされる。
- なお、注20で述べた「みなし輸出」管理の問題はなお生じ得る。この点は丙についても同様である。
- なお、注20で述べた「みなし輸出」管理の問題はなお生じ得る。
- 南澤・前掲注17)。
- 「不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、加害行為の結果が発生した地の法による。ただし、その地における結果の発生が通常予見することのできないものであったときは、加害行為が行われた地の法による。」
- しかし、将来の空間的な障壁が消滅するCA社会ではその程度は当然に予見できるようになるかもしれない。
- 山口厚『刑法総論』(有斐閣、第3版、2016)416頁。
- この点は著作権侵害について現在議論が進んでいる<https://www.bunka.go.jp/seisaku/ bunkashingikai/chosakuken/workingteam/r06_01/pdf/94080501_03.pdf >
- 赤坂亮太「テレイグジスタンスの提供に伴う不法行為責任の検討」情報ネットワーク・ローレビュー12巻(2013)1-20頁。
- 「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」
- 渋谷寛『ペット訴訟ハンドブック:関係法・判例解説、交通事故、動物病院、飼い主が加害者となる場合、ペットショップ、ペットホテル、トリミングショップ、ペットをめぐる近隣トラブル』(日本加除出版、2020)75頁。
- 松尾剛行「季刊連載第2回〜CAと消費者法」InfoCom T&S world trend report 425号(2024)23頁<https://www.icr.co.jp/news letter/wtr425-20240829-keiomatsuo.html>
- 松尾剛行=山田悠一郎『最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務』(勁草書房、第2版、2019)21頁。
- つくば市株式会社オリィ研究所「分身ロボットに係る障碍者雇用率の算定の特例」(2023年6月23日)<https://www.chisou. go.jp/tiiki/kokusentoc_wg/r5/pdf/20230623_shiryou_s_1_1.pdf >
- 厚生労働省「厚生労働省 令和元年度障害者総合福祉推進事業 重度障害者の在宅就業に関する調査研究 報告書」<https://www. mhlw.go.jp/content/12200000/000654254.pdf>
- 厚生労働省「重度障害者等に対する通勤や職場等における支援について」<https:// www.mhlw.go.jp/content/001073876.pdf>
- 最判平成10年4月9日労判736号15頁。
- なお、いわゆる「ロボット技術」を利用した能力拡張のみを「サイボーグ」と呼ぶことが多いが、本文ではそのような狭義のサイボーグにとどまらず、広い意味での物理的な能力拡張技術をサイボーグ(技術)として検討の対象としている。
- 小名木明宏「科学技術時代と刑法のあり方:サイボーグ刑法の提唱」北法63巻5号(2013)521頁。
- MATT SIMON(ASUKA KAWANABE訳)「『義肢に痛覚を与える』という奇妙な研究は、わたしたちに何をもたらすか?」WIRED(2018年7月8日)<https://wired.jp/2018/07/08/ making-bionic-arms-feel-pain/>
- 胸部に疼痛が残るような打撲について傷害罪を認めた最決昭和32年4月23日刑集11巻4号1393頁。但し、一瞬のみ痛みを感じそれで終わりだ、という場合には少なくともこの決定の射程にはないと思われる。
- 小名木・前掲注40)517頁。
- 但し、機能的一体性を貫くと、理論的には物理的に1,000キロ離れても「身体」ということになりかねないが、それでは従来の解釈と相当乖離が生じてしまうことが課題だろう。
- 身体拡張ロボット提供者に過失があれば不法行為責任(709条)を負い得る。また、欠陥があれば、製造物責任を追い得る。
- なお、自動運転について作動状態記録を義務付ける道路運送車両法第41条第2項も参照。
- 小名木明宏「人体と機械の融合に伴う法律問題についての研究:科学技術と刑法の調和」北法70巻5号(2020)1-16頁。
- 但し、タトュー事件最決(最決令和2年9月16日刑集第74巻6号581頁)を参照のこと。
- 藤原幸一ほか「埋込サイボーグ技術の社会実装に係る技術・社会的課題」人工知能36巻6号(2021)674頁以下。
- 吉野次郎「頭にアンテナ結合、職場クビに サイボーグ共生険しき道」日経ビジネス(2024年2月9日)<https://www.nikkei.com/article/ DGXZQOUC072FZ0X00C24A2000000/>
※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部抜粋して公開しているものです。
当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。
調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。
ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード
松尾 剛行の記事
関連記事
-
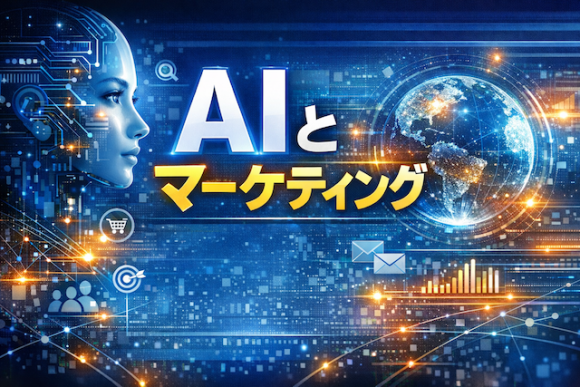
AIとマーケティング
- AI・人工知能
- ICR Insight
- WTR No442(2026年2月号)
- 生成AI
-

ICTが変える授業の形 ~複線型授業とICT
- GIGAスクール構想
- ICT利活用
- WTR No442(2026年2月号)
- 教育
- 日本
-

世界の街角から:真夏の海に浮かぶ"立体都市" ~長崎・軍艦島、半世紀後の生活の輪郭
- WTR No442(2026年2月号)
- 世界の街角から
- 日本
-

ソブリンAIを巡る各国の動向 ~制度・投資・地域連携に見る多様なアプローチ~
- AI・人工知能
- WTR No442(2026年2月号)
- 生成AI
-

超高齢社会における介護DXの可能性と課題
- DX(デジタルトランスフォーメーション)
- WTR No442(2026年2月号)
- 介護
- 医療
- 日本
- 福祉
InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧
ランキング
- 最新
- 週間
- 月間
- 総合





