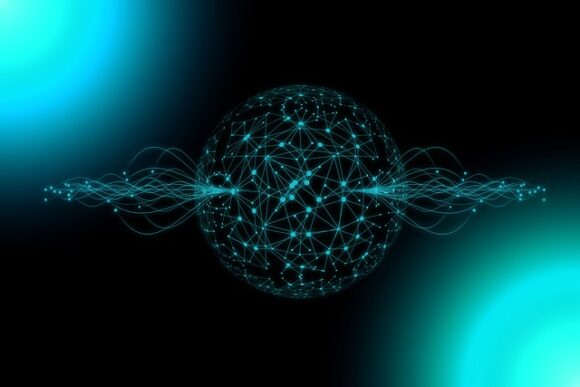11月2日に、この風見鶏に“火山「噴火速報」の運用と携帯通信環境のギャップは携帯事業者の努力不足のせい?”と題して、気象庁の火山噴火予知連絡会・火山情報の提供に関する検討会の報告(平成27年3月)に関して、携帯通信のエリアカバーの問題が事業者の不備、努力不足として語られてしまうことに疑問を感じ、小論を掲載しました。その直後に、私の小論に対して読者である携帯通信事業者の関係の方から、そもそも噴火速報による避難・被災回避の効果への疑問から、緊急地震速報に類似したエリアメールの取り扱いは携帯通信事業者各社とは合意形成に到っていない旨の御意見を頂きました。
そこで私の不勉強の反省の意味も込めて、もう一度この問題を掘り下げて考えてみたいと思い、今月2回目の掲載となりました。そもそも火山の噴火速報は噴火という現象発生直後に発せられるもので、地震発生直後の揺れに備えるための予報である緊急地震速報とは通報の位置づけが異なることは想定できます。既に噴火が起った直後の速報なので火山の火口現場では十分な回避はほぼ不可能です。本来そのような火山噴火のおそれがある火山には立ち入らないことが何より重要で、噴火警報レベルの取り扱いが最大のポイントであることは言うまでもありません。従って、火山の火口付近の登山者等の安全確保に対して噴火速報が避難や被災回避に効果があるかどうかはさらに検討・評価が待たれるところです。
地震発生時のように広範囲の地震の揺れに短い間に備えるために緊急地震速報をエリアメールとして一斉同報で携帯端末に送信しているのとは似ていますが、やはり違いが存在します。しかし一方で噴火直後の速報であっても、噴火の規模や態様によっては緊急の避難や被災回避行動を促す効果も期待できるとの見方があります。結局、こうした理解の差から今回の検討会による「火山情報の提供に関する報告(平成27年3月)」では、“登山者等に向けた情報については、携帯端末の活用を意識した情報内容とするとともに、具体的な伝達方法について関係する事業者と調整する。”との表現に止まっています。私は前回の小論(11月2日掲載)では、この点に十分に触れずにいた上、また単純に緊急地震速報と類似の扱いとしてエリアメールに言及しましたが、前述のとおり、この背景には気象庁当局と携帯通信事業者の間に認識の違いがあり、またまだ合意には到っていないこともまた事実です。
ただ私は噴火速報を発表する以上、速報として登山者に伝え(もちろん登山者自身には火山の噴火は現場では当然すぐに分かりますが)、緊急の避難を直ちに促す効果が期待できるので速報の効果があると思っています。命を守るための方策なので、できることはトライしてもよいと考えていますが、問題はその手間とコスト負担にあります。こうした緊急の命を守るための負担は公共性の最たるものなので、国家の施策として一定の水準が確保されるべきものです。これを民間企業である携帯通信事業者の負担のまま推進することは決して許されるものではありません。協力要請によって、国の施策(費用)や民間事業者のあり方の本質論が解決するものではありません。今回の検討会報告の問題はそこにあると考えます。エリアメールの有効性の評価ばかりでなく、仮りに有効であるとして、携帯通信のエリアカバーの実態がどうなっていて、どの技術でどの位の費用がかかるのか、それを誰が負担するのが適当なのかなどの議論を掘り下げずに“具体的な伝達方法について関係する事業者と調整する”とだけしか記載していないことが誠に残念でなりません。
噴火速報の登山者等への周知方法の検討は始まったばかりです。携帯端末やエリアメールの効用もやはりあると思います。今後の整備方向に当たって、手間とコストの負担について国の政策(費用)として取り組む時期だと思っています。安心・安全、国土強靭化の一貫として政策当局の施策が進展することを願って止みません。
今回、携帯通信事業者の関係の方から貴重な御指摘と御意見を頂きましたことに感謝致します。
調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。
ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード
平田 正之の記事
関連記事
-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上
- WTR No441(2026年1月号)
- ヘルスケア・医療
- 日本
-

中国におけるロボット産業の進展
- WTR No441(2026年1月号)
- ロボット
- 中国
-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜
- WTR No441(2026年1月号)
- ポイントビジネス
- 日本
- 経済
- 金融
-
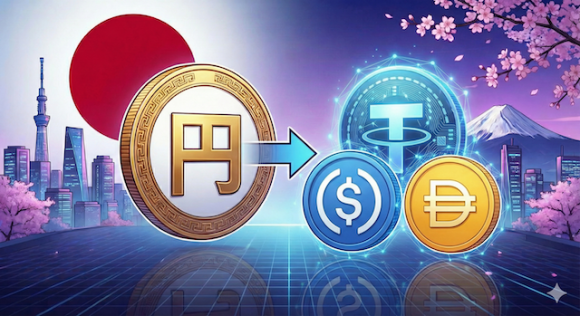
「信頼」と「ポイント文化」が融合する: 日本型ステーブルコインが描く資金決済の未来
- WTR No440(2025年12月号)
- 暗号通貨
-

眠れる資産から始まる未来 ~循環価値の再発見
- ICR Insight
- WTR No438(2025年10月号)
- 日本
- 環境
ITトレンド全般 年月別レポート一覧
ランキング
- 最新
- 週間
- 月間
- 総合