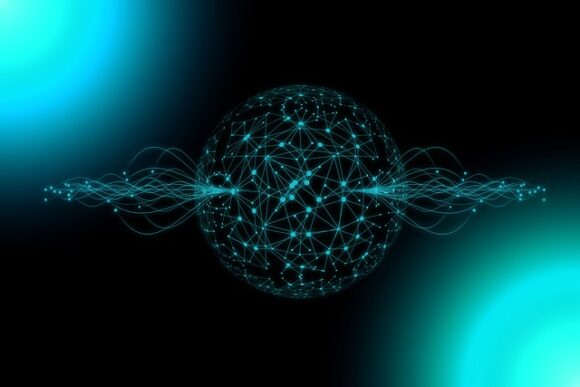会社法制の見直しが法務省の法制審議会 会社法制(企業統治等関係)部会で本年4月から始まっています。これは2015年5月に施行された現行の会社法附則第25条に「政府は、この法律の施行後2年を経過した場合において、社外取締役の選任状況その他の社会経済情勢の変化等を勘案し、企業統治に係る制度の在り方について検討を加え、(中略)社外取締役を置くことの義務付け等所要の措置を講ずるものとする。」とあり、これを受けて本年2月9日開催の法制審議会に法務大臣から会社法制(企業統治等関係)の見直しに関し諮問されたものです。会社法制部会(座長:神田秀樹 学習院大学法科大学院教授)では、4月26日の第1回開催を皮切りに月1回のペースで検討が進んでいます。10月からは論点の第2読会が始まっていますので、来年2月の中間試案、3月の取りまとめ・パブリックコメント募集に向けて集中的な議論が予定されています。
今回の企業統治等に関する会社法制部会の主な検討課題は、1.株主総会に関する手続の合理化、2.役員に適切なインセンティブを付与するための規律の整備、3.社債管理の在り方の見直し、4.社外取締役を置くことの義務付け、と整理されています。この中でICTに関係するものとしては、1のうちの「株主総会資料の電子提供制度の新設」があり、株主総会資料をインターネットを利用して提供するための制度を新設しようとするものです。本件は「日本再興戦略2016」で取り上げられていて、具体的な措置内容等を検討するとされています。これまでICTによる変化に消極的と見られていた株主総会運営に関し前向きな取り組みの一歩と捉えてよいと思います。主な狙いは株主総会資料の早期提供や充実を行って株主との間のコミュニケーションの質向上を図ることにあり、ICT利活用の本筋の方策と言えるものです。
また、3の社債管理の在り方の見直しは資本市場制度の領域で企業金融の基本問題です。企業統治とは直接の関連性は乏しいのでここでは取り上げませんが、筆者が長年携わってきた分野なので社債管理制度の充実の方向を評価しています。
やはり今回の会社法制、特に企業統治関係の見直しでポイントとなるのは2と4で、まとめると取締役および取締役会の活性化を進め、取締役がガバナンスのうえで中核的役割を果たすための仕組み作りということになると思います。取締役会における多様な見識と意見、活発で自由な論議、迅速で規律ある判断と決定こそ機能強化につながるものです。企業統治の規律の見直しでは、しばしば普遍的に言われている経営と執行の分離の重要性を認めるところですが、欧米とは違って取締役会メンバーのうち社外取締役を除く取締役は全員が担当・所管を持つ執行部なので、直ちに経営と執行とを分ける方向に舵を取ることは現実的な方策ではありません。特に株式会社では圧倒的な中堅・中小企業・非上場企業、さらに上場企業のうちで多数を占める監査役会設置会社(東証1部上場 2,020社中1,516社で75%)では現実問題として独立社外取締役の適材を確保することは難しく、多くの人数を求めることには無理があります。東京証券取引所のソフトローであるコーポレートガバナンスコードでは独立社外取締役2名以上の選任を求めていて、その割合は年々上昇して67.8%(東証1部 2017年7月現在)まで達していることは評価できます。大手上場会社なら会社法上の義務付けも大きな混乱なく進められそうです。問題は対象とする会社規模等の線引きにあります。当面は大会社に限定しないと混乱は避けられそうにありません。
最後に私は企業統治に関する規律の議論となると、どうしても社外取締役の義務付けを含めて配置の問題となりがちなことが気になって仕方がありません。欧米流の経営と執行の分離論からすると独立社外取締役の一定割合の配置は当然の帰結であり、監査を含めて取締役会メンバーとして経営の評価・判断を行う委員会設置会社方式こそ、正当なガバナンスであり、コンプライアンス機能を果たす統治機構となることは十分に理解できます。しかし、これには重要な前提条件があることを忘れてはいけないと思います。それは自由で健全な労働市場、特に会社経営を担う経営人材の市場が存在することが不可欠であるということです。日本では専門職など特定のスキルを持つ労働者(人材)の流動性は近年高まっていて、マッチングを業とする企業も多数存在して市場形成が進展していますが、経営層となるとまだ十分とはとても言えません。上場会社でも取締役になる人材は非執行の社外取締役を除いて社内の執行に当たる職責を有する人達に頼らざるを得ません。ましてや社長・CEO・CFOなどの経営層の市場はほとんど認識されていない実状にあります。典型的な事例が日本企業でも国際的に通用する外国人社長・CEOなどには国際的な価値(相場)観から多額の報酬が容認される一方で、社内出身の日本人の社長や取締役には国内的な横並びが強く意識されていることです。
優秀な取締役(社内・社外とも)に積極的で活発な活動を促すためには、インセンティブとして役員報酬の多様化と同時に、活動に伴うリスクに対し適正に補償する仕組みの確保という両面の規律の整備が必要であることは当然のことです。株主代表訴訟を含めて取締役の責任を過重すると、取締役会の活動や判断が低下・畏縮してしまい、企業統治規律の在り方の見直しが逆効果となってしまいかねません。報酬インセンティブの促進と責任追及を受けた際に要した費用等の補償とのバランスを適正に確保することが社外取締役を含めて経営層人材の流動性を高めることになり、我が国の産業活動の活性化、さらには事業構造の転換やM&Aなど中長期の成長戦略の議論・策定に貢献することでしょう。
取締役および取締役会の活性化は日本の企業社会全体に突き付けられた課題であると同時に、個別の企業の取締役および取締役会にとっては将来の自身の存続に係る重大事であると捉えて活性化に努める必要があります。会社法上、監査役設置会社の取締役には固有の権限の定めがなく、取締役会に出席して意見を表明し決議に参加することがその権限なのです。一方、責任としては利益相反行為など厳しく追及されますので、取締役会の運営に積極的に臨んで経営判断原則に従って行動することが必須です。その意味で上場会社で大半を占めている監査役設置会社でも監査等委員会設置会社と同様の範囲で重要な業務執行の決定を一定の取締役に委任して、取締役会の決議事項を軽減することができるようにする方向はよいことです。取締役会の事務的負担を減らして戦略的議題に時間を充てるべきだからです。
我が国の会社法上の定めでは企業統治に関する機関設計は株主総会決議に委ねられていて会社(株主)自治が貫かれていますが、他方で会社制度における取締役会の機能・役割を法制上も社会・経済上も明確にすることなく今日に至ってしまっていることを改めて考えてみる必要がありそうです。それこそ取締役会の第一の課題です。
※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部無料で公開しているものです。
調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。
ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード
平田 正之の記事
関連記事
-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上
- WTR No441(2026年1月号)
- ヘルスケア・医療
- 日本
-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる
- WTR No441(2026年1月号)
- オーストラリア
- 世界の街角から
-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに
- 5G/6G
- AI・人工知能
- ICR Insight
- WTR No441(2026年1月号)
- モバイル通信事業者(国内)
- モバイル通信事業者(海外)
-

中国におけるロボット産業の進展
- WTR No441(2026年1月号)
- ロボット
- 中国
-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜
- WTR No441(2026年1月号)
- ポイントビジネス
- 日本
- 経済
- 金融