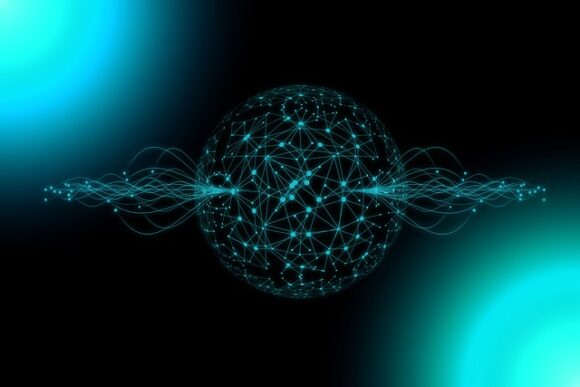5Gのユースケースを考える~バーティカル用途(異分野)産業との連携とスマホネイティブ世代の発想が必要

第5世代移動通信システム (5G) の実現による新たな市場創出に向けて、今年5月から5G総合実証試験が5GMF(第5世代モバイル推進フォーラム)の下で進められています。そこでは、NTTドコモ、NTTコミュニケーションズ、KDDI、ATR、ソフトバンク、NICTの6社・機関が実施主体となって6分野に分かれて、(1)高速・大容量通信(基地局あたり10Gbps超)、(2)超低遅延通信(無線区間1ms)、(3)多数同時接続(100万台/km2)という5Gの要求条件に沿った実証試験が行われています。
5GMFが提唱してきたとおり実証試験はパートナーとして、鉄道・バス、観光、警備保障、建設土木、スポーツ施設、トラック運送、物流・在庫管理、テレワークや遠隔医療に携わる事業者と連携して進められています。通信事業者はもっぱら利用者に通信サービスを提供するだけで、実際に提供されるサービスやアプリケーションは別物と扱ってきたこれまでのいわば技術先行型の開発とは一線を画す取り組みとなっています。10月4日には、CEATEC JAPAN 2017と併行して総務省主催で「5Gワークショップ2017」が幕張メッセで開催され、実証試験の模様がNTTドコモ、KDDI、ソフトバンクの3社から発表があり、注目を集めていました。昨今のICTを取り巻く大きな潮流のなか、今年のCEATECではB to Bの出展が主役になっていましたが、5Gの実証試験の取り組みでも、バーティカル用途(異分野)産業との連携が中心的テーマとなっていたことは大きな変化の先取りを感じました。
特に、5Gの特色として要求条件に加わった超低遅延と多数同時接続は、これまで産業的には開拓・活用されていない領域なので、建設機械の遠隔操作やトラックの隊列走行、ドローンやロボットのリアルタイム情報伝達・操作など新しい用途開発に期待が持てそうです。もちろん、高速・大容量通信の利用シーンはこれまでのサービスの延長線上にあるだけに、4K・8Kのより高精細映像コンテンツの配信や広域監視、さらには総合病院と地域診療所間の遠隔医療への応用実証が進められています。
これほどさまざまな分野で実証試験が進められているにもかかわらず、今年のCEATEC会場では5Gの展示や説明はほとんどなく、NTTグループのブースでも唯一5Gを意識した高品質パノラマVRがNTTドコモから展示されていたくらいでした。ブース脇で行われるセミナーでも30回のうち1回だけ「5Gの早期実現に向けたドコモの取り組み」と題して行われただけでした。また、KDDIのブースでも5Gを意識した(今回の会場ではWi-Fiを使用)テレイグジスタンスのデモ、すなわちオペレーターによるロボットの遠隔操作が行われていただけで、2社とも5Gそのものの出展はありませんでした。B to Bの潮流に乗っているといっても実証試験の段階であり、実機を展示してのサービスの説明が無理なので止むなしの印象でした。B to B主流のなかでは、現実の事業や業務のレベルで役立つ、使えるものでないとアピールできないことがよく分かるCEATECでした。
5Gと交替で今年の花形はAIとIoTであり、電機メーカー始め各社のブースではもっぱらAI搭載機器を用いたサービスと低コスト化著しいIoTの展示が主役となっていました。当然、1社だけの機器やサービスでは取り組めませんので、バーティカルな異業種との提携がここでも主流となっていて興味深く感じました。今年のCEATEC出展に対する主催者3団体の意図がB to Bシフトにあり、異分野やベンチャーの招聘にあることが明確に表れていました。しかし、私としてはモバイル通信サービスや無線技術のない展示会となるとやはり寂しさを感じました。
一方、今年9月に米国サンフランシスコではMWC Americas 2017と題して5Gに関する一大イベントが開催され、米国のモバイル通信会社を始め世界の情報通信機器ベンダーとチップベンダーが集まって大きな盛り上がりを見せていました。米国の5Gは、固定ブロードバンド回線を補完し高速・大容量通信を全米各地に普及することを狙いとする5G FWA (Fixed Wireless Access) なので、世界の流れであるモバイル通信サービスとは様子が違っていますが、世界が目指している2020年の5G商用化よりも一足早く実現する勢いとなっています。これも米国流の存在感を前面に押し出しての世界戦略なのでしょう。確かにアジアや欧米のモバイル先進国では、利用実態もネットワーク構造ももはや5Gを必要とする客観的情勢にありますが、多くの途上国ではモバイルの5G化よりもむしろブロードバンド回線の方に大きな需要があると想定できます。光回線の建設より手軽な5G FWAに力を入れる米国のしたたかさが窺われます。
周波数の標準化もまだなので、こうした米国での取り組みが直ちに世界のデファクトになる訳ではありませんが、いずれ5G FWAから本命のモバイルに発展してくることは自明なので、やはり米国の通信事業者の動き、特に推進母体となっているVerizonの動向は気に懸けておく必要がありそうです。米国の5G FWAでは既にスモールセルの配置や建設方法が話題になっていて、ミリ波利用の実用化フェーズが間近かと受け取れます。周波数利用の免許上の制約が少なく技術中立的に電波の利用が可能という国柄であり、かつ、もともと固定通信サービスとモバイル通信サービスの業務区分にとらわれない規制環境にあるので、ミリ波利用にも柔軟に対応できるものと思われます。
そこで今回のMWC Americasでテーマになっていたのが日本と同様に5Gのユースケースについてでした。いろいろなアイディアはあるものの結局のところスマートフォンによる映像サービス、それも動画とVRではないかというのが大勢の意見とのことです(本誌2017年11月号、弊社の中村邦明主任研究員のレポートに詳しく述べられています)。これこそスマホネイティブ世代の発想に立脚した現実的な解答なのかも知れません。このスマートフォンを利用した映像系の新サービスも米国の大手ネット企業 (OTT) の牙城となるような気がしてなりません。5G FWAを用いた新サービスにAIを搭載しビッグデータを組み合わせた活用が進めば、米国の大手ネット企業にはとうてい太刀打ちできそうにありません。やはりスマートフォンが5Gのユースケースの主役になることを今から覚悟しておいた方がよさそうです。
こうなると現在、我が国で進められている5G実証試験においても、これから通信各社が取り組む個別のサービス作りにあたっても、5G回線に加えてAI、IoT、ビッグデータ、センサーといったサービス要素をどのように組み合わせるのがよいのか、バーティカル用途(異分野)産業との連携に際しては、スマホネイティブ世代に属するベンチャーと積極的に提携する途が何より早道ではないかと思います。基地局設置(配置)を始め、モバイルインフラ作りもこうしたユースケースに応じて柔軟な対応が求められるからです。
※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部無料で公開しているものです。
調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。
ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード
平田 正之の記事
関連記事
-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上
- WTR No441(2026年1月号)
- ヘルスケア・医療
- 日本
-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる
- WTR No441(2026年1月号)
- オーストラリア
- 世界の街角から
-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに
- 5G/6G
- AI・人工知能
- ICR Insight
- WTR No441(2026年1月号)
- モバイル通信事業者(国内)
- モバイル通信事業者(海外)
-

中国におけるロボット産業の進展
- WTR No441(2026年1月号)
- ロボット
- 中国
-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜
- WTR No441(2026年1月号)
- ポイントビジネス
- 日本
- 経済
- 金融
5G/6G 年月別レポート一覧
ランキング
- 最新
- 週間
- 月間
- 総合