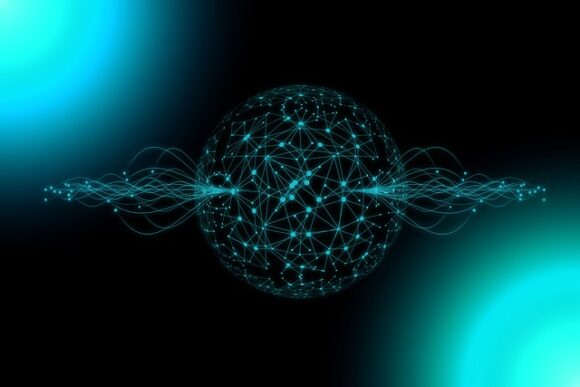5G商用サービス開始、モバイル通信インフラに 広がる課題

いよいよ5Gの商用サービスが始まります。昨年4月に開設計画の認定(周波数の割当)があり、既に昨年後半からはプレサービスが行われていますが、ようやく本格サービスとなるので期待が高まっています。周波数の割当を受けたNTTドコモ、KDDI/沖縄セルラー電話、ソフトバンク、楽天モバイルの4社は5Gサービス開始に向けて基地局の構築を進めています。総務省は5G開設計画の指標として、これまでの人口カバー率を評価することに代わって、全国への展開可能性の確保、地方での早期サービス開始、サービスの多様性の確保の3点を取り上げて評価し認定しました。つまり、5Gの普及拡大は人口の多いエリアよりむしろ、全国展開(5年以内に50%以上のメッシュで整備、2年以内に全都道府県でサービス開始)を優先する指標を取り入れています。5Gの普及過程では利用者数よりも、利用エリアの展開拡充を重視した施策と言えます。これは、既存のエリア整備が人口カバーで99.99%まで進んでいるので、5Gに新たに求められているのは産業利用を含めたサービスの多様化であり、工場や農地等の非居住エリアへの展開などDX(デジタルトランスフォーメーション)時代に不可欠なインフラということになります。
5Gは既に世界50カ国以上でサービスが開始されていて、契約数も韓国の500万をはじめ世界で1,300万超になっているので日本は遅れているとの指摘がよく見られます。しかし、5Gの本質を従来の4G/LTEの延長となる超高速性能だけでなく、超低遅延と多数同時接続という機能を加えて捉えておく必要があります。超高速性能だけでは結局料金プランの競争が中心となってしまい新サービスの開発とはなりません。5Gのサービス開発ではIoT、ビッグデータ、AIとの連繋が重要で、法人企業との連携(協創)によるDXなどリアルとバーチャルの両方に対応する必要があり、一般の個人向けサービス(B to C)よりも法人企業向けの取り組み(B to B to C)に力点を置いていることに注目すべきでしょう。サービス開始で先行した韓国や米国でもB to Cサービスでは新しい動き、キラーアプリケーションがまだ出てきていないことからそれがよく分かります。
5Gの性能の特徴に、超高速、超低遅延、多数同時接続の3点があることはよく知られているところですが、この性能発揮自体にも、さらに、これらを取り巻く技術や事業運営、事業者の組織構造にまで及ぶ新しい課題が突き付けられていることを以下に取り上げたいと思います。
- エリアカバーの整備拡充→基地局拡充計画の提示が必要
・産業利用と人口カバーの両面のバランス確保
・NSA(ノンスタンドアローン)とSA(スタンドアローン)のエリアの組み合わせ
・周波数サブ6とミリ波のすみ分けと組み合わせ
- ネットワーク機能の配置→AIの活用が急務
・ネットワークスライシング機能の配置方法
・エッジコンピューティングシステムの配備先
- 4Gバンドの5G化対応→2020年に制度整備
・早期の3Gサービスの終了; KDDI 2022年3月末
ソフトバンク 2024年1月下旬
NTTドコモ 2026年3月末
- ローカル5Gとの事業関係→コア網、アクセス網の提供方式
・接続と卸、受委託、運用支援、出資関係など
- 周波数共用への対応→電波資源の有効活用
・ダイナミック周波数共用システムの方向性
以上のとおり、5Gインフラの構築や5Gサービスの展開上の主な課題だけでも数多くあり、未知数の多い連立方程式を解くという難しさがあります。もちろん、これ以外にもセンサーIoTに適した低容量・省電力タイプのLPWA(Low Power Wide Area)への対応やコグニティブ無線技術、特にヘテロジニアス型の開発と端末の普及など技術面の課題はさらに多く存在します。加えて、5G時代にはICTシステムの社会基盤化がさらに進展するのでセキュリティが極めて重要になると誰もが認めるところですが、ウイルス対策に限らず、なりすましや詐欺などを未然に防止し、社会に安心・安全への信頼感を根付かせる取り組みが求められています。5G、IoT、ビッグデータ、AIが関係するイノベーションには新しい社会基盤となる「トラストサービス」が不可欠です。このトラストサービスの整備と普及こそ、5Gインフラの構築と同時並行的に進めておかないとIoTの展開もスマート社会も信頼を得られず、結局、日本は再度新しいイノベーションに乗り遅れてしまうことになりかねません。DX推進をサポートする立場にある通信事業者においても事業運営や組織構造まで含めて幅広い対応が求められています。特にIoTに関係するトラストサービスが世界的に未整備な現状にあるので、日本の関係事業者の前向きな取り組み・協力を期待しています。
最後に、5G商用サービスを前にして、日経新聞が昨年12月3日~5日の3回にわたり、有識者3人の「5Gが開く未来」と題する意見特集記事を掲載していましたので、それに触れて本稿を終わりたいと思います。とても意義深い特集でした。本文内容を私が解説することはとても出来ませんが、記事の見出しだけで5Gの意義が十分伝わってきますので取り上げてみます。次のとおりです。
IoTの革新 日本に好機(12/3) 国領二郎 慶大教授
「超スマート社会」実現へ(12/4) 坂口 啓 東工大教授
「何をするか」自ら創造せよ(12/5) 森川博之 東大教授
これらをまとめてみると、サイバー・フィジカルシステムの拡充こそが日本の強みである現場力をデータとして発揮できる絶好の機会となり得ると整理できます。特に、日本の5Gの普及見通しとして2025年度に約半数のモバイル回線が5Gとなる(野村総研 北俊一氏の講演)ので、システム産業で言われている「2025年の崖」の時期とちょうど重なりますし、さらに、DXの進展期とタイミングが一致するので、5Gの効用には非常に大きな期待が掛かります。5Gの普及テンポの予測でも4G/LTEの時より早いとの見方が一般的なのも頷けるところです。
モバイル通信事業者だけで5Gの産業利用が進む訳ではないし、ましてやDXの推進による2025年の崖の解消が図れることはありません。しかし、モバイル通信事業者自身にも前述のとおり数多い課題があり、自らの事業運営や組織構造にまで及ぶ革新がないと5Gという新しい未来を開くステージに立つことはできないと理解しておく必要がありそうです。世界でも5Gサービスのスタンダードな成功モデルはまだありません。日本発のスタンダードモデルが生まれることを期待しています。
※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部無料で公開しているものです。
調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。
ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード
平田 正之の記事
関連記事
-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上
- WTR No441(2026年1月号)
- ヘルスケア・医療
- 日本
-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる
- WTR No441(2026年1月号)
- オーストラリア
- 世界の街角から
-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに
- 5G/6G
- AI・人工知能
- ICR Insight
- WTR No441(2026年1月号)
- モバイル通信事業者(国内)
- モバイル通信事業者(海外)
-

中国におけるロボット産業の進展
- WTR No441(2026年1月号)
- ロボット
- 中国
-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜
- WTR No441(2026年1月号)
- ポイントビジネス
- 日本
- 経済
- 金融
5G/6G 年月別レポート一覧
ランキング
- 最新
- 週間
- 月間
- 総合