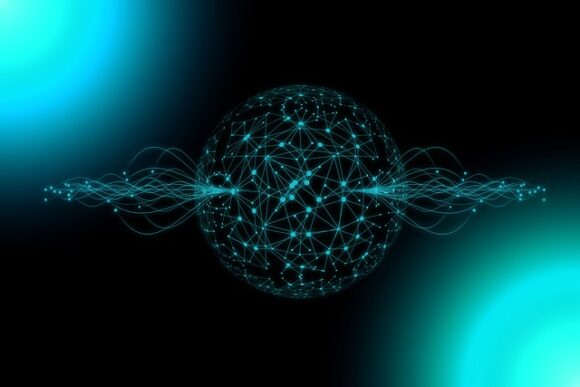改正会社法の施行と取締役会の機能強化、ガバナンスの強調

現在、3月決算の上場会社では6月の株主総会に向けた準備が進んでいますが、本年3月1日に令和元年(2019年)改正会社法が施行となりガバナンス面でさまざまな影響が出ています。今回施行された主な項目は次のとおりです。
- 取締役報酬等の決定方針と株式報酬関係の決議
⇒株主総会における説明義務と事業報告の記載
- 補償契約と役員等賠償責任保険契約の決議
⇒株主総会参考資料と事業報告の記載
- 社外取締役の選任
⇒期待される役割(株主総会参考資料)と行った職務(事業報告)について記載
- 株主提案権の濫用的行使の制限措置
⇒株主の議案要領通知請求権の議案数上限を10とする
- その他市場実務面の改正‐社債管理補助者制度の導入と株式交付制度の制定など
なお、実務面での取り扱いが最も変わる株主総会資料の電子提供制度等あらかじめ準備が必要となる規定は2022年度の施行予定なので、今回はまだ影響はなく従来どおりです。以上のとおり、今回の改正会社法施行の趣旨を大別してみると、5の市場実務面の改正を除いて上場会社のガバナンスに関する改正が中心となっていることが分かります。上記4の株主提案権関係の行使制限と2022年度施行予定の株主総会資料の電子提供制度の導入は株式会社の最重要意思決定機関である株主総会の議事運営を円滑に行って、株主との対話や質疑の充実を図る狙いを持ち、実務上の過度な負担を軽減するもので、従来企業側からの要望が強かったものの制度化です。
一方、上記の1~3の改正・制度化は実質的に取締役会の機能強化をもたらし、ガバナンスを強調するものです。特に取締役の報酬に関しては、近年一部の上場会社で企業トップの暴走が目立ち、いわゆるお手盛り的な役員報酬の決定などが明らかになるなど問題が顕在化していただけに注意が必要です。また、役員報酬に関しては取締役会一任、代表取締役への再一任とする実務が多く見られるだけに、取締役報酬等の決定方針の取締役会決議とその内容の事業報告や有価証券報告書への記載・開示の義務付けには大きな意味があります。有価証券報告書の記載義務違反が企業トップの逮捕原因となったことは記憶に新しいところです。今回の取締役の報酬等に関する取締役会の責務の規定において、決議と同時に株主総会における説明義務および株主総会資料と事業報告への記載義務の定めをおいている趣旨もそこにあります。ただ、2019年1月31日施行の金融庁の「企業内容等の開示に関する内閣府令」により有価証券報告書では既に同様の内容の記載が規定されているので、開示の実務としては大きな変化はないと思われます。(本誌「InfoCom T&S World Trend Report」2019年3月号 巻頭“論”「コーポレートガバナンス法制、2019年以降に大きな変化」参照)。本質は取締役会決議等の役割の変化、つまりガバナンスの一層の発揮に帰着します。取締役の個人別報酬の決定が実務上代表取締役への再一任となるケースが多いだけに、企業トップの暴走・お手盛りとならないように歯止めをかける役割が取締役会に求められています。
そうなると勢い社外取締役の役割が重要となるので選任の義務付けにつながりますが、既に東証1部上場会社では2020年に2人以上の独立社外取締役を選任する会社が95.3%、3分の1以上選任する会社が58.7%に達しているので、実際には今回の改正会社法の規定が問題となることはほとんどなく、むしろコーポレートガバナンス・コードの改定で東証市場再編後の「プライム市場」では独立社外取締役を3分の1以上にすることの方に関心が集まっています。実務面では株主総会参考資料や事業報告に社外取締役に期待される役割や行った職務の概要を記載し開示する規定により、社外取締役の具体的な役割に注目が集まることの方がガバナンスに大きな変化をもたらすと思います。そこでは適切な方針と手続きのもと会社役員にとってインセンティブが効いた妥当な報酬とすることが何より大切となります。その意味で今回の改正で非金銭報酬として株式報酬の仕組みの見直しが行われて、取締役報酬として金銭の払込みを要しないで株式や新株予約権を発行する特則(いわゆる無償交付)が施行されたので、従来の株式報酬実務の運用がさらに緩和されています。上場会社の取締役のインセンティブ機能発揮が期待できます。
併せて、取締役との補償契約や賠償責任保険(D&O保険)契約に関する規定が施行となっています。これらは株主代表訴訟が対象とする賠償とは違って会社の業務執行上発生する第三者への賠償責任を対象としていて取締役の経営判断における萎縮を軽減しようとするものなので、報酬面のインセンティブと併せて一体となって効用を発揮するものです。インセンティブの強化、例えば業績連動報酬の割合の増加や株式報酬等の非金銭報酬の多様化などとのバランスを勘案して、全体として取締役の経営判断の際の萎縮効果を軽減して積極的な経営判断を促す意義は大きいと考えます。上場会社それぞれの姿勢が表れることになります。
最後に、日本の株式会社の運営は多くが監査役会設置会社でありマネジメントモデルとなっていて、欧米のモニタリングモデルをベースとしたグローバルスタンダードとはなかなか噛み合わずに国際的に見て十分な評価が得られず今日に至っています。最近の数次に渉る会社法改正やコーポレートガバナンス・コードの制改定もこの点を念頭において進められてきました。端的には取締役および取締役会の機能をいかに発揮してガバナンスの効いた株式会社経営とするのかという課題に挑戦しているということです。ガバナンスの強調はともすると判断の遅延や消極化を招きかねず、積極的な挑戦への妨げになるとの懸念さえありました。現実にCEOの暴走やお手盛りが見られているだけに舵取りの難しさを感じるところです。ただコロナ禍の今こそ、会社経営において前向きな取り組みが求められています。これまでの路線を離れて事業ポートフォリオの見直しを進める時です。今回施行の改正会社法の規定を活用して取締役会の機能強化、ガバナンスの強調を図る必要性を感じています。取締役会にとっては、CEO以下執行部の積極的な経営姿勢と経営目標追求の成果を評価・検証(モニタリング)すると同時に経営トップの報酬設定においてインセンティブの効いた仕組みの設計を行うことが最重要の課題となります。イノベーション、気候変動、感染症など事業環境が急激に変化するなか、投資家や消費者などのステークホルダーの動向にまで及ぶ幅広い見識が経営に必要となる今日、取締役会の機能強化が求められます。
※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部無料で公開しているものです。
調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。
ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード
平田 正之の記事
関連記事
-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上
- WTR No441(2026年1月号)
- ヘルスケア・医療
- 日本
-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる
- WTR No441(2026年1月号)
- オーストラリア
- 世界の街角から
-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに
- 5G/6G
- AI・人工知能
- ICR Insight
- WTR No441(2026年1月号)
- モバイル通信事業者(国内)
- モバイル通信事業者(海外)
-

中国におけるロボット産業の進展
- WTR No441(2026年1月号)
- ロボット
- 中国
-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜
- WTR No441(2026年1月号)
- ポイントビジネス
- 日本
- 経済
- 金融
InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧
ランキング
- 最新
- 週間
- 月間
- 総合