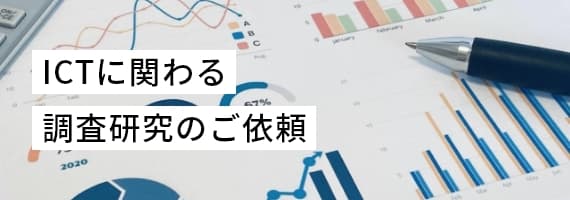転勤は死語になるのか?

2019年に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(働き方改革関連法)が施行され、残業時間の上限規制や一定日数の年次有給休暇の時季指定の付与義務化、正規・非正規雇用労働者間の公正な待遇の確保などの働き方改革が進められている。この法律は、労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現するための働き方改革を総合的に推進するためのものであるが、長年深く根を張って変えることが難しかった従来の働き方や慣行を変えることに一定の効果をもたらしたものと考えている。
しかしながら、現時点ではあくまでも基本的な労働環境の整備が進んだ段階であり、労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を真に選択できるようにしていくためには、働き方改革をもう一段前進させることが必要だと考える。とりわけ、長年続けられている転勤[1]という慣行については、労働者本人のみならずその家族にも重大な影響を及ぼすものであり、そのあり方について改めて社会全体で考え直す必要があるのではないだろうか。こうした問題意識から、本稿では転勤をテーマに取り上げ、今後のあり方について考察してみたい。
転勤という慣行はわが国独特のものであると言われている。それは転勤が戦後のわが国の経済成長とともに確立・定着した日本型雇用システムと密接不可分なものとして生まれ、定着してきたからである。戦後、わが国の経済は朝鮮戦争による特需をきっかけに神武景気、いざなぎ景気などを経て、およそ20年に亘る高度成長を遂げた。この間、第一次産業から第二次産業への移行が進むなど産業構造も大きく変化し、機械産業や重化学工業などが発展した。この過程において被用者の増加とともに雇用システムや労働慣行も戦前のものから変化を遂げ、年功序列、終身雇用、企業別労働組合のいわゆる「三種の神器」と言われる日本型雇用システムが確立・定着した。
日本型雇用システムにおいては、企業は学生を一括で新卒採用し、従事する職務や場所・地域を限定することなくジョブローテーションによって長期的に幅広い業務や組織を経験させ、多種多様な知識や経験を身につけた人材を育成するのが一般的であった。このように雇用契約において職務が特定されず、就く職務が使用者の命令によって決まることが諸外国と決定的に異なる日本型雇用システムの最大の特徴である。また、給与については、長期勤続者ほど高い給与で処遇する年功賃金が主流であったが、年功賃金は若年層ほど貢献度よりも低い賃金に、高年層ほど貢献度よりも高い賃金となる傾向があったことから、社員も長期的な雇用(=終身雇用)を望んだ。
これに加え、正社員については「整理解雇の4要件」(①解雇に経営上の必要性があるか、②希望退職者の募集や配置転換など解雇を回避する努力を尽くしたか、③解雇対象者の人選は合理的で公平か、④解雇の手続きは妥当か)を満たさなければ解雇できないという厳しい解雇制限の存在も相まって、終身雇用が定着したと考えられている。
このような背景により、企業は社員の長期雇用を保障する代わりに配置転換などに関して広範かつ強い人事・裁量権を有し、社員は一定程度の不利益などがあったとしてもそれに従うことにより安定した雇用が長期間約束されるという、日本独特の雇用慣行が確立された。転勤はこのような日本独特の雇用システムの下で生まれ・定着したものであり、企業内で人材の需給調整、人材育成、幹部養成におけるスクリーニング、不正・マンネリ防止といった複合的機能を長期に亘り果たしてきた。転勤は高度経済成長期に合致した人事労務慣行として一定の合理性があったと言えるであろう。
転勤は労働契約上の職務内容・勤務地の決定権限(配転命令権)に基づき行われるものである。判例では、就業規則に定めがあり勤務地を限定する旨の合意がない場合には、使用者は労働者の合意を得ずに勤務地の変更を伴う配置転換を命じることが広く認められている。また、転勤命令について、①業務上の必要性がない場合、②その必要性があっても他の不当な動機・目的をもってなされた場合、③労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合等、特段の事情がない場合には、当該転勤命令は権利の濫用に当たらないとされている。
一方で、近年、育児や介護などの事情を抱える労働者の仕事と生活の調和を実現するための法整備も行われてきた。例えば、育児・介護休業法は企業が就業場所の変更を伴う配置の変更をしようとする際に、これにより育児や介護が困難となる男女労働者がいる場合は、その育児や介護の状況に配慮すべきことを規定している(第26条)。また、男女雇用機会均等法は性別による間接差別を禁止しており(第7条)、間接差別となり得る措置を省令[2]で列挙している。具体的には①募集、採用、昇進又は職種の変更に当たって、転居を伴う配置の変更に応じられることを要件とすること、②昇進に当たって、異なる事業場間の配置の変更の経験があることを要件とすることを挙げ、合理的な理由がない限りこれらは性別による間接差別になるとしている。
このように労働者への配慮規定などが整備されてきたものの、転勤は社員のみならずその家族の家庭生活やライフプランなどにも重大な影響を及ぼすものであり、その是非が裁判で争われたケースも多数ある。転勤拒否を理由にした懲戒解雇を巡る「東亜ペイント事件(S61.07.14最二小判)」はその一つである。家庭の事情により転勤命令に従わず解雇された元社員の男性の訴えに対し、最高裁判所は使用者の転勤命令権は無制限に行使できるものではなく、これを濫用することは許されないとしながらも次のような判断[3]を示した。「(前略)本件転勤命令には業務上の必要性が優に存したものということができる。そして、(中略)転勤が被上告人に与える家庭生活上の不利益は、転勤に伴い通常甘受すべき程度のものというべきである。したがって、(中略)本件転勤命令は権利の濫用に当たらないと解するのが相当である。」これにより転勤命令は権利の濫用に当たらず、企業には強い配置命令権があるとの解釈が確立し定着することとなった。
時代は令和となり、少子高齢社会の進展に伴う労働力人口の減少、女性の就業率の向上、共働き世帯の増加などの社会の変化に加え、デジタル化とグローバル化の進展によって企業のあり方も働き方も大きな変革を迫られている。とりわけ、コロナ禍という有事によりリモートワークへの移行が急速に進み、労働者の働く場所や時間の柔軟性が大幅に高まったことにより、労働に関する「時間主権」と「場所主権」が企業側から労働者側にシフトするという劇的なパラダイム転換が起こっていることに注目したい。コロナ禍を経験したことにより、仕事や職業生活に何を求めるか、さらには仕事と個人の生活や人生をどう結びつけるのかを考え直すようになった人も多いのではないだろうか。
また、企業と労働者間の雇用関係に目を転じると、ギグワークや副業・兼業が広がっていることにより、必ずしも企業と労働者が「1対1」の関係ではないことも珍しくなくなった。また、プラットフォームビジネスの台頭に伴い、企業に抱えられていた労働力の外部化や独立事業者化が進み、デジタルプラットフォームを媒介して働くプラットフォームワーカーも増加するなど、企業と労働者の雇用関係もかつてとは比較にならないほど多様化している。このような社会のあり様や人々の価値観の変化などにより、現在は働き方も企業と労働者との関係も昭和の高度成長期とは全く異なる状況となっている。転勤が家庭生活に及ぼす影響について、どのような場合に「通常甘受すべき程度のもの」と言えるのかについては個別のケース毎に判断すべきことではあるが、令和の社会においては昭和の高度経済成長期とは異なる多様な受け止め方があるところであろう。
このような変化に対して、企業は転勤をどう見直し、労働者が求める働き方と企業が労働者に望む働き方のミスマッチを防いでいくべきであろうか。既に多くの仕事はVR(仮想現実)、AR(拡張現実)などを含めたICTを有効に活用すれば、時間と場所に関係なく進めることが可能となっている。メタバースや遠隔コミュニケーションロボット[4]の活用も今後さらに進むであろう。ICTの活用によりリモートで遂行可能な業務やポストを選定し、これらの業務に社員を充てることで望まぬ転勤を減らすことはすぐにでも開始できる取り組みの一つと言えるであろう。
一例として、NTTグループは「住む場所」の自由度を高め、ワークインライフ(健康経営)を一層推進する観点からリモートワークを基本とする新たな働き方を可能とする制度(リモートスタンダード)を今年7月から導入している。国内であれば全国どこでも居住可能で、これにより転勤や単身赴任を伴わない働き方を拡大していくこととしている[5]。弊社でも既にリモートワークを基本とした働き方が定常化しており、オフィス所在地である東京都から遠く離れた地域に生活の拠点を構えながらリモートワークで仕事をすることは、もはや日常の光景として定着している。このように、働き方の選択肢を増やすことは社員のエンゲージメントを高めるうえでも重要なことだと考える。
一方で、転勤は単に「働く場所」の問題としてではなく、企業にとっては極めて重要な人事・経営戦略の一部として考える必要があることは論を待たない。したがって、転勤の見直しに当たっては、その根底に人事制度や異動管理を含むトータルな人事戦略の改革を据えることが必要不可欠である。一例として、パーパス経営と働き方改革を連動させ、パーパス実現のために必要な人材の採用・育成戦略の中に社員のニーズや希望に応じた多様な働き方の実現を組み込んでいくといった考え方を採用することが挙げられる。そして、このような戦略に基づき、転勤を繰り返すことにより幅広い業務経験を積んで能力を培い、それが格付けに反映されていく「職能資格制度」から、社員の役割や職務を明確にし職務に人をくくり付ける「役割等級制度」や「ジョブ型制度」に人事制度を抜本的に見直すことも有効な選択肢の一つとなるであろう。
また、これらの見直し前であっても、転居を伴わない「異動」では得られない転勤の本質的な目的やメリット・デメリットなどをゼロベースで包括的に検証することや、転勤を個々のライフイベントの変化に対応できるものにしていくこと、そして予め転勤の有無やその具体的な運用について社員が中長期的な見通しを持てるような仕組みにすることなどにより、望まぬ転勤を減らすといった個別の取り組みも考えられる。なお、労働者にも企業の定めたルールに従うだけでなく、一人ひとりが自律的に自身にとって幸せな働き方を考え実践する主体的な姿勢や行動が求められるのではないだろうか。
リモートワークが日常のものとなり、既に多くの仕事がリモート環境で可能になっているとはいえ、現実にはすべての仕事がリモートで完結できるわけではない。また、リモートワークには必ずしも適さない職種や役職もある。それらを踏まえれば、転勤という慣行が一朝一夕になくなることは現実的に考えづらいであろう。しかしながら、全国各地に拠点を持つ大企業を中心に転勤の見直しに向けた取り組みが始まっている。これらはまだ緒に就いたばかりであるが、転勤のメリット・デメリットを今一度包括的に検証したうえで、労働者が望まぬ転勤をなくしていく取り組みが進むことを期待したい。
新型コロナウイルス感染症のパンデミックを社会全体が経験したことにより、長年なかなか変えられなかった働き方や仕事の進め方を根本から変革する千載一遇の好機が訪れている。今進められている働き方に関する様々な取り組みは、わが国全体、さらにはグローバルな規模での壮大な社会実験とも言えるかもしれないが、このチャンスを決して逃してはならない。コロナ禍により社会や人々の価値観が大きく変化した今を変革の絶好の機会と位置づけ、コロナ禍前の働き方に戻るのではなく、デジタルテクノロジーなどを活用して既存の枠組みに捉われない新たな働き方にチャレンジすべきである。
内閣府が今年6月に公表した令和4年版男女共同参画白書[5]は「もはや昭和ではない」というフレーズで「脱・昭和」を呼びかけている。働き方にも「脱・昭和」が必要であり、昭和の働き方の象徴の一つである転勤についても見直しが急務である。見直しが進むことにより、働くことを希望するすべての人がそれぞれの事情に応じた柔軟かつ多様な働き方を選択でき、ダイバーシティに富んだ人材がいきいきと活躍できる、令和に相応しい社会が一日も早く実現されることを期待したい。
参考文献
- 「転勤に関する雇用管理のヒントと手法」
(厚生労働省雇用均等・児童家庭局 2017年3月)
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11903000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Shokugyoukateiryouritsuka/0000160191.pdf - 「企業における転勤の実態に関するヒアリング調査」
(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 資料シリーズNo.179 2016年11月)
https://www.jil.go.jp/institute/siryo/2016/179.html - 「ダイバーシティ経営推進のために求められる転勤政策の検討の方向性に関する提言」
(中央大学大学院戦略経営研究科ワーク・ライフ・バランス&多様性推進・研究プロジェクト 2016年11月)
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000148348.pdf - 「転勤のゆくえ」
(Works No.134 リクルートワーク研究所 2016年2月)
https://www.works-i.com/works/item/w134_toku1.pdf - 『働き方ネクストへの人事再革新』
(吉田寿著 日本経済新聞出版 2021年7月) - 『ジョブ型雇用社会とは何か―正社員体制の矛盾と転換』
(濱口桂一郎著 岩波書店(岩波新書) 2021年9月) - 『人口と日本経済 長寿、イノベーション、経済成長』
(吉川洋著 中央公論新社(中公新書) 2016年8月)
[1] 転勤という言葉は様々な意味で用いられるが、本稿では労働者やその家族の生活への影響に着目して論じることから、「単身赴任を含む、転居を伴う配置の変更・異動」という意味で用いる。
[2] 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年一月二十七日労働省令第二号)
[3] https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/925/062925_hanrei.pdf
[4] https://orihime.orylab.com/
[5] https://group.ntt/jp/newsrelease/2022/06/24/220624a.html
[6] https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r04/zentai/pdf/r04_tokusyu.pdf
※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部無料で公開しているものです。
当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。
調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。
ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード
村松 敦の記事
関連記事
-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上
- WTR No441(2026年1月号)
- ヘルスケア・医療
- 日本
-
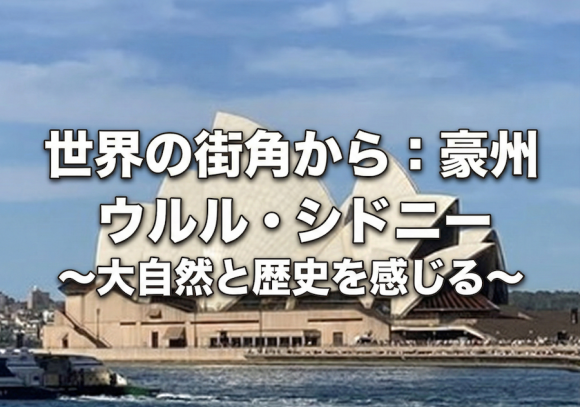
世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる
- WTR No441(2026年1月号)
- オーストラリア
- 世界の街角から
-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに
- 5G/6G
- AI・人工知能
- ICR Insight
- WTR No441(2026年1月号)
- モバイル通信事業者(国内)
- モバイル通信事業者(海外)
-
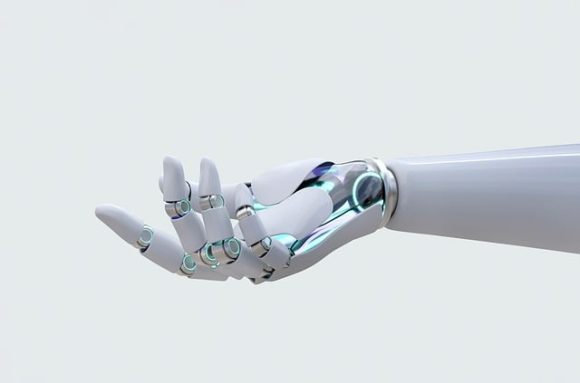
中国におけるロボット産業の進展
- WTR No441(2026年1月号)
- ロボット
- 中国
-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜
- WTR No441(2026年1月号)
- ポイントビジネス
- 日本
- 経済
- 金融
InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧
ランキング
- 最新
- 週間
- 月間
- 総合