ICT分野に身を置く者として長年感じることは、多数の新しいカタカナ言葉が出てくることはもちろんのこと、通常使わないような意味で使う言葉が結構たくさんあることだ。それがいつの間にか定着し、曖昧な理解のままその言葉を使い続けていることがよくある。
その中で筆者が違和感を覚えるもの、その言葉の本来の意味を関係者が理解して使っているのか疑問に思うものを二つほど挙げてみよう。いずれも最近のICT分野では頻出する言葉である。
「仮想化」
ひとつめは 「仮想化」あるいは「仮想」という言葉だ。 この言葉は最近のクラウド全盛の時代になり、より多く耳にするようになった。例えば「ネットワークの仮想化」「サーバの仮想化」「デスクトップの仮想化」、あるいは今年の1月初めに米国で開催されたConsumer Electronics Show(CES)でのキーワードでもあった、「仮想現実(バーチャル・リアリティ:VR)」というような使い方をされる。本来、「仮想」というのは、実在するものでなく、文字通りにいえば「仮に思う」であり、「仮説」「妄想」とも文脈上はあまり意味が変わらない。「仮想化」するとは、一般の感覚では「実在しないものにする」と思ってしまう。「仮想化」の元の英語は「Virtualization」であるが、そのベースである「Virtual」という英語の本来の語義はもともと「実質的な」という意味であり、VRのように、実在するもの(リアル)に対して、実際にあるように感じさせるというのが「バーチャル」だったはずだ。Virtualizationは「実質化」と言った方がそもそもの語義に近い。
本来、「ネットワークの仮想化」「サーバの仮想化」と言ったら、現在そこにある物理的なネットワークやサーバを実在しないものにするという意味になってしまう。それとは逆に散在する物理的なネットワークやサーバを含む様々なインフラの必要な部分を集めて、「実質的に」ネットワークやサーバとして機能させるもの、こういえば分かりやすくないだろうか。
ちなみに、筆者の専門分野でもある中国語では、「仮想化」は「虚擬化」と書く。中国語にすると、日本語ではカタカナで分かったような気になっている言葉の本来の意味が改めて納得することがあるが、この「仮想化」の場合は文字面をみると中国語でも今一つだ。仮想移動通信事業者(MVNO)のことを中国語で「虚擬移動通信運営商」、略して「虚商」と書いたりするが、これでは偽業者のようにも見えてしまう。
話をもとに戻すが、「仮想化」と同じ流れでの最近のバズワードとして「SDN/NFV(ソフトウェア定義ネットワーク/ネットワーク機能の仮想化)」があげられる。何となくわかったつもりでもわかりにくく、とっつきにくい言葉の代表ともいえるが、「散在したリソースをパッチワークのようにつぎはぎをして、『実質的に』それと同じように利用するもの」と考えるとわかりやすくないだろうか(『 』部分を「仮想的に」というよりも)。実際、SDNとはバラバラだった各ハードウェアに、同じ標準のソフトを上からかぶせて(オーバーレイ)横串することで、「実質的に」ネットワークとして利用するということだ。また、ごく最近注目されている、企業内のWANを「仮想的に」構築するというSD-WANはまさにユーザがほぼ無意識に「実質的に」通常のWANと同じように利用できるセキュアなネットワークを企業に提供するものだ(SD-WANについては別の機会に詳述したい)。
「プラットフォーム」
もうひとつ、気になる言葉として「プラットフォーム」を挙げてみる。「プラットフォーム」=Platformは、ICT分野では、インフラ、アプリケーションなどと同列に一つのレイヤとして使われる言葉であることは周知のとおりだ。どうしてもこの業界の中にいると、テクニカルなとらえ方が先行してしまう。ただ、もともとの英語での「プラットフォーム」とは、平場、舞台、ステージといった意味であり、それは鉄道の駅の「プラットフォーム」という言葉で使われるとおりである。ちなみにこれも中国語でどう書くかといえば、「平台」となる。ICT分野で使う場合でもそのとおりに表記するが、カタカナよりも明らかにその意味が把握しやすくないだろうか。「プラットフォーム」とはそもそも平場や舞台のように人、モノ、カネ、情報が集まるところという意味であり、そこには本来インフラも、アプリケーションも含まれるわけである。Googleは検索エンジンというプラットフォームで巨大化した。FacebookはSNSというプラットフォーム、LINEはメッセンジャーアプリというプラットフォームでそれぞれ「舞台」に多数の客を集めた。通信事業者についていえば、インフラという舞台がプラットフォームであると考えればよいはずであるが、インフラとプラットフォームは別物と捉えられている場合が多い。現在NTTグループが推進している「コラボレーションモデル」は、インフラという巨大なプラットフォームの上に、様々な分野のステークホルダーが乗っていくことで、社会的な課題を解決するためにともに行動する巨大な「舞台」であると理解すれば、もっと腑に落ちる話になってくるのではないだろうか。
水天宮も
ところで、弊社は、日本橋人形町に鎮座する水天宮の目の前にある。安産と子宝でご利益のあるといわれる水天宮は、この約3年間、新社殿改築のために、日本橋浜町の仮宮(これも「仮想」でなく、「実質的」な社である)に移転していたが、今週4月8日についに新社殿が正式竣工した。この人形町界隈は、水天宮を中心とした「プラットフォーム」があるおかげで多数の人が訪れることで賑わっている。水天宮新社殿完成という新たな「プラットフォーム」の始まりを機に、リアルな水天宮を是非ご覧いただき、ついでに弊社にもお気軽にお立ち寄りがてら、「実質的」な調査研究のご相談をいただければ幸いである。

水天宮新社殿
※水天宮ホームページ
https://www.suitengu.or.jp/
調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。
ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード
町田 和久の記事
関連記事
-
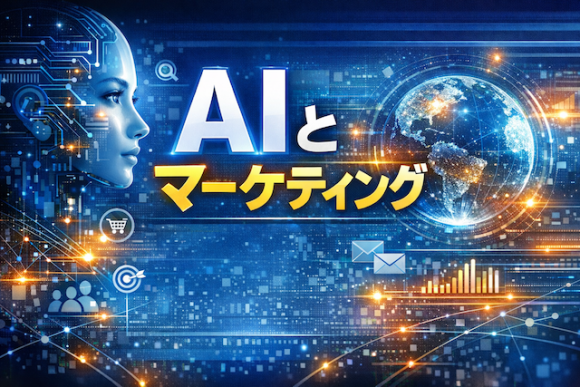
AIとマーケティング
- AI・人工知能
- ICR Insight
- WTR No442(2026年2月号)
- 生成AI
-

ソブリンAIを巡る各国の動向 ~制度・投資・地域連携に見る多様なアプローチ~
- AI・人工知能
- WTR No442(2026年2月号)
- 生成AI
-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上
- WTR No441(2026年1月号)
- ヘルスケア・医療
- 日本
-

中国におけるロボット産業の進展
- WTR No441(2026年1月号)
- ロボット
- 中国
-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜
- WTR No441(2026年1月号)
- ポイントビジネス
- 日本
- 経済
- 金融
ITトレンド全般 年月別レポート一覧
ランキング
- 最新
- 週間
- 月間
- 総合









