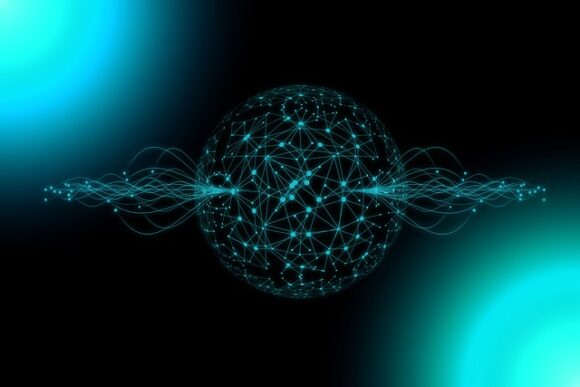映像と音楽のネット・放送サービス―中高年個人の生活を豊かにする
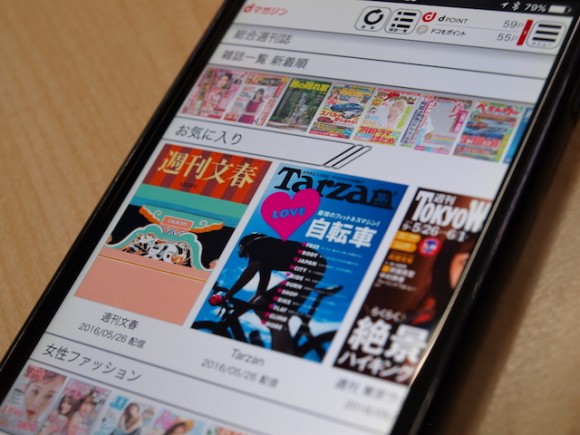
ここ2~3ヵ月の間に私の身の回りのICTサービス環境にいろいろな変化がありました。この“風見鶏”にも、3月1日に「光BOX⁺をテレビに接続-中高年の新たな楽しみ」を掲載して、テレビでネット番組を視聴する新たな楽しみについてレポートしました。しかし残念ながら、やはりテレビはテレビで、ネット番組や映画などを見ることは少なく普通のテレビ番組を見ています。家では妻と2人暮しですが、テレビは結局家族全員のものという認識は変らず、家族共通・共用のデバイスとの位置づけであることを改めて感じています。そこで今度は、パソコンやタブレットを使って独りで楽しめるサービスに挑戦してみましたので、それをレポートします。

自宅のパソコンとWi-Fiチューナー
第1は、4月11日始まった「AbemaTV」を早速、パソコンとタブレットに設定して、主にニュースやドキュメンタリー、ドラマを見るようになりました。タブレットでは画面が小さく視聴するのが少し辛いですが、パソコンなら十分にこの無料テレビ番組(20チャンネル以上)が楽しめます。番組内容はまだまだ成熟しておらず、感動するような番組はまだ体験していませんが、空き時間に立ち上げておいて、ながら視聴を独りで楽しむには十分なレベルです。テレビのような共用ではなく、ネットとITデバイスで独り楽しむ新しい映像サービスではないかと思います。VODとは違って自分で番組(コンテンツ)を選ぶ必要がなく、これまでのテレビ視聴に近いスタイルなので気楽に接することができるのが特徴ですし、何よりも無料というのが中高年には魅力です。番組の提供側からは、視聴者、視聴番組・時間などの情報がすべて確認できるので、各種のデータを蓄積し解析することで、新しい番組制作や広告宣伝手法の開拓に繋がることを狙っているものと思います。従来のテレビに近い感覚なので新しい分野開拓になるでしょう。
2番目は、3月から開始された「i-dio」という無料のV-Lowマルチメディア放送を聴くようになりました。まだ東京・大阪・福岡の都市圏だけのサービスですが、放送受信に必要な専用チューナーの“i-dio Wi-Fiチューナー”をモニター応募で入手して、タブレットにアプリを取り込んでラジオとして音楽を聴いています。これも典型的なながら族です。デジタル信号を放送電波で受信しているのでとてもよい音質でジャンル別の音楽番組を楽しむことができます。このi-dio放送を聴くには専用チューナーが必要なのでデバイスの普及が何より大事なところですが、同様にV-High放送電波を用いたNOTTVがこの6月30日にサービス終了することを考え合わせると、二の舞にならないか心配でもあります。自宅で聴いている限り、このi-dio Wi-Fiチューナーの性能には問題がなく、音楽番組もラジオのストリーミングサービスとして十分なレベルにあると感じます。成功するかどうかは、結局、NOTTVのケースのように専用チューナーを搭載したデバイスの普及と音楽コンテンツ(番組内容)に依存することになります。
前述のAbemaTVにせよ、i-dio放送にせよ、テレビ・ラジオの放送会社にとっては、これまでなじんできたあらかじめ定めた番組編成に従ったストリーミング(流し切り)型なので、番組制作・編成のノウハウが活用できる利点があります。他方、サービスの受け手側からは使うデバイスは一緒でも通信回線を用いるネットサービス型と専用チューナーが必要となる放送サービス型とに2分されます。NOTTVの教訓からは、いかに専用チューナーを普及するのかが大きな課題です。また、AbemaTVは通信回線を使ったネットサービスなので、どうやって収入を得てビジネスモデルを成り立たせるのかというネットサービスに本質的な難問が存在します。CATVや衛星多チャンネル放送とは違う通信回線を用いる放送型サービスという新しい領域にこれからの可能性を感じます。
少し話題が逸れますが、タブレット(スマホ)とパソコンを共通に使ったサービスとして、少し前からNTTドコモの「dマガジン」を登録(契約)して、いろいろな週刊誌を読み始めています。会社勤めもシニアになり会社以外、自宅にいる時間やフリーに外出する機会が多くなっていて、週刊誌、特にいわゆる総合週刊誌やビジネス誌を手にする機会が減ってしまいましたので、週刊誌1冊程度の値段でいくつも読めるこのサービスを重宝しています。お蔭様でテレビのワイドショーや報道番組を見ても話題についていくことができるようになりました。外出先でのモバイル回線では回線の混雑具合にもよりますが、どうしてもダウンロードに時間がかかることがあります。ただ、自宅ではWi-Fi環境なのでとてもスムーズに週刊誌を読んでいます。もちろん、パソコンを使えば画面がさらに大きく楽に読むことができます。紙とは異なる感触なので最初は少し戸惑うところがありましたが慣れてしまえば大丈夫、今や相当の週刊誌通になりました。これもICTサービスを活用した楽しみのひとつです。加えて、ビジネス週刊誌に目を通すことで、日頃人に会う機会が減り、セミナーや講演会などに参加することも少なくなっている中高年には、良い意味で脳細胞の刺激になりますし、若い世代や現役の人達の苦労のほどが分かり、文句ばかりは言っていられないとしみじみ感じています。まさかNTTドコモがそこまで見通して、このdマガジンを始めたとは思いませんが、私には誠にありがたいサービスです。今年3月末の契約数が325万とのこと、特にドコモユーザー以外の人も利用可能なので、新しい購読プラットフォームになりつつあるようです。dマガジン以外の各社が運営している週刊誌購読プラットフォームまで含めるとかなりの週刊誌購読者がネット上に存在していることになります。ドコモのdマーケット全体では1,554万契約に達しているなか、このdマガジンはシニア層向けサービスとして本当に有効だと感じます。
私のICTサービス環境は、自宅にいる時間が長くなり、会社以外に外出する機会が多くなるにつれて、光回線、モバイル回線、Wi-Fi、携帯、タブレット、パソコン、テレビを組み合わせて、ながら視聴から情報誌の購読まで広がってきました。もちろんメールアドレスは、会社用、個人用、各種登録用と使い分けながら日々生活しています。次に何か新しいサービスがあれば、それに挑戦して、これからのマーケットやイノベーションを考える契機にしたいと考えています。
調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。
ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード
平田 正之の記事
関連記事
-

都市農業(アーバンファーミング)におけるICT利活用の現状と未来展望
- ICT利活用
- WTR No438(2025年10月号)
- 日本
- 農業
-
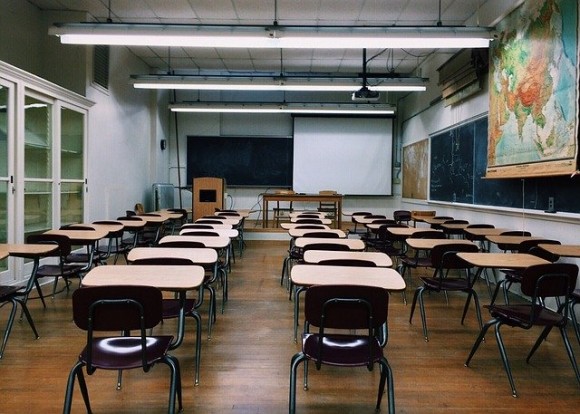
ICTが変える授業の形 〜NEXT GIGAにおけるICTの現在地とこれから
- GIGAスクール構想
- WTR No439(2025年11月号)
- 教育
- 日本
-
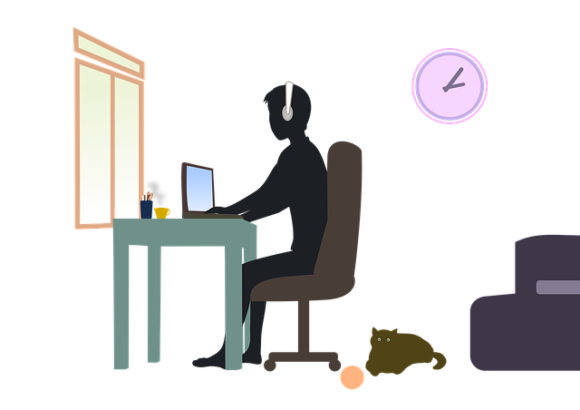
テレワークは「終わった」のか、「これから」なのか ~「ハイブリッドワーク」が最終解とも言えそうにない理由~
- WTR No431(2025年3月号)
- テレワーク
- 働き方改革
- 日本
- 米国
-

地域通貨はエコマネーの夢を見るか?
- ICR Insight
- WTR No430(2025年2月号)
- デジタル通貨
- 日本
-

梨の生産におけるICT活用の現状と未来展望
- ICT利活用
- WTR No427(2024年11月号)
- 日本
- 農業
ICT利活用 年月別レポート一覧
ランキング
- 最新
- 週間
- 月間
- 総合