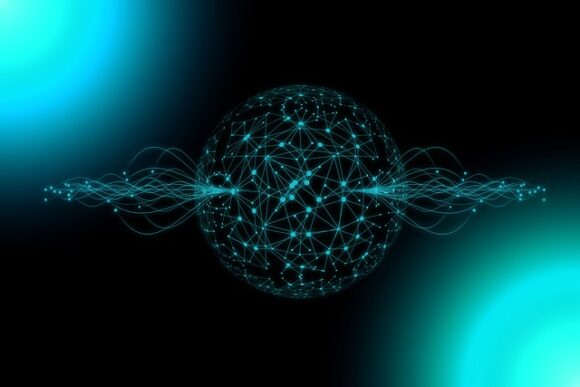先月5月中旬に宮城県内の東日本大震災被災地を巡ってきました。県南部の長い砂浜が続く名取市・岩沼市から、北の岩手県にまで及ぶ切り立った岩場が連なるリアス式海岸地帯の石巻市、女川町、南三陸町、気仙沼市まで、今、震災被害地はどうなっているのか、復興の模様はどうなのか、また保存論議のある震災遺構を自分の目で確かめておきたくて訪問しました。
実は東日本大震災の発生後、これまでも2度、岩手・三陸海岸の津波被災地に行ってその被害の大きさを実感してきました。南から陸前高田、大船渡、釜石、大槌町、宮古、田老町などで津波の爪跡をまざまざと見せつけられ、大きなショックを味わったことを覚えています。最初の2011年秋に訪ねた時には震災後まだ日が浅かったので、がれきの撤去・収集作業が各地で行われていて、コンクリート、鉄材、石材、タイヤ類、自動車・バイクなどがあちこちに分別されて文字どおり山のように積み上げられて本当に異様な光景でした。もちろん、街のなかには建物はまったくなく、電柱も携帯基地局も何も残されてはいませんでしたし、大きな電話局局舎すら3階まで水没して完全に使用不能となっていました。今でも忘れられません。
2回目も岩手県内を2012年秋に巡りました。被災から1年半以上が経過していましたので、既にがれきの撤去は終了し、どの町に行っても一面野原となり、もともとそこは草地だったのではないかと思わせる、人の気配のない荒涼感を感じました。さらに、ようやく始まった海岸の防潮堤防の復旧工事を見て、津波の高さとその破壊力のすさまじさを見せつけられました。例えば、田老町の高さ10mにも及ぶ大堤防すら破壊して町を押し流したのですから、人の力で防げるのか疑問すら抱きました。
そして今回、久し振りに震災被災地を訪れてみたくなったのは、復興の模様や被災の記憶との向き合い方、また保存論議のある震災遺構の対象を見ておきたいと思ったためです。昨年2014年夏に福島県いわき市の奥に行く用事があった折、除染で出た土や草木などを保管する仮置き場を見て回ったことがありますが、その時に改めて震災の被害といっても場所や原因によって大きな違いがあり、人々の心に刻み込まれたことも違っていることを実感しました。津波の被害も砂浜の海岸とリアス式の湾とでは違いがあるし、避難場所も裏山の高台のあるなしでまったく違っていることがよく分かりました。さらに人の心に残る傷跡も家族・友人などが無事避難できたかどうか、逃げる際の判断の分れ目にどう行動したのか、亡くなった方の無念さにどのように向き合うのか、などそれぞれ事情を異にしていることがしみじみと伝わってきます。
ただ今回救われたのは、岩沼市の玉浦西地区では既に海岸地域の被災者の方々の集団移転先の整備が終了して新しい住宅に移転が進んでいたことでした。元々の集落から5km以上内陸側に入った幹線道路沿いに新しく宅地造成が行われて住宅が建てられて、以前の集落毎に集団で隣近所まとまって移転が行われていました。造成地の中に広い公園が造られていて再出発するには生活面の環境が整ったところでした。普段の生活が破壊され多くの人が亡くなったことを思うと何とも言えませんが、復興に向けて一歩踏み出したことは確かです。
次いで震災遺構の保存で話題を集めている南三陸町の防災対策庁舎です。鉄骨がむき出しでいまにも崩れそうな残がいですが、平日の午前中にも拘らず次々と訪問者があり関心を集めていることがよく分かりました。また、その周辺では広大なかさ上げ工事が行われていて数多くのダンプトラックが動き回っており、時間の停止した場所と復興という変化が進む状況が対比されていましたので、私は将来の南三陸町復興の原点としてこの遺構は心に刻まれるのではないかと感じました。
最後に美談をひとつ、それは気仙沼向洋高校の生徒と先生方の適確な判断と勇気ある機敏な行動で当日学校内に残っていた2百人以上が誰ひとり欠けることなく全員が無事避難して助かったという事実です。校舎は3階まで津波で破壊され4階の1mまで浸水したということです。校庭はかさ上げが進んでいますが、南側の一部校舎は震災遺構として保存されることになりました。これもその時誰がどのように判断して行動したのか、どうリーダーシップが発揮され、皆が協力し合ったのか、この校舎とともに長く私達の記憶として伝えられていくことでしょう。
今回の被災地訪問で改めて感じたことを整理してみると、災害が人の心に残した傷跡は土地や家などそれぞれ事情を異にするのと同時に、避難時の状況や家族・友人・知人の被害によってまったく違っているということが第一です。復興を立案し計画実行する上でもこのことを踏えないといけないということです。しかし第二に、かさ上げや高台・内陸への集団移転も工事などが既に始まっていますので、一日も早くその姿を形にすることの大切さです。すべての集落が元どおりには決してならないでしょうが、かさ上げや高台などに街の中心を早期に作り上げることが復興の出発点です。高齢化が進んでいる地域なので、先が見えないと若い世代は町を出て行ってしまって戻って来ないでしょう。例えば、若い世代の親達は子供達が小学校存校中は移転先の仮校舎でも元の学校に通わせているが、子供が卒業する時に校区から離れて新しく住居を構えることが多く見られると言っていました。現実の生活とはそういうことなのだと思います。かさ上げ工事の壮大さには驚くほどです。新しい街作りには大きな希望がありますが、残された時間があまりないことも忘れてはいけないことです。
通信設備はかさ上げや高台整備に合わせて計画されていますが、工事中のところではまだまだ電柱も地下設備も手がつけにくい状態です。周辺の高い所に携帯電話の大規模基地局が建設されていて、まだ住む人のいない街なかをエリアカバーしています。工事関係者や訪問者には特に支障がなく復興の先取りの役目を示していたことに安心した次第です。
調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。
ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード
平田 正之の記事
関連記事
-

「地方創生2.0基本構想」を読む
- ICR Insight
- WTR No437(2025年9月号)
- 国内
- 地方創生
-
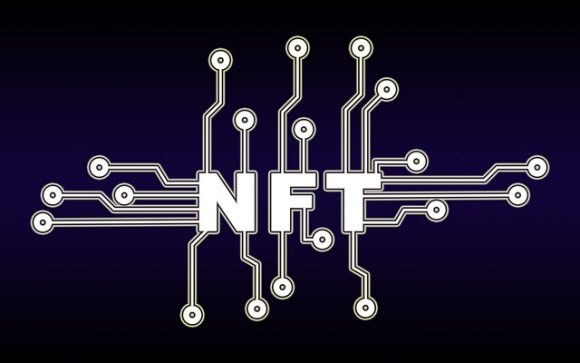
ブロックチェーンとどのように向き合うか ~地域活用の可能性~
- WTR No432(2025年4月号)
- ブロックチェーン
- 地方創生
-

久米島モデル ~カーボンニュートラルと産業振興を同時に達成するエコな地域経済社会システムの実現
- ICR Insight
- WTR No405(2023年1月号)
- カーボンニュートラル
-

地域発コロナ後の観光を考える(2) ~新たな観光・まちづくりを考える神戸市および倉敷市での 大学生たちの取り組み
- COVID-19
- ICTx観光
- NTTドコモ
- WTR No403(2022年11月号)
- 日本
- 観光
-

地域発コロナ後の観光を考える(1)~倉敷美観地区を舞台として大学生たちが考える新たな観光サービス
- COVID-19
- ICTx観光
- NTTドコモ
- WTR No400(2022年8月号)
- 日本
- 観光
地方創生 年月別レポート一覧
ランキング
- 最新
- 週間
- 月間
- 総合