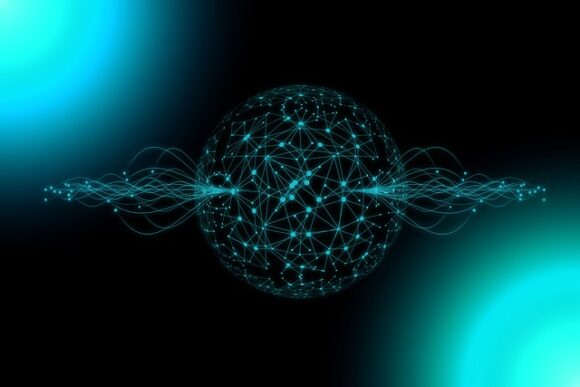大学講義での学生の質問に答えて―「現代の経営;情報通信サービスの動向と課題」を講義して―

先月7月の夏休み前に、滋賀県にある立命館大学びわこくさつキャンパスで、理工学部と薬学部の学生(1回生~4回生)に対し“現代の経営”コースで「情報通信サービスの動向と課題」と題して講義する機会がありました(注)。これまでに私が体験を通じて得た情報通信サービスについての思いを学生の皆さんに90分間話をしました。
受講したなかには就活中の4回生や今夏のサマーインターンを予定している3回生もいて、将来の職業選択についての真剣な思いが伝わってきて私もつい力が入って大声を張り上げてしまいました。講義に未熟なせいで時間配分にミスをしてしまい、十分な質疑時間が持てずに終了となってしまい残念なことをしました。そこで質問票を提出してもらって後から全体を整理して回答することにしたのですが、130人以上の方から約170の質問があり、大変なことになってしまいました。今の大学生の就職に対する真面目な取り組みと質問上手さに本当に驚きました。質問に対しては10問に整理して回答しましたが、私にとっていままでにない貴重な経験となりました。日本の産業界はこうした若い人達に日本の未来を託していることに希望が持てました。

講義の様子
今回は私なりに質問全体を取りまとめた10問を紹介して、現代の学生気質を感じて頂きたいと思います。前半5問は情報通信産業に関すること、後半5問は職業意識や仕事観に関することです。
- モバイル3社の多角化の方向など競争戦略の違い、料金・サービス・設備などはどうなるか。なかでもNTTグル―プの将来はどうか。
- 事業拡大の苦労や楽しさ、イノベーションやM&Aでの難しさなど。
- 料金の定額制と従量制、パケホーダイなどの料金の今後。LINEなど無料サービス、スマホの将来や通信サービスの動向。
- 通信事業者が減少した理由、新規参入の意味、今後の通信産業の姿はどうなるのか。
- 電波周波数の配分、周波数免許の方法、ソフトバンクの主張と現在の位置、標準化と技術選択のリスクなど。
- 就職にあたって通信分野を選択した理由とその選択の時期。官(公務員)とも民(会社員)とも違う電電公社という存在。
- リーダーシップとフォロワーシップの意味、リーダーの心得、組織における人と人との関係。
- 経営者とは何か、挫折や悩み。最も心掛けていること。現場主義の意味するものなど。
- 新しい分野への挑戦、失敗から学ぶ、変化を恐れない。チャンスは常にある。
- 異分野・異文化を学ぶ、交流することの意味。
以上のとおりですが、質問範囲が広く多岐に渉っていることが見てとれると思います。もちろん、定額制や周波数問題、またフォロワーシップという言葉などは私が講義のなかで触れたために疑問を抱き質問になったものです。聴講したのはほとんどが理工学部の学生だったので情報通信分野への興味が高いと思って臨みましたが、現実はさらに進んでいてロボット(ロボティクス)への関心が強いことに少し残念な思いを持ちました。しかしよく考えてみれば、これからの最先端産業を占う上では当然のことです。ICTをも取り込んだロボット産業に日本の経済も社会も期待しているので、新サービスや生産性の向上だけでなく、さらに介護や福祉にも貢献してくれると思います。
今回の講義のなかでも、職業選択の際の持論を私なりに展開しましたが、現在の大学(特に経営学コース)でややもするとベンチャーへの挑戦を促す極端な傾向にあることを批判しました。ベンチャービジネスへの挑戦はやりがいがあることですが、他方で大組織の活動を(再)活性化する意義と必要性をもっと大学の授業で強調してもらいたいと考えています。現実の経済・社会へのインパクトの大きさを思うと雇用など効果はベンチャービジネスを上回ります。大学での講義が学生の職業観に与える影響は計り知れません。バランスのとれた授業が行われることを希望しています。今回、久し振りに大学生に向けて話ができたことで改めていろいろなことを感ずることができました。関係の方々に感謝しています。
調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。
ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード
平田 正之の記事
関連記事
-
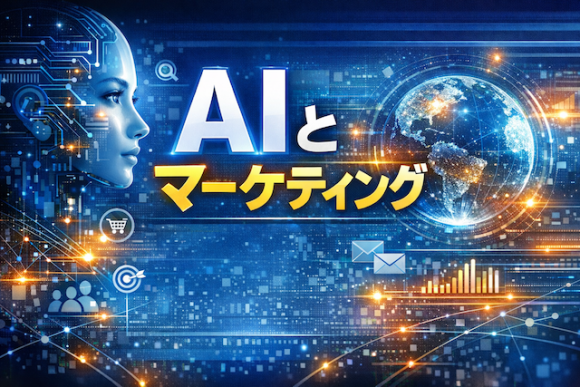
AIとマーケティング
- AI・人工知能
- ICR Insight
- WTR No442(2026年2月号)
- 生成AI
-

ソブリンAIを巡る各国の動向 ~制度・投資・地域連携に見る多様なアプローチ~
- AI・人工知能
- WTR No442(2026年2月号)
- 生成AI
-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上
- WTR No441(2026年1月号)
- ヘルスケア・医療
- 日本
-

中国におけるロボット産業の進展
- WTR No441(2026年1月号)
- ロボット
- 中国
-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜
- WTR No441(2026年1月号)
- ポイントビジネス
- 日本
- 経済
- 金融