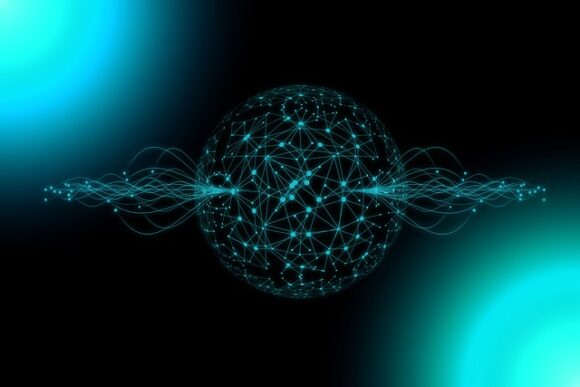令和3年(2021年)、新年に想うこと ~情報通信事業・サービスの課題

(本レポートは「InfoCom T&S World Trend Report」2021年1月号に掲載されております。本文内の「昨年」は2020年、「今年」の表記は20201年といたします)
新年おめでとうございます。令和3年(2021年)を迎えて、新しい年の意気込みに燃えておられることと思います。恒例ですが、干支では今年は辛丑(かのとうし)になります。干支占いを信じる訳ではありませんが、辛丑の年は、辛く大変な出来事を乗り越えて全く異なる段階に移る年、協力して結び付きが強くなる年だそうです。昨年発生したCOVID-19の大流行から、はや1年、本当に重苦しく社会経済が落ち込んだ1年でした。今年こそ辛く苦しい出来事を克服し、その上で元に戻るのではなく新しい異なるステージに移る年、自助・共助・公助で結び付きを強める年、即ち紐(糸へんに丑・うし)=絆を深める年になると想定しています。
そこで新年のお許しを頂いて、私なりの今後の情報通信事業分野の課題を述べてみたいと思います。干支占いに従って、これまでとは違う新しい異なるステージを見定め、結び付き・協力を深める動きを中心に探ってみます。まず時間的な区分から、それぞれ2項目ずつ取り上げます。第1の短期的(1年以内)な課題は、携帯料金値下げとリモートワークの定着、第2の中期的(3~4年程度)課題は通信インフラからサービスインフラへの大変貌とNTTグループの再編、最後に長期的(5年超)な課題として6GとIOWNの融合・一体化とグローバル競争の生き残りの6項目について述べます。新年の余興と受け止め願います。
第1の短期の課題としては、既に各社で動き始めている携帯料金値下げに注目しています。消費者・利用者の立場としては料金水準が低く、品質が高いことが何より望ましく、値下げそれ自体は大歓迎です。しかし他方それによって回線速度や接続率などの通信品質が下がるのは、最も避けてもらいたいと思います。各種のアンケートや民間の調査会社のレポートをまとめてみると、日本のモバイル通信サービスの水準は料金は中位で品質は高位、利用者の満足度は比較的高く大きな不満にはなっていないと認識しています。つまり料金水準を含めてサービスについてはマクロ的な取り組みではなく、“最も重要なのは、平均的な料金や大まかな指標を見ることではなく、個々の携帯利用者について実際の契約、通話、データ通信などの履歴の詳細なミクロデータを収集し分析することである”(2020.10.2(金)日経新聞Opinion・エコノミスト360°視点、渡辺安虎 東大教授)との指摘のように、まさに神は細部に宿るということでしょう。単純な儲け過ぎ批判による政治介入は自由主義経済、市場経済に反するので、注意を要します。日本経済の国際競争力回復を目指してROEの向上に取り組んで来た大きな流れに逆風を浴びせてはなりません。利益率は世界水準、グローバルスタンダードで判定するのがベターでしょう。いずれにせよ、料金値下げの問題は水準というよりむしろ、どの階層のどのような利用方法を対象にするのかの問題となるので、次の短期的課題であるリモートワークの定着と大きく関連してきます。リモートワークはコロナ禍で普及拡大しましたので企業経営面でも雇用施策として各社において制度化が進められています。一部は元に戻ることでしょうが全体として社会に定着し始めています。こうなると労働の質や生産性をどう高めていくのかが新しい課題となりますので、情報通信事業・サービスに求めるものも従来とは違ってくることでしょう。料金水準はもとより、新しい形のサービスとセットで取り組まなければなりません。光回線とのサービス統合、各種プロバイダーサービスとの連携や融合が求められます。ビジネスだけでなく、教育面でもリモート授業に適した料金・サービスが必要になっています。出席や質問などの記録や授業態度の評価にまで及ぶサポートを可能とするサービスプロバイダーが必要なのです。
第2の中期的課題は前述の短期的課題の延長上にあるので簡単に述べます。情報通信事業・サービスはこれからは通信インフラ中心からサービスインフラ中心に大変貌を遂げていきます。設備・ハードからサービス・ソフトへの変化であると同時にそれが社会経済のインフラとなって一定の規制下に実装されることを意味しています。既に欧米では競争法の網がかかり始めていて、いわゆるGAFAといえども完全に自由な企業行動には制約がかかるようになっています。だからこそ、通信インフラに過度に拘泥することなくサービスインフラを目指して自らを変えていくべき時です。そのためには5Gについては基地局のエリア展開だけでなく、5Gコアネットワークの構築を急ぎ進める必要があります。今後は進展著しいコンピューターパワーを取り込んでクラウド・AIと一体となった5Gプラットフォームの確立が求められます。それこそ5Gがサービスインフラとなるための第一歩です。過去のiモードの時には、いわゆる“勝手サイト”と扱って自己規制していた歴史があるだけに、通信インフラ事業にサービスインフラを加えることは事業者の企業文化や技術動向にまで及ぶ大きな転換なので重大事です。同様にNTTドコモの完全子会社化とNTTグループ内での再編にもこの流れは影響してきますので要注意です。NTTドコモが発足して30年近く経ちますが、前半の拡張期の自立精神が後半に次第に乏しくなっていく姿が見えていましたので、新たな企業文化の変革が前提となります。新体制はもとより、NTTグループとしてそうした新しい企業文化創造を目指す再編を図るべきです。当然、新しいサービスインフラを構築することがその道筋となります。NTTグループだけでなく、長年の日本の情報通信事業とサービスの課題となっていた移動通信と固定通信、モバイルと光ファイバーのサービス融合を進める時です。NTTグループにサービス分離を課している現在の日本の規制はグローバルから見て周回遅れの状況に見えます。
最後に5年超の長期的課題を考えてみます。先のことは不透明なところが多くて難しいのですが、まずは研究開発と標準化の領域で6GとIOWNの融合・一体化を図る必要がありそうです。NTTドコモは政府の通信産業政策の下、独立した会社として無線分野の研究開発を国内的にも国際的にも独自に進めてきましたし、標準化活動にも自立して取り組んできましたので、NTT持株会社の研究開発体制とは協力関係にはあるものの、資金的にも人的にも一線を画してきたところです。こうした距離感は独立心、競争心という大切なものを生み出していて事業の現場に近い関係を保ってきましたので、グループ全体の研究開発目標である6GとIOWNに関して事業と実証的に結び付けて融合・一体化を進めないと国際的な標準化の分野で後れを取ることになりかねません。ましてや、しばしば見られる研究開発分野における主導権争い、人材と資金の囲い込みに陥ることのないように研究開発の再編成にも挑戦しなければなりません。国際標準化の世界で発言力・影響力を高めて具体的な知的財産を構成していかないと次世代の通信インフラやサービスインフラにおいてグローバルな主導権は確保できず、ハード/ソフトの両面で日本の情報通信産業の復活を果たすことはできないでしょう。GAFAに伍してグローバルで生き残るためには、中期的にサービスインフラを構築し市場構造を変革して世界に向けて発信していくことと長期的に研究開発で標準化を主導していくことが王道です。NTTグループと関係業界の協調に期待しています。
※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部無料で公開しているものです。
調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。
ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード
平田 正之の記事
関連記事
-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに
- 5G/6G
- AI・人工知能
- ICR Insight
- WTR No441(2026年1月号)
- モバイル通信事業者(国内)
- モバイル通信事業者(海外)
-

中国におけるロボット産業の進展
- WTR No441(2026年1月号)
- ロボット
- 中国
-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜
- WTR No441(2026年1月号)
- ポイントビジネス
- 日本
- 経済
- 金融
-

アバターと立法〜サイバネティック・アバターの法律問題季刊連載第二期第3回
- WTR No441(2026年1月号)
- メタバース
- 仮想空間
-
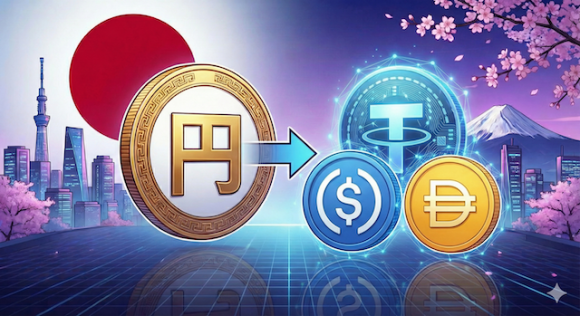
「信頼」と「ポイント文化」が融合する: 日本型ステーブルコインが描く資金決済の未来
- WTR No440(2025年12月号)
- 暗号通貨
InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧
ランキング
- 最新
- 週間
- 月間
- 総合