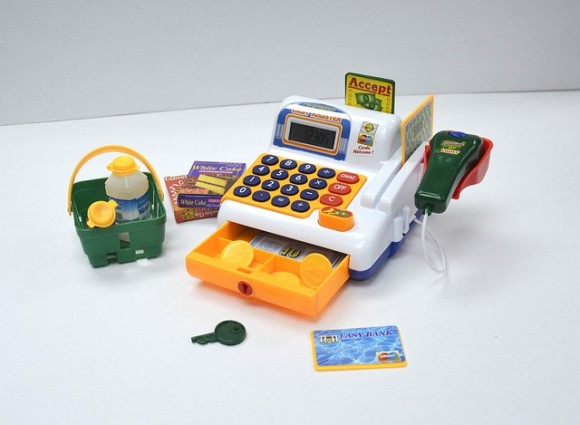ICT雑感:真のモビリティ実現に向けて:ワイヤレス給電の昔と今
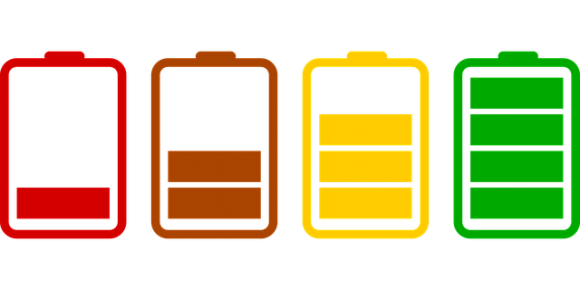
最近秋葉原の電気街に行ってみた。自宅でAndroidスマートフォンを充電するためのケーブル、いわゆるMicro USBケーブルを購入しようと思ったためだ。店頭には様々なケーブルが比較的安価に売られていて、見ているだけでも楽しい。中にはAndroidスマートフォンとiPhoneの双方に使えるように、ケーブルの端が二股のようになっているものや、アダプターを付け外しすることで、AndroidスマートフォンとiPhoneの双方に対応できるようにしているものなど工夫がみられるものもある。
「充電」という名の制約
これを読まれている方もそう思われるかもしれないが、スマートフォンの充電というのはやや面倒だ。全く使わない時間、というのは寝ているときくらいなので、起きている時間はなるべく自分の近くに置いておきたい。しかし、大して広くない家の中であっても、ただ、置いておくだけならできるだけ充電にあてたいと思うと、ケーブルを持ち歩くか、充電ができそうな場所にあらかじめケーブルをセットしておくことになる。
おそらくオフィスであっても、最近ではデスクの上で仕事をしている間は充電ケーブルをスマートフォンに挿しておく人が多いのではないだろうか。筆者の職場はICT系の研究をしているところなので、スマートフォンを持っていない人を探す方が難しく、ほぼ全員のデスクの上に充電ケーブルがセットされている。Android用のUSBケーブルとiPhone用のLightningケーブルの2種類があるデスクも散見される。
その他、自分のデスク上にあるケーブルはというと、PCとキーボードをつなぐケーブル、PCとマウスをつなぐケーブル、PCの電力ケーブル、ビジネスホンの電源ケーブルなどがある。ビジネスホンについては、つい2年ほど前にコードレス型に更改され、電話機と受話器をつないでいるケーブルは存在しなくなった。また、キーボードやマウスもワイヤレス化することは可能である。
こうしてみると、非ケーブル化、つまりワイヤレス化はだいぶ進んできているものの、今一歩進んでいないのが電力関係のように見える。もちろん、PCもデスクトップをラップトップに変更すれば、基本的にはワイヤレス対応になり、モビリティは高まることになる。ただし、コードレスビジネスホンも、ラップトップも、スマートフォンも、タブレットも、ワイヤレスなのは、「バッテリーが保つ間だけ」である。電力が供給されなくなったこれらのデバイスは全く役に立たないガラクタになってしまう。
通勤など、オフィスの外では、スマートフォンやタブレットの電源が切れたときのために、バッテリーを携帯している方も少なくないであろう。カフェなどでは充電用の電源を設置してあるところもあるが、移動中となると、多くの場合は自分の持つバッテリーにより「自己解決」となっているのがほとんどではなかろうか。
本当の意味での「モビリティ」を実現するには、通信にしろ、電力にしろ、ワイヤレスになり、「ケーブル」から自由になる、ということが必要だろう。モバイル通信がこれだけ普及した世の中で、最後の一歩を詰めるのは電力になりそうだ。電力供給がワイヤレス化されたときに、真のモビリティが実現されることになるだろう。
ワイヤレス給電の昔と今
実は、このワイヤレス給電の考え自体はかなり古くから存在するものである。オーストリア人電気技師Nikola Teslaは、1901年に米国ニューヨークのロングアイランドに「ウォーデンクリフ・タワー (Wardenclyffe Tower)」という無線送信塔の設立を始めた。Teslaは発明王Edisonと「電流戦争 (The War of Current)[1]」を戦った人物としても知られている。Teslaは自らが構築した無線による電力電送システムを「世界システム (Tesla World System)」と呼び、電波を使った無線送電についての実験を行った。Teslaは150kHzという長波領域の電波を使用したため、電波拡散等により十分な電力が得られず、実験は失敗だったと評されている。
Teslaの実験から100年以上が過ぎ、ワイヤレス給電は実用化への道すじを付けてきている。例えばWireless Power Consortium (WPC) はワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)」を2010年7月に策定した。これはワイヤレス給電方式でも 「電磁誘導方式[2]」という比較的古くからある方式を採用しており、対応するスマートフォンや充電器も製品化されているので、ご覧になった方もおられるであろう。
Qiの他、MITが開発した磁界共鳴方式[3]の技術を使った「WiTricity(ワイトリシティ)」は、2013年トヨタ自動車がライセンス契約を締結、2016年5月には、医療機器メーカーのGreatbatch社がWiTricity社の知的財産使用権を得たと報じられ、埋め込み型などの医療機器への展開も進められている。
さらに電波を活用してワイヤレス給電を実現する技術も開発が進められており、2.4GHz等の免許不要電波帯域を活用するOssia社の「Cota」や、Energous社の「WattUp」、超音波を活用した方式の開発を進めているuBeam[4]などが存在している。
電波方式の中には、Wi-Fiを活用する、というもの (PoWiFi : Power over Wi-Fi) も出てきた。米国ワシントン大学の研究者チームが2015年5月に発表したもので、既成のWi-Fiルーターを活用し、通信と電力伝送を同時にできるようにしたものだ。実験では、Wi-Fiルーターから5メートルほどの距離にある監視用小型カメラに電力を供給することなどに成功したとしている。ただし、現時点では電子機器のそばに受信用アンテナを設置する必要があるため、実用化にはまだ時間がかかるだろう。
以上で述べたように、我々のデスクから電力ケーブルをなくすワイヤレス給電の技術は進められてきているが、真のモビリティを実現するのにより貢献するのは電波方式であろうと思う。それは電気を送信する機器(送電機)と電気を受け取る機器(受電機)との距離は、電波を使った方式の方が長く取れる可能性が高く、自由度が高まるからである。
一方で、電波方式を筆頭に、ワイヤレス給電では送信できる電力量の制限や安全性等多くの解決すべき課題があるのが現状である。今後、真のモビリティの実現に向け、各種のワイヤレス給電技術がさらに進展していくことが期待される。次のICT分野のブレークスルーは電力分野からもたらされるのかもしれないと期待しつつ、動向を見守っていきたい。
[1] 1900年代初頭、送配電において直流方式を主張するEdisonと、交流方式を主張するTeslaおよびWestinghouseとの間で争われた一連の出来事を示す言葉。現在では一般的に交流が送配電の主流となっている。
[2] 給電側のコイルに交流電流を流し、受電側のコイルに磁束を発生させることで受電側に電流を流す方式。原理的にはコードレス電話や電気シェーバーなどで以前より利用されている方式である。
[3] 給電側のコイルに電流を流すことで発生した磁場の振動が、受電側に伝わり(共鳴し)、受電側に電流を流す方式。電磁誘導方式に比べると電送距離を長く取れるというメリットがあり、EV(電気自動車)の充電用電力電送方式として開発が進められている。
[4] 超音波を介して電力電送を実現する技術を開発する企業。2014年8月にプロトタイプを発表。しかし、2016年5月、同社の元エンジニアが同社技術の実現性に関する疑問をブログで公表するという出来事が起こった。
※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部無料で公開しているものです。
調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。
ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード
滝田 辰夫(退職)の記事
関連記事
-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上
- WTR No441(2026年1月号)
- ヘルスケア・医療
- 日本
-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる
- WTR No441(2026年1月号)
- オーストラリア
- 世界の街角から
-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに
- 5G/6G
- AI・人工知能
- ICR Insight
- WTR No441(2026年1月号)
- モバイル通信事業者(国内)
- モバイル通信事業者(海外)
-

中国におけるロボット産業の進展
- WTR No441(2026年1月号)
- ロボット
- 中国
-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜
- WTR No441(2026年1月号)
- ポイントビジネス
- 日本
- 経済
- 金融
InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧
ランキング
- 最新
- 週間
- 月間
- 総合