ポイントビジネスとスマートフォン

ポイントプログラムは従来、顧客の囲い込みを目的として、主に流通・小売業やサービス業において、専用カードや会員証を発行し、購入額に応じて一定量のポイントが蓄積すると自社商品・サービスの割引特典等が受けられるといったスタイルで、日本では広く受け入れられている。
一方でTポイント、ポンタに代表されるポイントプログラムのように、自社提供サービスとは直接関係なく、通貨のごとく流通し特定の経済圏を形成しているものもある。また、クレジットカードを始め、様々な決済と連動したものもあることはご存じのとおりである。ポイントそのものは数値でしかないため、ICTとの親和性は非常に高く、ここにきてスマートフォンの普及によるライフスタイルの変化に応じて、様々な発展とビジネスチャンスが垣間見られるようになっている。それらを紹介しつつ、今後のポイントビジネスの方向性について考察したい。
TポイントとYahoo!の連携
オンラインとオフライン融合の先駆け
2013年、Tポイントプログラムを提供するCCC(カルチュア・コンビニエンス・クラブ)はYahoo! Japanのポイントプログラムとの連携を発表。実際には、Yahoo! Japanで利用されていたポイントをTポイントとして蓄積できるようになるというものだった。
それまでは、実店舗のポイントは実店舗で、オンラインのポイントはオンラインで利用というのが一般的であったが、ポイントプログラム大手とポータルサービス大手が提携することで、一挙にその垣根が取り払われた。
同様な取り組みとして、楽天が実店舗でも楽天スーパーポイントが蓄積できるプログラムを提供開始し、ネットとリアルの融合を図ることとなった。
ネットの特性をポイントに
ネットはアクションでポイント
ポイント付与の観点では、オンラインサービスと実店舗ではそれぞれ異なる特徴が見られる。
実店舗におけるポイント付与の条件は購入金額の1%相当といった具合にあくまで購入がベースであるが、オンラインサービスの場合は購入という行為に限定されない。楽天市場のようなECサイトでは購入額に応じたポイント付与が行われていることは明らかであるが、それ以外でも、フリーミアムのビジネスモデルを提供しているところでは、違った形でポイントが提供されていることはご承知のとおりだろう。ポイントが通貨と同等と考えれば、その流通の容易さを利用し、ユーザーが何らかのアクションを行うことに対して付与されることが多々ある。例えば、投稿サイトでユーザーが情報提供することに対する謝礼としての付与。また、一方では面倒さを受け入れるためのインセンティブとして、例えば一定時間動画を視聴することを条件にポイントを付与する等もある。また、スマートフォンの場合だと、特定のアプリをダウンロードすることを条件にポイントを付与する、といったものもあることはご存じだろう。
つまり、ネットを起点としたポイントサービスはサービス提供者との明確な商取引が存在しない状態で、ユーザーは何らかのアクションをすることでポイントの入手が可能となっている。
スマホなら実際活動量もポイントに
人間の活動量でポイント付与
以前からも健康促進プログラムとして、万歩計のデータをPCに移行し、達成した歩数に応じて、ポイントを付与するといった取り組みは随所で行われていた。
そして近年、複数のセンサーと通信機能が融合したスマートフォンが普及したことにより、そうした取り組みへのハードルは一気に下がった。
「TSUTAYAのスマホ」のコピーで売り出している、MVNO事業者トーンモバイル株式会社は、加入者拡大策の一つにその仕組みを活用している。

【図1】トーンが提供するライフログアプリ
(出典:トーンモバイル ホームページ)
トーンモバイルは2016年の2月より、自社スマートフォンユーザーに対して、内蔵アプリ「ライフログ」を利用し、1日の活動量に応じてTポイントを付与するサービスを開始している。
ポイント付与の条件は「自社のスマートフォンを持って1日に8,000歩以上歩き、活動量が20分を超えた場合にはTポイントを1ポイント付与」するというもの。
確かに、健康促進のため、歩くきっかけにはなりうるものの、2015年12月9日に厚生労働省が発表した「平成26年国民健康・栄養調査結果の概要」によると、成人の1日当たりの平均歩数は男性7,043歩、女性6,015歩となっている。つまり、成人男子の日常の歩行数でもTポイント付与されるまでに満たないことになる。
また、付与されたとしても換金率を考えると、1日1円程度では、既存のスマートフォンユーザーにとっては、このサービスをきっかけにTONEモバイルのMVNOサービスに乗り換えるインセンティブとしては少々辛いものがある。
地方と高齢者をターゲットに
「使ってみる」のきっかけに
その一方で、健康に対する意識が高いが、所得が限られ、必要性の観点からこれまでスマートフォンを持ったことがなかったユーザー層にとっては、違った意味合いを持つ。つまり、高齢者層をターゲットとした場合、親和性が高いポイントサービスとなる。
ふるさとスマホ株式会社
そこで2015年7月28日、CCCは「ふるさとスマホ株式会社」を設立。この会社はスマートフォンを利用して、高齢者サポート・健康増進など、ふるさと(地域)活性を実現することを目的とし、「自治体スマホ連絡協議会」と連携し事業を進めている。
この協議会は富山県南砺市が発起人となり、全国の有志自治体で組織されている。この協議会には、自治体共通の地域課題についてスマートフォンを利活用することで、解決する方法を検討するとともに、民間企業との連携を促進し、地域課題を解決するための取り組みを実践することを目指し、71の自治体(2016年3月現在)が参加している。
2015年11月には同協議会メンバーの群馬県下仁田町、ふるさとスマホ社、Tポイントジャパンの3者で協定を結んでいる。
下仁田町での狙い
トーンモバイル社のスマートフォンを配布
下仁田町における具体的な施策としては以下のものがあり、そこにスマートフォンとTポイントの組み合わせがユーザー側にも自治体側にもメリットを創出するものとして、しっかりと要点を占めていることが見て取れる。
- スマートフォンの全戸配布(全3,413戸)を前提に、実験モデル地区(約500戸)へ先行配布
- 自治体から各戸への連絡手段の確保
- 子供や高齢者の見守りネットワークの創出
- 歩数計アプリなどによる健康増進の推進
- 買い物難民など高齢者の問題の解決
- 世界遺産の富岡製糸場などでの観光活用
- 初期導入端末はモニターとして提供され、アフターサポートやスマホ活用体験会も提供
- 実証実験での月額利用料は下仁田町側が負担
上記に加えて、ふるさとスマホ社およびTポイントジャパンより、下記の施策が提案されている。
- 道の駅や商店街の活性化とマーケティング
- Tポイント提携企業との連携
- 歩数に換算したTポイントでの健康ポイント付与
- ふるさとスマホが開発するアプリの無料提供
自治体スマホ連絡協議会においてはトーンモバイル社の利用が推奨されており、当然ながらここで配賦されるスマートフォンは同社のものとなっている。
横展開で一挙に高齢者層を獲得する可能性
この下仁田町での取り組みが成功した場合、トーンモバイル社、およびTポイントを提供するCCCにとっては自治体を通じた横展開はもちろん、高齢者にスマートフォン、ポイントといった新しいシステムを受け入れてもらうことによって、概して保守的な高齢者層を安定した顧客層として、全国的に新たに獲得することが可能となる。
注目される今後の動向
現在、モバイル事業者によるポイントプログラムはソフトバンクが自社ポイントをTポイント化することに積極的である一方で、auとNTTドコモはそれぞれ、au Walletポイント、dポイントといった新たな決済を含めた自社ポイント経済圏の構築を進めている。
今後のポイントを巡る動向に注目したい。
※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部無料で公開しているものです。
調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。
ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード
前川 純一(退職)の記事
関連記事
-
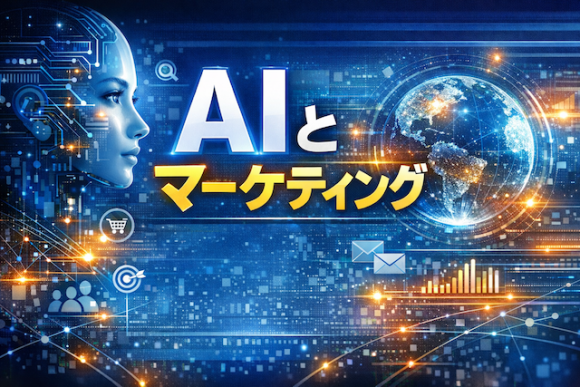
AIとマーケティング
- AI・人工知能
- ICR Insight
- WTR No442(2026年2月号)
- 生成AI
-

ICTが変える授業の形 ~複線型授業とICT
- GIGAスクール構想
- ICT利活用
- WTR No442(2026年2月号)
- 教育
- 日本
-

世界の街角から:真夏の海に浮かぶ"立体都市" ~長崎・軍艦島、半世紀後の生活の輪郭
- WTR No442(2026年2月号)
- 世界の街角から
- 日本
-

ソブリンAIを巡る各国の動向 ~制度・投資・地域連携に見る多様なアプローチ~
- AI・人工知能
- WTR No442(2026年2月号)
- 生成AI
-

超高齢社会における介護DXの可能性と課題
- DX(デジタルトランスフォーメーション)
- WTR No442(2026年2月号)
- 介護
- 医療
- 日本
- 福祉
ICT利活用 年月別レポート一覧
ランキング
- 最新
- 週間
- 月間
- 総合








