21世紀初頭、もう15年以上前だが、ユビキタスという言葉が流行っていた。聞いたことがない若い世代も多いかもしれないが、言葉自体はubiquitous、すなわち、遍在する、という意味である。パロアルト研究所のMark Weiser博士が、1991年に書いたThe Computer for the 21st Centuryという論文の中でUbiquitous Computingを提唱し、21世紀にはあらゆるものにコンピュータが組み込まれそれがネットワークでつながる、と予想した。
博士自身は1999年に他界してしまい見ることはかなわなかったが、21世紀になり彼の書いた世界が現実となった。多くの人がスマートフォンを持ち歩き、コンピュータを意識しなくてもIOTによってあらゆるものがネットワークにつながり、AIが生活に入り込み始めている。彼の論文は驚くほど正確に四半世紀先の現代社会を見抜いていた。
当たり前になったがゆえに、ユビキタスは死語になってしまったのだろう。
ただ、本当の“ユビキタス社会“になるにはまだ越えなければならない壁があると思う。
簡単な例を書くと、例えば、外出先で、しばらく連絡していない古い友人に連絡を取る必要が出てきたことを想像してほしい。整理整頓のしっかりした人なら、前もって友人の連絡先が書かれた自宅のPCにある住所録とスマートフォンの住所録と連携させ、外出先でも問題なくその友人に連絡を取ることができるだろう。だが、整理整頓が得意でない人もいる。
外出先からスマートフォンを使って自宅のPCを起動し、そのPCにアクセスして住所録を確認することは、大したお金をかけなくても可能である。ただ、そのためには、事前にかなり面倒な設定をたくさんしなければいけない。この“設定”が曲者で自動化されていないのだ。
“Hey Siri、自宅のPCの住所録に書かれた〇〇さんの電話番号を教えて”と頼んだら、すぐに教えてくれるというようにならないと、本当に“つながった”とは言えない。
そうなるためには何が必要なのか。一番手っ取り早いのは、自宅のPCの記憶装置をなくしてクラウド化することだろう。そうすれば単純にクラウドにアクセスして情報は取れる。しかし、それでも、セキュリティは大丈夫?、クラウドと連携しなきゃ、ログインIDとPWを入力して、等々面倒なことはなくならない。
いっそのこと、デバイスや情報資産の所有者の定義を標準化してその公開鍵を使うことでログインIDを無くしてしまい、その所有者情報に基づいて秘密鍵を持つエージェント(ネットワークコントローラーやAI)が自由にアクセスできるようにすれば、この問題は解決するのではなかろうか。同時に、増え続けるデバイスや情報資産に個別にIDとパスワードを設定したり、パスワード管理に頭を悩ませたり、パスワードの流出による情報漏洩を心配したりすることもなくなるはずだ。
Weiser博士は上記の論文の中で、ユビキタス社会では個人情報の取り扱いにも注意が必要だと警鐘を鳴らしている。そして、“デジタルペンネーム”を使えば個人情報を送信する必要はなくなる、と書いている。”パスワード“が”ユビキタス“のように死語になるのは何年後のことなのだろうか。
調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。
ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード
出口 健(転出済み)の記事
関連記事
-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上
- WTR No441(2026年1月号)
- ヘルスケア・医療
- 日本
-

中国におけるロボット産業の進展
- WTR No441(2026年1月号)
- ロボット
- 中国
-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜
- WTR No441(2026年1月号)
- ポイントビジネス
- 日本
- 経済
- 金融
-
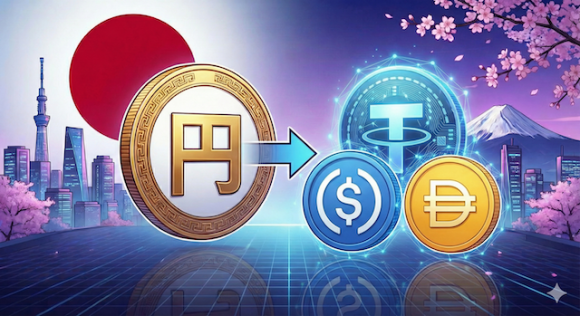
「信頼」と「ポイント文化」が融合する: 日本型ステーブルコインが描く資金決済の未来
- WTR No440(2025年12月号)
- 暗号通貨
-

眠れる資産から始まる未来 ~循環価値の再発見
- ICR Insight
- WTR No438(2025年10月号)
- 日本
- 環境
ICR View 年月別レポート一覧
ランキング
- 最新
- 週間
- 月間
- 総合









