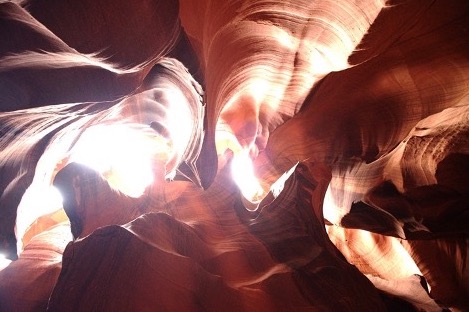ICT雑感:コインの行方

日本におけるキャッシュレス比率は約20%であり、主要各国の40~60%と比較するといまだに低い水準だが(出所:経産省)、令和元年に閣議決定された「成長戦略フォローアップ」では2025年までに40%程度、将来的には世界最高水準の80%を目指すとしている。そのための様々な促進策も実施され、今年の6月まで実施されていたキャッシュレス・ポイント還元事業は、ポイント還元というダイレクトな魅力の効果により、利用者の拡大につながった。また店舗側の仕組みも、簡易で安価な端末と無線ネットワークでも対応できるという技術の進化により、商店街の小さなお店等でも簡単に導入できるようになったのは大きな進歩と言える。
ちょうどタイミングが重なったコロナ対策として、決済にかかる時間が短くて済み、お金の受け渡しという物理的な接触をさける意味から推奨されたこともキャッシュレス化の推進につながったのは間違いない。
コロナ禍においては、硬貨や紙幣などにもウイルスが付着する可能性があると、流通への懸念も取り沙汰され、なんだか少し肩身が狭くなったコイン達だが、その歴史は古く、現存する最古のコインは紀元前670年頃、現在のトルコのあたりにあったリュディアのエレクトロン貨。もっと古くギリシャのあたりで紀元前10世紀頃から造られていたという説もある。日本における最古の硬貨も所説あるが、683年の富本銭と言われており、昔習った和同開珎より古いというのが通説になっている。コインは長年にわたり、人類の経済システムの根幹として存在し、世界中で様々なものが造られ流通してきた。素材もデザインも様々で、美しいコイン達は時代ごとの文化を表わしてもいる。コレクターも多く、通貨としての価値以上の価値を見出され、取引されることも。
私はコレクターというほどではないが、2種類のコインを集めている。
一つは米国の25セント(Quarter)コイン。通常のコインは表がジョージ・ワシントンで裏が双頭鷲となっているが、1999年からStatehood Quarterという州ごとのデザインが裏面に入ったコインが造られているのはご存じだろうか? 意外と知られていないが通常に流通しているので、皆さんのお手元にもあるかも。NYなら自由の女神、テキサスならローンスター、フロリダはスペースシャトルなど、その州を表わす美しい絵柄となっており楽しめる。こちらは一時期、足繁く通っていたシリコンバレーのパートナー達の協力もあり、残り6州まで集まったが、2010年からNational Park Quarterというバージョンも発行され、2021年まで順次発行されるため、こちらまで手を出すとまだまだ先は長くなりそう。
もう一つはユーロコイン。現在、EU加盟国は英国が離脱したため27カ国。そのうち、19カ国がユーロ通貨を採用しており、その他、非EU加盟国のバチカンなど4カ国がユーロを導入しているため、23カ国が使用している通貨となる。コインは1、2、5、10、20、50ユーロセント、1、2ユーロの8種類となるが、片面は統一デザインで、反対面は各国ごとにデザインが異なる。国によってはコインの種類ごとにすべてデザインを変えており、複数のシリーズを発行している国もあるので、通常コインで300種類近く。記念コインも入れると500種類以上となり、これらをすべて集めるのは至難の業。大きなユーロ圏として通貨が流通しているので、その国に行ったからと言って、必ずその国の絵柄のコインが手に入るわけではなく、米国Quarterよりはるかに難易度が高い。また流通量の少ない国のものがたまたま自分の手元に回ってくるのは奇跡のような確率となる。かなり集めた方だと思うが、それでもまだ7割弱というところ。
そういうコレクターのために、欧州の街のコインショップでは珍しい国のものをセットにして販売している所がある。ある時、出張でアムステルダムの街中を歩いていると、私が欲しかったリトアニアセットを発見! 当然、通常通貨としての額よりは高く販売されているが、さほど無茶な値段でもないので大人買いしようとしたところ、同行していた部下達から「それはズルい! 自力で集めないのはらしくない!」と許可されず、泣く泣く諦めた。しかしそのおかげで後にバルト三国を回る旅行を実現することができ、素敵な旅の思い出とともに美しいコインも手に入れることができたのは、彼らに感謝しないといけないのかもしれない。
キャッシュレスは今後ますます進んでいくことが予想されるが、何世紀にもわたり、我々の生活の中に欠かせない存在であったコイン達はいずれ消滅してしまうのだろうか? それともコレクションアイテムとしてのみ流通するようになるのか?
あまりにも身近で意識して見る機会は少ないコインだが、長い歴史と文化を刻んだ存在をたまには眺めてみるのもいいのかもしれない。特に海外旅行がままならない状況下においては、いつかまたこのコレクションのフルコンプリートを目指して旅に出ることができる日を楽しみにしながら...
※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部無料で公開しているものです。
調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。
ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード
船本 道子の記事
関連記事
-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上
- WTR No441(2026年1月号)
- ヘルスケア・医療
- 日本
-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる
- WTR No441(2026年1月号)
- オーストラリア
- 世界の街角から
-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに
- 5G/6G
- AI・人工知能
- ICR Insight
- WTR No441(2026年1月号)
- モバイル通信事業者(国内)
- モバイル通信事業者(海外)
-

中国におけるロボット産業の進展
- WTR No441(2026年1月号)
- ロボット
- 中国
-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜
- WTR No441(2026年1月号)
- ポイントビジネス
- 日本
- 経済
- 金融
InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧
ランキング
- 最新
- 週間
- 月間
- 総合