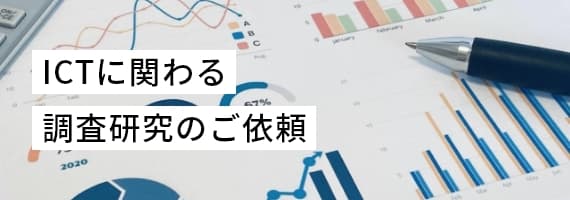オーストリアの首都ウィーンといえば、ハイドン、シュトラウス、モーツァルト、ベートーヴェン、シューベルト、マーラー――多くの音楽の巨匠達が活躍し、世界最高峰といわれるウィーン管弦楽団を擁する「音楽の都」というイメージを持つ人がほとんどだろう。しかし、ハプスブルグ家のお膝元として発展したウィーンは、建築史に残る数々の有名建築を楽しめる「建築の都」でもある。今回は、そんな名建築を探しながら古都を巡る「建築散歩」を振り返りつつ、ウィーンの都市としての魅力を紹介したい。
まずはリンク・シュトラッセで欧州建築史を学ぶ
ウィーンの都市としての構成は、1850年代に始まったフランツ・ヨーゼフ1世による街づくりに遡る。彼は、旧市街を囲んでいた城壁をすべて取り払い、その跡地にリンク・シュトラッセと呼ばれる環状大通りを整備した。このリンク・シュトラッセ、略してリンクは、東京でいえば、皇居内堀通りのイメージである。
さらに、そのリンクに沿って、ネオ・ゴシック、ネオ・ルネサンス、ネオ・バロックなどの複数の様式に基づいた公共施設が建設された。それらは、19世紀半ばから約50年の間に建設されたが、個々の公共的な機能の理念に従って、建築様式が選ばれて設計された。建築学的には「歴史主義」というらしいが、細かい様式の定義は横において、それぞれの建物の違いを感じてみよう。
例えば、ウィーン市庁舎には、中世の「都市の自治」という理念に基づき、その理念が最も盛んだった時代のゴシック様式が選ばれ、美しい透かし彫りのような尖塔がトレードマークとなっている。国会議事堂は、民主主義発祥の地であるギリシャの様式で、アテネの神殿のような堂々とした趣がある。また、ハプスブルグ家が代々収集した貴重なコレクションを収める美術史美術館と自然史博物館、そしてウィーン大学の校舎には、芸術と自然科学の殿堂として、ルネサンス様式が選ばれた。演劇のためのブルグ劇場は、演劇が文化として広く普及した時代を考慮し、バロック様式となっている。
どのガイドブックでも、ウィーンを初めて訪れたら、まずトラムに乗って、リンクを一周してみることを勧めているが、そうすると、時系列的とはならないが、欧州建築の歴史を辿ることにもなる。それぞれは異なる様式だが、ある建築の専門家は、なぜかリンク沿いに立つ建物にバラバラ感はなく、調和し共存していて、それがウィーンの魅力だと書いている。
旧市街でハプスブルグ帝国の栄華を感じる
次に向かいたいのは、リンクに囲まれた旧市街。リンクから内側中央に向かって伸びる通りは、旧市街の中心にあり、ウィーンのシンボルともいえる聖シュテファン寺院に通じている。12世紀半ばにロマネスク様式で建設、その後14世紀に一部を除いてゴシック様式で建て替えられ、その塔は旧市街のどこからでも見えるため、観光客の迷子防止に一役買っている。北塔にはエレベーターが設置され、屋上からウィーンの街並みが一望でき、カラフルな幾何学模様の屋根瓦を間近に見ることもできる(写真1)。

【写真1】ウィーンのシンボル「聖シュテファン寺院」
(出典:文中掲載の写真はすべて筆者撮影)
聖シュテファン寺院を起点に、ケルンストナ―・シュトラッセや、グラーベンといった多くの人々が行き交う大通りが伸びるが、大通りから一歩入ると、趣のある石畳の小路が入り組んでおり、小路に沿って多くの建物が立ち並ぶ。歴史的な由来がある建物には赤と白の旗の付いた説明版が掲示されているが、歴史上の人物が住んでいた、あるいは人生の終焉を迎えた建物、名曲が生まれた建物等々、数多くある。小路にも歴史的に由来のある名前が付けられており、繁栄の往時がしのばれる。また、パバラッチェンと呼ばれるバルコニー付きの中庭に面した部屋がギャラリー等で開放されていたり、1階部分に通り抜け通路がある建物もたくさんあったりして、建物の内側を垣間見ることも楽しみである(写真2、3)。

【写真2】路地からさらに建物の中へ。パバラッチェンから通り抜けができるドゥルヒハウス

【写真3】旧市街中央には、地下に大駐車場があり、景観を保ちながら、観光需要にも対応
アール・ヌーヴォー建築の宝庫を堪能する
ウィーンでは19世紀末、フランスから始まった芸術運動「アール・ヌーヴォー」を受けて、新たな芸術を模索した多くの芸術家が活躍し、日本でも人気の高いグスタフ・クリムト、エゴン・シーレらによる革新的な作品が生まれた。彼らは、旧来の美術組合から離脱して、オーストリア芸術家協会、通称「分離派」を結成するが、その創立には多くの建築家も参加し、彼らが中心となって新しい建築の様式やスタイルが生まれた。このように建築・工芸の専門家が中心になって始まったことで、その影響は絵画・彫刻だけでなく、建物や家具、インテリア、舞台美術の分野にも及び、より生活に身近で影響の大きい芸術運動となったことが、ウィーン分離派の最大の特徴という。初代会長のクリムトも工芸美術大学の出身で、もともとは舞台芸術に携わっていた。
その分離派の作品展示館として建設されたのが分離派会館である。最寄りの地下鉄カールスプラッツ駅を出ると、その横に分離派の主要メンバー、建築家オットー・ワーグナー設計の、緑の鉄骨に細かい金色の装飾が施された美術品のような旧駅舎がある(写真4)。

【写真4】ワーグナーの博物館となっている「カールスプラッツ旧駅舎」
その弟子、ヨゼフ・オルブリヒが建築した分離派会館は、金色に輝く6,000枚の月桂樹の葉で覆われたドーム屋根の建物で、壁面には動植物の平面的で可愛らしい装飾が施され、正面玄関の上には、分離派のモットー「時代に芸術を、芸術に自由を」が掲げられている(写真5)。

【写真5】金色のキャベツ、とも呼ばれる分離派会館のドーム屋根
特徴的な外見に目を奪われるが、内部は、期間限定的な展覧会に対応できるように、トップライトの採光を用いて敢えてシンプルに設計され、ホワイトキューブと呼ばれる展示空間の先駆けともいわれている。

【写真6】ベートーヴェン第九の世界に没入
現在は、1902年の発表当時、音楽の冒涜として批判されたベートーヴェンの交響曲第9番をテーマにしたクリムトの壁画「ベートーヴェン・フリース」が常設展示され、ウィーン管弦楽団の演奏を聴きながら、彼の最高傑作の一つに没入できる空間となっている(写真6)。ここから少し歩くと、ワーグナーとその弟子が設計した集合住宅、バラの花のタイルを壁面に使ったマヨルカ・ハウスとメダルの装飾が施されたメダイヨン・ハウスがある(写真7)。

【写真7】並んで建つ「マヨルカ・ハウス」と「メダイヨン・ハウス」
旧市街東へと向かうと、必見なのが郵便貯金局。当時欧州で初めて郵便貯金という制度が導入され、革新的な建築をということでワーグナーの設計が採用されたという。大理石の外壁はアルミニウムの鋲で固定され、屋根や床材としてガラスが、そして支柱や上部の天使像にもアルミニウムが使われ、明るく優美な空間を生み出している。ワーグナーは、家具、クッション、照明器具、スイッチに至るまですべてデザインしたという。現在、建物内部は一般に開放され、ロビーのカフェで美しい曲線の梁を眺めることができる(写真8)。この建物の向かいには、バロック様式の重厚で厳めしい旧陸軍省があるが、こちらは郵便貯金局の7年後の完成である。旧市街地中心には、今でも店舗やオフィス、住居として使われているアール・ヌーヴォーの名建築が多数あり、街歩きをしながら探してみるのも楽しい(写真9)。

【写真8】アール・ヌーヴォー建築の代表作「郵便貯金局」内部

【写真9】天使の壁画が美しい
アール・ヌーヴォー建築「エンゲル薬局」
装飾は害悪だ!
一方、このように芸術的な装飾やデザインが特徴のアール・ヌーヴォー建築に背を向け、「装飾は害悪だ」と言い切った建築家、アドルフ・ロースもウィーンで活躍した。代表作の「ロース・ハウス」が、壮麗な王宮の旧市街側の向かいにある。建設当時、激しい批判を浴びたというが、そのシンプルさ故か周囲の歴史的な建築にも違和感なく溶け込んでいる(写真10)。

【写真10】装飾を排除した「ロース・ハウス」
時代は違うが同じような例で、聖シュテファン寺院の向かいに、現代建築家ハンス・ホラインの「ハース・ハウス」がある。ガラス張りの近代的な建築は、こちらも景観破壊だと着工前に大議論が起きたが、ガラスに聖シュテファン寺院が映り込み、不思議な統一性を醸し出しているのが面白い(写真11)。

【写真11】「聖シュテファン寺院」と隣接する現代建築「ハース・ハウス」
第二次世界大戦後、自然への回帰を目指し「ウィーンのガウディ」とも呼ばれたフリーデンスライヒ・フンデルトヴァッサーもウィーンの代表的な建築家である。前述の郵便貯金局の近くに、フンデルトヴァッサー設計の市営住宅や美術館「クンストハウス・ウィーン」があり、観光名所ともなっている。無機質な直線を排除し、くねくねとした線、曲線、渦巻模様に区切られたカラフルなタイルや鏡でできた外壁、奇妙なオブジェで装飾され、テラスや屋上には樹木が枝を伸ばす摩訶不思議な建物である。彼の建築は、宮崎駿の世界観にも大きな影響を与えたという。まるで遊園地のようなウィーン市の清掃工場も彼の作品で、日本でも大阪市舞州の清掃工場を設計している(写真12、13)。

【写真12】摩訶不思議なフンデルトヴァッサーの「クンストハウス・ウィーン」

【写真13】ハリゲンシュタット駅から見えるフンデルトヴァッサー設計の清掃工場の煙突
コンパクトシティ、ウィーン ― 栄光と苦難の歴史
主要な見どころと都市機能が千代田区とほぼ同じ広さに集中し、地下鉄、トラム、バス、鉄道といった公共交通網がくまなく整備されているウィーンは、コンパクトシティの見本ともいわれている。しかし、その背景には苦難、影の歴史がある。ウィーンは、ハプスブルグ帝国の興隆に伴い1900年代には人口が200万を超え、パリ、ロンドンに並ぶ欧州屈指の大都市だった。しかし、帝国の崩壊と第一次世界大戦後の混乱、ヒトラー政権下のドイツによる併合、徹底的なホロコースト、第二次世界大戦敗戦後の連合国による共同統治、永世中立国としての再出発、といった変遷を経て、人口は1990年代までに約150万まで減少してしまった。冷戦終結後、人口は増加に転じるが200万には達せず、期せずして、今もハプスブルグ帝国全盛期に整備された都市機能の多くを、そのまま活用することができているという。
また機能だけでなく、都市としての統一性や、その時代の先進的な建築と共に調和された街並みを保ち続けているのは、ウィーン市民や行政側の、かつて欧州文化を牽引していた帝都としての矜持なのかもしれない、ともふと思う。近年、美術史美術館隣接の旧帝国厩舎跡地が再開発されたが、オフィスビルやホテル、ショッピング・センターではなく、広いオープンな空間を維持しながら、近代美術館や建築情報センター、図書館、ギャラリーを集めた「ミユージアム・クォーター」と呼ばれるアートの集積地となった。一方で、再開発といえば空も敷地も巨大な高層ビルで埋め尽くす東京の近年の状況と比較すると、都市計画への理念の差を感じてしまうのは筆者だけだろうか。
戦いは他にさせよ
650年続いたハプスブルグ家の家訓は「戦いは他にさせよ、幸いなるオーストリアよ、結婚せよ」だ。争いではなく、婚姻と子孫繁栄によって領土を拡大した、今は亡き大帝国の首都ウィーン。古きも新しきも内包する美しい芸術都市の懐の深さには、こんな家訓も影響しているのかもしれない。
さて、最後に――ウィーンで忘れてはいけないのが、カフェ文化とスウィーツ。ウィーンには街中に様々な歴史的な所縁あるカフェがあふれている(写真14)。

【写真14】世界で一番美しいカフェとも呼ばれるルネサンス様式の美術史美術館のカフェ
カフェ・ザッハーのザッハートルテが有名だが、どのカフェにも、美味しくて可愛いスウィーツが並び選ぶのに迷うほど(写真15、16)。建築散歩に疲れたら、そんな栄光のハプスブルグ帝国が残したレガシーもぜひ味わってほしい。

【写真15】濃厚なチョコレートケーキ、ザッハートルテ

【写真16】老舗カフェ、ハイナー。
地元のおじ様達も朝からケーキ
※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部抜粋して公開しているものです。
当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。
調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。
ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード
神尾 友紀子の記事
関連記事
-

AIとマーケティング
- AI・人工知能
- ICR Insight
- WTR No442(2026年2月号)
- 生成AI
-

ICTが変える授業の形 ~複線型授業とICT
- GIGAスクール構想
- ICT利活用
- WTR No442(2026年2月号)
- 教育
- 日本
-

世界の街角から:真夏の海に浮かぶ"立体都市" ~長崎・軍艦島、半世紀後の生活の輪郭
- WTR No442(2026年2月号)
- 世界の街角から
- 日本
-

ソブリンAIを巡る各国の動向 ~制度・投資・地域連携に見る多様なアプローチ~
- AI・人工知能
- WTR No442(2026年2月号)
- 生成AI
-

超高齢社会における介護DXの可能性と課題
- DX(デジタルトランスフォーメーション)
- WTR No442(2026年2月号)
- 介護
- 医療
- 日本
- 福祉