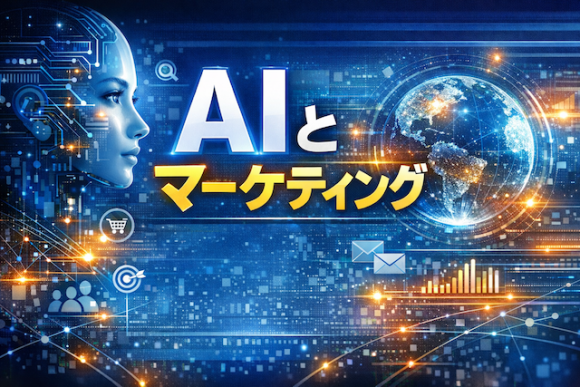中動態の視点から考える、これからのコミュニケーションのあり方

中動態という第三の視点
私たちが日常的に使う言葉には、行動や関係性の理解に深く関わる枠組みが組み込まれている。なかでも文法の「態」は、行為をどう捉えるか、主体と客体の関係をどう位置付けるかという点で象徴的だ。一般的に文法の「態」は、能動態の「私がする」、受動態の「私がされる」という二項構造に基づいており、現代の社会や制度もこの枠組みを前提として組み立てられている。
だが古代ギリシャ語には、「する」と「される」の区別では表現できない「中動態」という第三の態が存在していた。例えば「怒る」「恥じる」「恋をする」といった感情や行為は、自分の意志だけでも、他者からの影響だけでも説明しきれない。このような内側からの動きに巻き込まれた状態を表すのが中動態である。
興味深いのは、中動態的な構造がギリシャ語だけでなく、サンスクリット語や古典アラビア語など他の古代言語にも見られる点だ。そこでは人と世界が分かちがたく結びついており、行為は個人の意志に加え、状況や関係性の中で「起こるもの」として理解されていたようだ。
しかし現代社会では、行動の責任や帰属を明確にする方向へと傾き、「自己責任」や「自律的な選択」が強調されるようになった。もちろん、それが制度や規範の整備において重要な意味を持つのは確かだが、その一方で、私たちの内面の動きや曖昧な感情、葛藤といった複雑な人間性が見えにくくなっている。
中動態の視点は、こうした単純化された世界観に揺らぎを与える。明確な因果や帰属の外側にある「巻き込まれながらの行為」にこそ、リアルな人間存在のあり方が宿っているのかもしれない。
感情と身体の役割
私たちはしばしば「人生は自分の意志で選ぶもの」と考える。進路、仕事、パートナーなど、あらゆる選択が自己決定に基づくとされ、その結果には責任が伴う。だが、本当に私たちは完全に自律的に選んでいるのだろうか?
神経科学の研究によれば、人間の脳は過去の経験とそれに伴う感情を記憶し、いま受けている刺激が、次の判断に無意識のうちに影響を与えているという。例えば、過去に恥ずかしい思いをした場面を身体が覚えていて、似た状況では避けるようになる。これは意識的な判断だけではなく、身体の記憶といま受けている刺激が相互に結びついて、そのような状態になるのである。
つまり、私たちの行為とは「いまこの瞬間の意志」だけの結果というよりも、過去の経験と感情、この瞬間の刺激が複雑に絡み合ったプロセスの産物である。そのような見方に立てば、意志や選択については「主体が何かをする」ということに加えて「状況において自然に生じてくる動き」という観点も見逃せないと理解できる。
中動態はまさにそのような行為のあり方にフィットする概念だ。「選ぶ」という行為も、ただの能動ではなく、環境や身体、記憶に巻き込まれながら立ち現れる。この視点は、人間の行動をより深く、よりリアルに捉えるための足がかりとなる。
中動態的コミュニケーションの可能性
コミュニケーションは、私たちの関係性や世界との関わり方そのものを形づくっている。とりわけ「対話」においては、話す人と聴く人が互いに影響を与え合いながら、主体と客体といった直接的な二項対立だけでなく、その周辺からの間接的な影響を通じて、言語以外の形として、新たな意味や気づきを生み出していく。
悩みを語る人も、それを聴く人も、対話の中で内面に揺らぎが生じ、思考や感情が変化していく。「話すことで自分の思いに気づく」「聴いているうちに何かが動く」といった現象は、中動態的経験かもしれない。
さらに、こうした対話には感情や身体の反応も密接に関わっている。沈黙、ためらい、声の震えといった非言語的な表現が、対話において重要な意味を持つのは、私たちが身体ごと相手に向き合っているからだ。
このように対話は、単なる言葉としての意見交換を超え、話し相手との関係性、その人自身を深掘りする場になる。そこでの関係性は誰かが意図的に「つくる」ものではなく、共に「生まれてくる」ものとなる。対話が生み出す変化とは、まさにこのような生成のプロセスなのである。言語だけではないコミュニケーションの重要性を改めて理解できるのではないか。
ケアと教育における実践例
教育やケアの現場では、「教える―教えられる」「支援する―される」といった関係がしばしば前提とされるが、現実の現場ではその境界は往々にして曖昧である。例えば、教師が生徒から新たな視点を得ることもあれば、介護職が高齢者との関わりの中で深く心を動かされることもある。
こうした関係性は、一方的な力の行使ではなく、相互的な変容を含む。つまり、ケアや教育の本質もまた中動態的である。教えることは同時に学ぶことであり、支援することは同時に支えられることである。そこには明確な始点や終点、能動と受動の区別はない。
依存症支援の分野においても、正解を与えるのではなく、当事者が自らの語りを通して意味を再構築していく過程が重要視されている。その語りを聴く支援者もまた、自分の中にある偏見や理解を問い直すことになる。ここでは、「やめさせる」でも「やめさせられる」でもなく、「共に回復が起こる」というあり方が求められる。
中動態的な視点は、主体と客体、能動と受動では表現できない言語化されていない関係性や、無意識での心の動きを発見し、そこに人間の可能性を見る。変容は、一方が他方を変えるのではなく、「関係の中で共に変わる」ことによって生じるのである。
これからの社会に必要な対話のかたち
情報が高速で流れ、意見が断定的に発信される時代において、対話の質は大きな危機に直面している。SNSでは、見えている現象をベースにした「正しさ」や「勝ち負け」をめぐる言葉が飛び交い、じっくりと向き合う関係が築きにくくなっている。
だが、社会の複雑さが増す今、忘れてはならないのは、ある行動や発言の裏にそれを引き起こす何かがあるのではと必ず考えることではないだろうか? 例えば、学校で居眠りをしている生徒がいる場合、もしかしたらゲームで徹夜したかもしれないし、親が病気で、家計の助けのための深夜バイトで居眠りをしていたかもしれない。居眠りという表面に現れている行動の背景がわかると、居眠りへの接し方は変わってくる。さらに掘り下げると、ゲームで徹夜した生徒も、親が喧嘩していて寝られずにゲームで気を紛らわしたかもしれない。バイトでへとへとになったのは、その生徒のバイトに対するモチベーションの低下がもたらしたミスによるものかもしれない。これらを考慮するとまた見え方は違ってくる。
また、感情と身体の交差点としての対話を捉えることで、私たちは対話をより深く、より人間的なものとして回復することができる。話す/聴くという行為の背後にある身体の動きや記憶、感情の波を感じ取りながら、私たちはより相互に理解を深め、好ましい関係を構築するための新しい言葉を見いだすことができるだろう。
結びにかえて
ある文献にも指摘されているが、中動態と神経科学的視点の交差は、人間の行為や変容をより豊かに理解するための新しい地平を開く。そこでは「する」でも「される」でもない、自然とそうする、感じる、考えるということ、さらに、そのような行動や発言を生む背景が存在する。背景となる刺激の集合により、行動や発言が(意識的にも無意識的にも)生じると認識すれば、普段の生活で何を考え、何をなすべきかという指針を考える材料がより明確になるのではないか。今は見えていないことであっても、背景にあるものは何だろうか? とデフォルトで考える習慣が、コミュニケーションの質を上げる大きな一助になると考える。
※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部抜粋して公開しているものです。
当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。
調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。
ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード
木村 仁治の記事
関連記事
InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧
ランキング
- 最新
- 週間
- 月間
- 総合