ICTが変える授業の形 〜NEXT GIGAにおけるICTの現在地とこれから
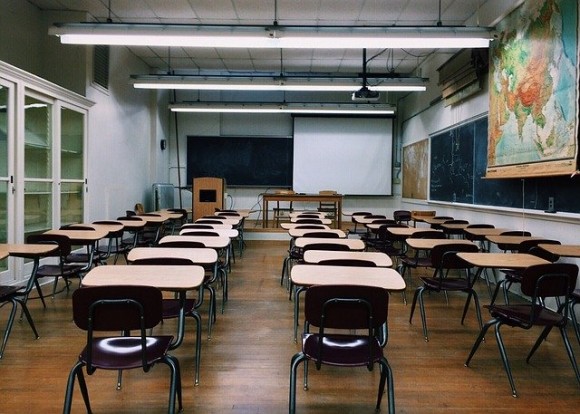
はじめに
2019年より開始されたGIGAスクール構想は、学校におけるICT環境に大きな変化をもたらした。それから数年が経過し、GIGAスクール構想をより深化させる取り組みとして、いわゆる“NEXT GIGA”と呼ばれる新たな取り組みが進められている。
本稿では現時点におけるGIGAスクール構想の現在地を整理するとともに、NEXT GIGAという新たなステージにおいて、ICTが果たすべき役割や可能性について見ていくこととする。
GIGAスクール構想の整備状況
図1は、文部科学省の調査[1]結果に基づき、学校における主なICT環境の整備状況について最新データをまとめたものである。
まず目に留まるのは、児童生徒1人当たりの学習用コンピューター台数が、小学校から高等学校、特別支援学校までの全校種において1.0台/人を上回っていることである[2]。これは言うまでもなく、GIGAスクール構想によって学習者用情報端末が児童生徒に行き渡った成果といえる。さらに、普通教室におけるネットワーク整備率も全校種でほぼ100%に達しており、ほとんどすべての普通教室でネットワーク接続が可能となっている。
このように、GIGAスクール構想の進展により、情報端末とネットワークの一体的な整備は全国の小・中・高等学校でほぼ達成されており、ICT環境は「整備」の段階から「活用」の段階へと移行していると言える。
GIGAスクール構想の成果と課題
GIGAスクール構想の進展によって、どのような成果が生まれ、またどのような課題に直面しているのだろうか。ここでは2025年1月に開催された「全国ICT教育首長サミット」の文部科学省による講演内容をもとに主な成果と課題を整理し、それぞれに対して筆者の補足コメントを加えていきたい。
まず、成果としては以下の4点が挙げられている。
【成果1】 世界に先駆け、わずか1~2年で整備完了
【成果2】 学力調査等にも効果
【成果3】 誰一人取り残されない学びの保障
【成果4】 単なる教育施策ではなく、我が国の重要施策のインフラ
成果1について、当初は5年間をめどとした段階的な整備計画であったが、コロナ禍による全国一斉休校への対応策として前倒しで整備が実施された。この特殊事情が追い風となったものの、結果として短期間で全国的なICT環境の整備が完了したことは、先進諸国と比較しても極めて異例と言えよう。
成果2については、全国学力・学習状況調査の分析により、ICT機器を積極的に活用し学びに取り組んでいる児童生徒ほど正答率が高い傾向があり、学習効果に関して肯定的な成果が確認された。さらに、児童生徒の約9割がICT活用に対し、「学習に役立つ」という効力感を持っていることも明らかになっている。
成果3については、拙稿「GIGAスクール構想とコロナ禍を経て、広がりをみせるオンライン授業」(本誌2023年4月号)でも述べたとおり、コロナ禍でのオンライン授業をきっかけに、様々な理由で学校に通えない児童生徒への学びの支援として、オンライン授業の活用が広がっている。
成果4については、単なる情報端末の配布にとどまらず、GIGAスクール構想によって整備されたICT環境が、教育DXやデジタル人材育成を推進するための基盤としても活用できることを示唆している。
一方、課題としては次の3点が指摘されている。
【課題1】地域・学校間で大きな活用格差
【課題2】端末更新・学校のICT環境(ネットワーク)の改善
【課題3】校務DXの推進
課題1について、GIGAスクール構想以前は、“整備”における格差が課題であったが、現在は環境が整ったことで“活用”における格差が新たに生じている。この格差は授業での活用頻度や活用内容といった学校内での利用状況のみならず、端末の家庭への持ち帰りや家庭での利用状況、さらには児童生徒が自らの意思でICT環境を自由に活用できる度合いなど、様々な側面において見られる。
課題2については、特にネットワークの通信速度が不十分な学校が多く存在していることが課題として指摘されている。令和5年度のデータによると、文部科学省が同時・多数・高頻度での端末活用を想定して設定した「当面の推奨帯域」を満たしていない学校は74.8%にのぼっている。文部科学省ではネットワークアセスメントや改修に向けた補助事業を実施しているが、早急な改善が求められる課題と言えよう。
課題3については、校務支援システムがクラウド化に対応していない学校も多く、教務データや学習データなど、他の教育データとの連携が困難になっている点が指摘されている。
InfoComニューズレターでの掲載はここまでとなります。
以下ご覧になりたい方は下のバナーをクリックしてください。
授業におけるICT利活用の現況
NEXT GIGAの方向性
※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部抜粋して公開しているものです。
[1] 文部科学省は「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」を例年3月に実施している。
[2] 全校種で1.0台/人をはじめて上回ったのは前回調査となる2024年3月である。
当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。
調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。
ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード
安藤 雅彦の記事
関連記事
-
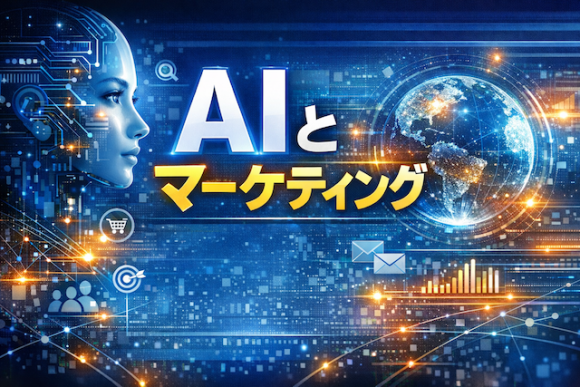
AIとマーケティング
- AI・人工知能
- ICR Insight
- WTR No442(2026年2月号)
- 生成AI
-

ICTが変える授業の形 ~複線型授業とICT
- GIGAスクール構想
- ICT利活用
- WTR No442(2026年2月号)
- 教育
- 日本
-

世界の街角から:真夏の海に浮かぶ"立体都市" ~長崎・軍艦島、半世紀後の生活の輪郭
- WTR No442(2026年2月号)
- 世界の街角から
- 日本
-

ソブリンAIを巡る各国の動向 ~制度・投資・地域連携に見る多様なアプローチ~
- AI・人工知能
- WTR No442(2026年2月号)
- 生成AI
-

超高齢社会における介護DXの可能性と課題
- DX(デジタルトランスフォーメーション)
- WTR No442(2026年2月号)
- 介護
- 医療
- 日本
- 福祉
ICT利活用 年月別レポート一覧
ランキング
- 最新
- 週間
- 月間
- 総合







