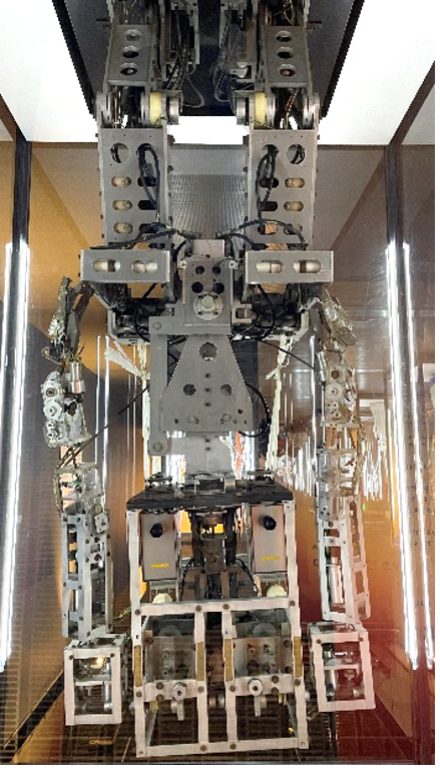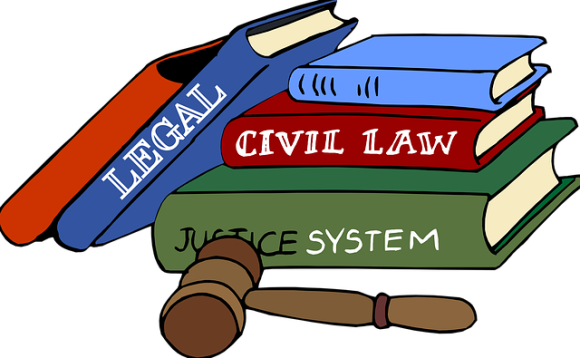ICT雑感:「Domo Arigato,Mr.Roboto」
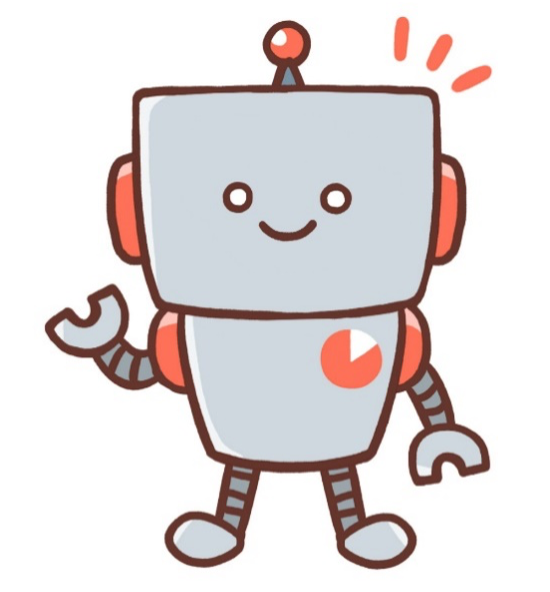
現在、都内において、ロボットの歩みを振り返り、ロボットと人間の関係を考察しようという展覧会が開かれています。たまたま駅のチラシで見て興味を持ち、先日行ってきました(注)。
単にロボット技術の発展を並べての時系列的展示で見せるというのではなく、現在のロボットがどこまで人間の代わりの役割や人間の機能のサポートができるようになっているのか、さらにはロボットと人間の比較を通して人間とは何なのかを探るという、かなり意欲的な内容でした。
会場では、「WABOT-1」のようなロボット開発史のレジェンドといえるようなロボットの展示だけでなく、「む~」のように人間とのコミュニケーションを行うロボットも紹介されていて、こうしたロボットたちに触れたり話しかけたりすることもできました。
中でも面白く感じたのは、2014年に誕生した「Pepper」です。もちろんその存在は知っていましたし、街角やイベントで見かけたこともありましたが、コミュニケーションをとってみたのは初めてでした。「感情を持った人間ロボット」という触れ込みがどういうことなのかよく解らなかったのですが、彼とお話をしたり頭をなでたりしてみました。すると、こちらの顔を見ながら受け答えをしたり、笑うような表情を見せたりしてくれるのです。
その「感情」の表現が、外からの刺激に対して疑似的なホルモンを出すことによって作られるという仕組みなのだそうで、そんな動物や人間などの生き物に通ずるメカニズムをロボットでやってみようという発想が大胆なものだと感じました。しかし、ロボットを人間に近づけよう、人間の友達になるようなロボットを生み出そうという目標からすると、ごく自然なチャレンジなのかもしれないですね。Pepperの誕生から既に8年が経過しており、現在の研究の最前線はどこまで行っているのか、気になります。
展覧会で展示されていたロボットの一部。

【図3】3体で会話しながら短くやさしい文章でニュースを伝えてくれる
ソーシャルなロボット「む~」
(出典:いずれも筆者撮影)
このような展示を観たことを踏まえて、ロボットの歴史の中で必ず出てくる文学作品にいくつか触れてみました。
「ロボット」という言葉が最初に登場したのは、チェコの作家カレル・チャペックの戯曲『ロボット(R.U.R.)』(1920年)においてであることはよく知られているところです。
……R.U.R.(ロッスムのユニバーサルロボット)社の製造する人造人間——ロボットは世界中に送られ、さまざまな労働に使われて、人々は便利な生活を享受するようになっていた。工場を訪れた同社会長の娘、ヘレナ(後に社長ドミンの妻になる。)は人間そっくりの姿をしたロボットが感情を持たないことにショックを受け、密かに開発者のガル博士に頼んで魂を持つロボットを作ってもらう。やがてロボットたちは連携を取り合い、「無能な」人間たちを抹殺してロボットが支配する世の中を実現すべく反乱を起こす……
今から100年以上前に書かれた作品で既に、映画『ターミネーター』シリーズでも取り上げられた、ロボットが発達した先に人間との関係がどうなるのか、ロボットが人間に対し反乱を起こすのではないか、あるいは現在盛んに論じられている、シンギュラリティが来るとどうなるのか、そういった論点が示されているのですね。作家の想像力の豊かさに驚かされます。なお、この戯曲では、ロボットが世界の支配者となったその先の、自己を製造する方法がわからず困ってしまうという物語の続きがありますので、興味ある方は作品を手に取ってみてください。
「ロボット工学の三原則」を示したことで有名なアイザック・アシモフの『われはロボット』(1950年)は、USロボット社のロボット心理学者スーザン・キャルビンの回想という形で、1990年代から2050年代までのロボットの発展と、ロボットと人間の関わりの進展が語られます。
……初期の家庭用のロボットは話すこともできなかった。子守りロボットのロビイもそうだが、子守りされる女の子グローリアは彼を一番の友達と思っている。母親はロボットを気味悪がり娘と引き離そうとするが、事故から女の子の命を助けることで家族の一員と認められる。その後もロボットは、ロボット工学の三原則のもとで人間との関係に悩み、ある時は奇怪な行動をとりつつ発達を遂げていく。やがて選挙を経て政治的指導者となったロボットは、人類が平和かつ安定的に暮らすのをプロデュースする(しかもその統治からロボット臭さを消すために、敢えて少しの混乱を演出する)ようになった……
小説の語りの中に、将来のディープラーニングの技術を予言するような以下のくだりがありました。「数学者のグループが数年がかりで、陽電子頭脳を作るために計算をし、陽電子頭脳に、それと類似の計算をする機能をあたえる。この頭脳を用いて計算を行ない、それよりはるかに複雑な頭脳を作りあげ、そしてまたできあがったその頭脳を用いてまたはるかに複雑な頭脳を作るという仕事を繰り返す」。一方でこうも語っています。「マシンはしょせん機械です。計算とか判定という重荷を人間の方からとりさることによって人間の進歩を早める役には立ちますよ。しかし、人間の脳の仕事は相変わらず残っている。つまり、分析すべき新しいデータを発見すること、検査する新しい概念を発見することだ」。ロボットと人間の関係は、これからも概ねアシモフの想像したようなコンテクストで進んでいくような気がします。
ちょっと趣向は変わりますが、洋楽ファンが「ロボット」という言葉を聞くとまず思い浮かべるのが、80年代初頭に「産業ロック」の一翼を担っていたスティクス(Styx)の『ミスター・ロボット』(Mr. Roboto)(1983年)でしょう。
……ロックスターのキルロイは、ロック音楽がアメリカを堕落させたと主張し迫害する団体のために捕えられ刑務所に入り、看守ロボットに監視されている。ロックを蘇らせようとする地下組織のメッセージを受け取った彼は、ロボットを乗っ取りロボットに変装して脱獄を図る。ロックのため、自由のため……
いきなり日本語で「♪ドモアリガト、ミスターロボット、マタアウヒマデ~」と始まるこの曲は大ヒットしたものの、あまりに突飛な内容が引かれたのか、彼らはその後ミュージックシーンの第一線から消えていきました。当時のエンタメではロボットなどのテクノロジーと人間の関係がネガティヴに捉えられる傾向があったそうで、そういえば『ターミネーター』も1984年の作品ですね。
曲の中ではロボットについて“with parts made in Japan……”と歌われていて、当時のロボットのテクノロジーは我が国がリードしていたことを反映していますが、これからもそうであってほしいと思いますし、ロボットと人間の関係が「Domo Arigato」と感謝しあえるような未来であってほしいと思います。この曲のコミカルなPVもネットで直ぐに観られるので、ちょっと手の空いた時などにご覧になってみてください。
(主な参考文献等)
- 『特別展 きみとロボット ニンゲンッテ、ナンダ? 公式ブック』
- 『ロボット(R.U.R.)』(カレル・チャペック著、千野栄一訳、岩波文庫、1989)
- 『われはロボット』〔決定版〕(アイザック・アシモフ著、小尾芙佐訳、ハヤカワ文庫SF、2004)
- 「Mr.Roboto」(Styx アルバム“Kilroy Was Here”収録)
(注)特別展「きみとロボット ニンゲンッテ、ナンダ?」は、2022年3月18日から8月31日までの予定で、お台場の日本科学未来館にて開催されています。(2022年7月13日時点の情報)
※この記事は会員サービス「InfoCom T&S」より一部無料で公開しているものです。
当サイト内に掲載されたすべての内容について、無断転載、複製、複写、盗用を禁じます。InfoComニューズレターを他サイト等でご紹介いただく場合は、あらかじめ編集室へご連絡ください。また、引用される場合は必ず出所の明示をお願いいたします。
調査研究、委託調査等に関するご相談やICRのサービスに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。
ICTに関わる調査研究のご依頼はこちら関連キーワード
川淵 幹児の記事
関連記事
-

デジタル技術を活用したウェルビーイング(Well-being)の向上
- WTR No441(2026年1月号)
- ヘルスケア・医療
- 日本
-

世界の街角から:豪州 ウルル・シドニー ~大自然と歴史を感じる
- WTR No441(2026年1月号)
- オーストラリア
- 世界の街角から
-

通信事業者は6Gをスマートパイプへのチャンスに
- 5G/6G
- AI・人工知能
- ICR Insight
- WTR No441(2026年1月号)
- モバイル通信事業者(国内)
- モバイル通信事業者(海外)
-

中国におけるロボット産業の進展
- WTR No441(2026年1月号)
- ロボット
- 中国
-

ポイント経済圏事業者の2026年戦略アジェンダ 〜消費者の利用実態調査より〜
- WTR No441(2026年1月号)
- ポイントビジネス
- 日本
- 経済
- 金融
InfoCom T&S World Trend Report 年月別レポート一覧
ランキング
- 最新
- 週間
- 月間
- 総合